日々の業務に追われ、口腔ケアは後回しになりがちだと感じていらっしゃる方もいますよね?介助をしようとしても抵抗されたり、その効果が実感しにくかったりすることから、「ただの作業」のように感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、その口腔ケアこそが、利用者の命を守る重要なケアです。厚生労働省の資料では、口腔ケアを怠り口腔内が不潔な状態にあると、それが誤嚥性肺炎の誘因となる、と示されています。日々の小さな積み重ねは、肺炎などのリスクを低減させるだけでなく、食事をおいしく食べる喜びにも繋がり、日本老年歯科医学会のマニュアルでも示されているように生活の質(QOL)の向上に資する専門的な技術なのです。
この記事を読んで分かる事
この記事では、口腔ケアがなぜ重要なのかという明確な根拠から、多忙な中でも安全かつ確実に行うための具体的な手順、そして利用者がケアを拒否するといった現場の悩みへの対処法まで、明日から実践できる5つのポイントに絞って解説します。
結論:「口腔ケアは5つのポイントを押えるだけ」で安全・確実な専門技術になる

日々のケアに追われる中でも、利用者の安全と健康を守るために押さえておきたいのが口腔ケアの基本です。難しく考える必要はありません。これからご紹介する5つのポイントを実践するだけで、ケアの質は大きく向上します。
ポイント1:誤嚥を防ぐ「安全な姿勢」を確保する
口腔ケアで最も優先すべきは、誤嚥を予防することです。一般社団法人 日本老年歯科医学会の「介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル」では、ケアの姿勢は、原則として座位または半座位(ファーラー位:ベッドを30~45度起こした状態)で行う、と具体的に示されています。これにより、唾液や水分が気管に流れ込むリスクを物理的に低減させ、安全なケアを実現します。体調などにより座位が難しい場合でも、できるだけ上半身を起こすことが重要です。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 歯ブラシは「ヘッドが小さく」、毛の硬さは「やわらかめ」か「ふつう」を基本とし、歯磨剤は「発泡剤や清涼剤の少ない低刺激性」のものが望ましい。
- 誤嚥の予防のために、ケアを行う際の姿勢は原則として「座位または半座位(ファーラー位:ベッドを30~45度起こした状態)」で行う。
- う蝕予防には「フッ化物配合歯磨剤」が効果的である。
ポイント2:利用者に合った「適切な道具」を選択する
道具の選択一つで、ケアの効果と利用者の快適さは大きく変わります。同マニュアルでは、歯ブラシはヘッドが小さく、毛の硬さは「やわらかめ」か「ふつう」が基本であると推奨しています。これは、口の隅々まで届きやすく、歯肉を傷つけないためです。また、歯磨剤は発泡剤や清涼剤の少ない低刺激性のものを選ぶことで、すすぎが困難な方でも不快感を覚えにくくなります。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 歯ブラシは「ヘッドが小さく」、毛の硬さは「やわらかめ」か「ふつう」を基本とし、歯磨剤は「発泡剤や清涼剤の少ない低刺激性」のものが望ましい。
- 誤嚥の予防のために、ケアを行う際の姿勢は原則として「座位または半座位(ファーラー位:ベッドを30~45度起こした状態)」で行う。
- う蝕予防には「フッ化物配合歯磨剤」が効果的である。
ポイント3:歯だけでなく「舌や粘膜」も清掃・観察する
口腔ケアは歯を磨くだけで終わりではありません。厚生労働省の資料では、口腔内の細菌が増殖することが誤嚥性肺炎の誘因となることが示唆されています。細菌の温床となりやすい舌苔(ぜったい)の清掃や、頬の内側・上あごといった粘膜部分の清掃も重要です。また、ケアの際には歯肉からの出血や腫れ、口内炎などの異常がないかを「観察」することで、口腔トラブルの早期発見に繋がります。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 口腔ケアの際には、歯や歯肉だけでなく、舌、頬粘膜、口蓋などの口腔軟組織の状態も観察し、異常の早期発見に努めることが大切である。
- 特に舌苔の付着は口臭や味覚障害、細菌の温床となるため、舌ブラシやスポンジブラシを用いて清掃することが推奨される。
- 口腔ケアは清掃だけでなく、口腔内の健康状態を把握する「アセスメント(評価)」の機会でもある。
ポイント4:「義歯(入れ歯)」は洗浄剤を併用し、外した後の口腔内もケアする
義歯の管理は口腔ケアの重要な一部です。義歯に付着するヌメリ(バイオフィルム)は、日本老年歯科医学会のマニュアルによると、義歯ブラシだけでは除去できないため、義歯洗浄剤を併用することが不可欠です。また、義歯を外した後の顎の粘膜を清掃することも忘れてはなりません。粘膜を清潔に保つことで、カンジダ菌などによる感染症(義歯性口内炎)を防ぎます。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 義歯(入れ歯)は毎食後、就寝前に外して清掃し、流水下で義歯ブラシなどを用いて機械的に汚れを除去することが基本となる。
- 義歯に付着したヌメリ(バイオフィルム)はブラッシングだけでは除去が困難なため、「義歯洗浄剤を併用」することが極めて重要である。
- 口腔乾燥が認められる入所者には、保湿剤を積極的に使用する。
ポイント5:清掃だけでなく「保湿と機能訓練」も意識する
口腔ケアには、口腔内を清潔にする「器質的口腔ケア」だけでなく、口腔機能の維持・向上を目指す「機能的口腔ケア」も含まれます。口の乾きが見られる場合は、保湿剤を積極的に使用します。また、唾液の分泌を促す唾液腺マッサージなども有効です。これらは口の中の潤いを保ち、食事や会話をスムーズにするなど、利用者の生活の質を高める上で重要な役割を果たします。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 口腔ケアは「器質的口腔ケア」と「機能的口腔ケア」に大別される。
- 器質的口腔ケアは口腔清掃を指し、口腔内の細菌数を減少させることでう蝕や歯周病、感染症を予防する。
- 機能的口腔ケアは摂食嚥下機能などの維持・向上を目的とした訓練やリハビリテーション(例:唾液腺マッサージ)を指す。
このように、一つひとつのポイントには明確な根拠があります。これらを意識するだけで、日々の口腔ケアは「作業」から利用者の安全と健康を守る「専門技術」へと変わります。
事例:現場で考えられる「口腔ケア」をめぐる3つのケース

理論や手順だけでなく、実際の現場で口腔ケアがどのように影響するのか、具体的なケースを通じて見ていきましょう。日々のケアが利用者の生活に与える変化をイメージしやすくなります。
ケース1:「最近よくむせる」Aさんの肺炎リスク
Aさんは、食事の際にむせることが増え、微熱を繰り返していました。口腔内を確認すると、清掃が不十分で乾燥も進んでいる状態でした。厚生労働省の資料では、口腔内の細菌などが唾液と共に気管に入ってしまうことが誤嚥性肺炎の原因であると示されています。Aさんの状態は、まさにこのリスクが高まっている状況でした。ケアの見直しと専門職による介入で口腔内が清潔に保たれるようになると、発熱の頻度が減り、体調も安定していきました。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
- 高齢者において肺炎による死亡率は上昇傾向にあり、その多くは「誤嚥性肺炎」である。
- 誤嚥性肺炎は、「口腔内の細菌などが、唾液や胃液などとともに、気管に入ってしまうこと」が原因で発症する。
- 特に高齢者は睡眠中に無意識に唾液などを誤嚥する「不顕性誤嚥」を起こしやすく、口腔内が不潔だと増殖した口腔常在菌が肺炎の誘因となる。
ケース2:「食事を嫌がる」Bさんの隠れた原因
Bさんは最近、好きだったものもあまり食べなくなり、食事介助に抵抗することが増えていました。口腔ケアの際に義歯を外して確認したところ、歯ぐきの一部が赤く腫れているのが見つかりました。日本老年歯科医学会のマニュアルでは、義歯が合わない状態を放置すると、痛みによる食事摂取量の低下や、栄養状態の悪化を招くとされています。この発見を歯科医師に繋げ、義歯を調整したことでBさんの痛みがなくなり、再び食事を楽しめるようになりました。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 義歯が合わない(不適合)状態を放置すると、痛みによる食事摂取量の低下や、栄養状態の悪化を招く。
- うまく噛めないことで、柔らかいものばかりを食べるようになり、咀嚼機能や嚥下機能の低下(廃用)につながる恐れがある。
- 介護職員は、利用者の「痛い」「食べにくい」という訴えや、食事中の様子から義歯の不適合を早期に発見し、歯科受診につなげる役割が期待される。
ケース3:「会話が減った」CさんのQOL低下
以前は談話室でおしゃべりを楽しんでいたCさんですが、次第に口数が減り、ふさぎ込みがちになりました。ケアの際に強い口臭が気になり、舌の汚れ(舌苔)も目立っていました。厚生労働省の資料にもあるように、食べる楽しみは生きる喜びに直結し、口腔機能は会話といった機能面や生活の質(QOL)の維持・向上という観点からも重要です。丁寧な清掃と保湿ケアを継続したところ、口臭が改善。Cさんの口腔内の不快感が和らいだことで、再び笑顔で会話する姿が見られるようになりました。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
- 高齢者の口腔機能の維持・向上は、衛生管理だけでなく、摂食・嚥下、会話といった機能面や、「生活の質の維持・向上」の観点からも重要である。
- 口腔機能の低下は「低栄養」を引き起こし、それが全身の筋力低下(サルコペニア)や心身の活力が低下した状態(フレイル)へと繋がる。
- 「食べる楽しみは生きる喜びに直結」するため、口腔機能を支えることは高齢者の尊厳を守るケアと言える。
これらのケースが示すように、口腔ケアは単なる清掃作業ではありません。利用者の全身の健康、そして穏やかな日常を守るための、観察に基づいた重要な専門的介入なのです。
理由:なぜ口腔ケアは「命を守る」と言えるのか?3つの科学的根拠
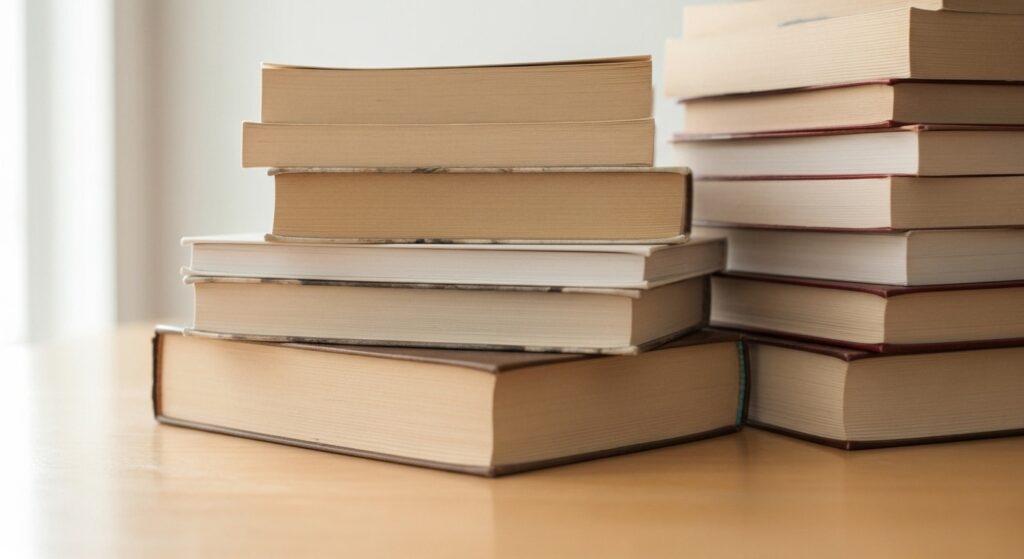
日々のケアがなぜそれほど重要なのか、その背景には明確な科学的根拠があります。ここでは、口腔ケアが利用者の「命」と「生活」に直結する3つの理由を、公的な資料を基に解説します。
根拠1:誤嚥性肺炎のリスクを直接的に低減するため
最大の理由は、誤嚥性肺炎のリスクを直接的に低減できる点にあります。厚生労働省の資料は、高齢者の肺炎の多くが誤嚥性肺炎であり、その原因は口腔内の細菌が唾液などと共に気管に入ることだと示しています。特に睡眠中などに無意識に起こる「不顕性誤嚥」は、口腔内が不潔だと肺炎発症の直接的な誘因となります。歯科専門職による専門的口腔ケアが肺炎発症率の抑制につながる可能性を示唆する研究もあり、日々のケアがいかに重要かが分かります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
- 誤嚥性肺炎は、「口腔内の細菌などが、唾液や胃液などとともに、気管に入ってしまうこと」が原因で発症する。
- 口腔内が不潔だと増殖した口腔常在菌が肺炎の誘因となる。
- 歯科専門職による専門的口腔ケアは、口腔内の細菌を減少させ、「肺炎発症率の抑制につながる可能性がある」ことが示唆されている。
根拠2:低栄養や全身疾患の連鎖を断ち切るため
口腔の状態は、口の中だけの問題では終わりません。厚生労働省の資料では、歯周病が糖尿病や動脈硬化性疾患などと相互に影響を及ぼしあうことが指摘されています。また、噛む力が弱まるなど口腔機能が低下すると、食事が十分に摂れず低栄養の状態となり、それが全身の筋力低下(サルコペニア)やフレイル(虚弱)に繋がるという悪循環に陥ります。口腔ケアは、この負の連鎖を断ち切るための重要な介入です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
- 口腔と全身の状態は密接に関係しており、歯周病は、糖尿病、動脈硬化性疾患などと相互に影響を及ぼしあうことが指摘されている。
- 口腔機能の低下は「低栄養」の原因となり、全身の筋力低下(サルコペニア)や、心身の活力が低下した状態(フレイル)につながる。
- 歯周病の患者では糖尿病である確率が高く、また、糖尿病の患者は歯周病に罹患しやすく、重症化しやすい。
根拠3:QOL(生活の質)と尊厳を維持するため
清潔で快適な口腔環境は、利用者の生活の質(QOL)に直結します。厚生労働省の資料が示すように、「食べる楽しみは生きる喜びに直結」します。口の中が健康であれば、食事をおいしく味わえ、それが生きる喜びや意欲に繋がります。また、口臭の改善や滑舌の維持は、他者との円滑なコミュニケーションを可能にし、社会的な孤立を防ぎます。口腔ケアは、利用者がその人らしく、尊厳ある生活を送るための基盤を支えるケアなのです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
- 高齢者の口腔機能の維持・向上は、衛生管理だけでなく、摂食・嚥下、会話といった機能面や、「生活の質の維持・向上」の観点からも重要である。
- 「食べる楽しみは生きる喜びに直結」するため、口腔機能を支えることは高齢者の尊厳を守るケアと言える。
- 口腔機能の低下は低栄養の原因となり、フレイルにつながる。
このように、口腔ケアは科学的根拠に裏付けられた、多角的な効果を持つ重要なケアです。これらの理由を理解することで、日々の実践への意識もさらに高まるはずです。
よくある質問:介護士の疑問に答える!口腔ケアQ&A
ここでは、多くの介護士さんが現場で直面する具体的な疑問にお答えします。理論だけでは解決しにくい悩みも、根拠を知ることで対応の引き出しが広がります。
- Q利用者さんが全力でケアを拒否します。どうすればいいですか?
- A
無理強いはせず、まずは拒否の理由をアセスメントすることが重要です。日本老年歯科医学会のマニュアルでは、拒否の理由として、認知機能の低下による不理解、口内の痛みや不快感、過去の嫌な経験などが考えられるとされています。まずは口の中に痛みがないか、不安を感じていないかなどを探り、安心できる関係性を築くことから始めましょう。時間や担当者を変えるなどの工夫も有効です。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 口腔ケアを拒否する入所者への対応は、まず「拒否の理由をアセスメントすること」が重要である。
- 理由としては、「認知機能の低下によりケアの意味が理解できない」「口の中に痛みや不快感がある」「過去の経験から不安や恐怖を感じる」などが挙げられる。
- 無理強いはせず、時間や場所、担当者を変える、まずは会話から始めるなどの工夫で、安心できる関係性を築くことが求められる。
- Q歯磨きが難しい場合、うがいだけでも大丈夫ですか?
- A
うがいは口内の爽快感を得るのに役立ちますが、決して十分ではありません。義歯などに付着するネバネバした汚れの膜(バイオフィルム)は、日本老年歯科医学会のマニュアルが示すように、歯ブラシなどを用いた機械的な清掃でなければ除去できません。うがいが困難な場合は、口腔ケア用のウェットティッシュで拭うなどの代替案を検討します。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 義歯(入れ歯)は毎食後、就寝前に外して清掃し、流水下で義歯ブラシなどを用いて機械的に汚れを除去することが基本となる。
- 義歯に付着したヌメリ(バイオフィルム)はブラッシングだけでは除去が困難なため、「義歯洗浄剤を併用」することが極めて重要である。
- 口腔乾燥が認められる入所者には、保湿剤を積極的に使用する。
- Q義歯の洗浄は、水洗いだけではダメなのでしょうか?
- A
水洗いだけでは不十分です。日本老年歯科医学会のマニュアルでは、義歯のヌメリ(バイオフィルム)は義歯ブラシだけでは除去できないため、義歯洗浄剤を併用することが極めて重要だとされています。洗浄剤は、目に見えない細菌やカンジダ菌などを化学的に分解・殺菌し、義歯性口内炎などの感染症を防ぐために不可欠です。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 義歯(入れ歯)は毎食後、就寝前に外して清掃し、流水下で義歯ブラシなどを用いて機械的に汚れを除去することが基本となる。
- 義歯に付着したヌメリ(バイオフィルム)はブラッシングだけでは除去が困難なため、「義歯洗浄剤を併用」することが極めて重要である。
- 口腔乾燥が認められる入所者には、保湿剤を積極的に使用する。
- Q口の中がカラカラに乾いている方への対応は?
- A
口腔乾燥は、う蝕や歯周病のリスクを高めるだけでなく、会話や嚥下の困難にも繋がります。日本老年歯科医学会のマニュアルでは、口腔乾燥が認められる場合には、スプレーやジェルタイプの保湿剤を積極的に使用することが推奨されています。また、唾液の分泌を促す「唾液腺マッサージ」も有効です。薬の副作用が原因の場合もあるため、看護師などと情報共有することも重要です。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 口腔乾燥が認められる場合には、保湿剤を積極的に使用します。保湿剤には、スプレータイプ、ジェルタイプ、マウスウォッシュタイプなどがあります。
- 唾液腺マッサージは、唾液の分泌を促進させることを目的に行います。耳下腺、顎下腺、舌下腺をマッサージします。
- 口腔ケアを拒否する入所者への対応は、まず拒否の理由をアセスメントすることが重要です。
- Qどんな状態になったら歯科医など専門職に相談すべきですか?
- A
日々のケアの中で、介護職員だけでは対応が難しい状況に気づくことは多々あります。例えば、「歯ぐきからの出血が続く」「義歯が明らかに合っておらず、食事に支障が出ている」「口の中に治りにくい口内炎やできものがある」といった場合です。日本老年歯科医学会のマニュアルでは、多職種連携が重要だとされており、こうした専門的な判断が必要なサインを見つけた際は、看護師やケアマネジャーに報告・相談し、歯科受診に繋げることが利用者の健康を守るために不可欠です。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 義歯が合わない(不適合)状態を放置すると、痛みによる食事摂取量の低下や、栄養状態の悪化を招く。
- うまく噛めないことで、柔らかいものばかりを食べるようになり、咀嚼機能や嚥下機能の低下(廃用)につながる恐れがある。
- 介護職員は、利用者の「痛い」「食べにくい」という訴えや、食事中の様子から義歯の不適合を早期に発見し、歯科受診につなげる役割が期待される。
日々の小さな疑問を放置せず、根拠を持って対応することが、ケアの質の向上とトラブルの予防に繋がります。あなたの「気づき」が、利用者を守る第一歩です。
まとめ:「作業」から「専門技術」へ――明日から始める口腔ケアの第一歩
最後に、この記事の要点を振り返ります。日々の口腔ケアに対する意識が少しでも変われば、あなたのケアはさらに専門的で、価値のあるものへと進化します。
この記事の要点
口腔ケアは、単なる口の清掃作業ではありません。厚生労働省や日本老年歯科医学会の資料が示すように、誤嚥性肺炎を予防し、全身の健康状態を維持し、そして利用者の生活の質(QOL)と尊厳を守るための、科学的根拠に基づいた専門的な介入です。この視点を持つことが、プロフェッショナルな介護の第一歩となります。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 介護保険施設等入所者の口腔の健康を維持・増進し、「誤嚥性肺炎の予防」「経口摂取の維持」「QOLの向上」に資することを目的とする。
- 中心となる考え方は「口腔ケア・マネジメント」であり、入所者一人ひとりの状態を踏まえ、多職種が連携して継続的に口腔を管理するプロセスを指す。
- このマネジメントの実践は、介護報酬における「口腔衛生管理体制加算」や「口腔衛生管理加算」の算定に繋がる。
今日からできること
明日から、ぜひ利用者の口の中を意識的に「観察」することから始めてみてください。食事の様子、口臭、舌の色、歯ぐきの状態など、小さな変化に気づくことが、専門的なケアの始まりです。日本老年歯科医学会のマニュアルが示すように、口腔ケアは清掃だけでなく、健康状態を把握する「アセスメント(評価)」の機会でもあります。あなたのその気づきが、利用者を多くのリスクから守ります。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会 介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル(2019 年度版) https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf
- 口腔ケアの際には、歯や歯肉だけでなく、舌、頬粘膜、口蓋などの口腔軟組織の状態も観察し、異常の早期発見に努めることが大切である。
- 特に舌苔の付着は口臭や味覚障害、細菌の温床となるため、舌ブラシやスポンジブラシを用いて清掃することが推奨される。
- 口腔ケアは清掃だけでなく、口腔内の健康状態を把握する「アセスメント(評価)」の機会でもある。
この記事が、あなたの毎日のケアに新たな視点をもたらし、利用者一人ひとりの豊かな生活を支える一助となれば幸いです。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月8日:新規投稿



