声掛けが正しいか不安だと感じている方、いらっしゃいますよね?
これは「認知症の声掛けシリーズ第3弾」です。今回のテーマは「血管性認知症(VaD)」に焦点を当てます。介護の現場では、昨日できたことが今日は難しい、感情が急に爆発する、歩行が不安定で声掛けにも緊張感が伴う——そんな経験をされている方も多いと思います。
結論として、血管性認知症は注意力・遂行機能の低下、感情失禁、身体症状が前景に出やすく、声掛けには「短文・一指示・二択・視覚化」の工夫が必須です。厚生労働省の意思決定支援ガイドラインでは「本人の価値観を基点にした支援」が求められ、日本神経学会/Mindsの診療ガイドライン2017でも「血管性認知症はアルツハイマー型と異なり、階段状進行や局所症状を重視する」と記されています。

この記事を読んで分かる事
血管性認知症の特徴とアルツハイマー型との違い、部位ごとの症状の違い、現場で使える「短文・一指示・二択・視覚化」の声掛け実例が理解できます。
結論:短文・一指示・二択・視覚化を標準化する
忙しい現場で「昨日は通じたのに今日は拒否…」という揺れに困りますよね。血管性認知症では段取りと身体症状を踏まえ、声掛けの型を全員でそろえることが要点です。

基本原則の統一
血管性認知症では刺激に敏感な場面が多く、「驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない」を徹底します。大阪府の資料では、背後から声をかけず目線を合わせ、ゆっくり・はっきり伝えることが良いと言われています。まずは短文で一つだけ指示し、成功直後に具体的称賛で次行動へつなぎます
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
「驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない」を基本原則とし、背後からの声掛け回避、目線合わせ、ゆっくり明瞭な話し方、原則1人での声掛けなど、初期接近から誘導までの具体策を示しています。現場で再現しやすい短い行動指針が整理され、拒否や混乱の予防につながる内容です。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
意思決定支援を軸にした声掛け
厚生労働省のガイドラインでは、本人の価値観を基点に合意形成を行うと言われています。声掛けも「何を優先したいか」を確かめ、選択肢を提示するなど負担の少ない形で意思を確認し、合意形成につなげます(例:「今は靴下にしますか、上着にしますか」)。合意→実行→振り返りの循環をチームで共有し、納得感と受け入れ率を高めます
※エビデンス
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の価値観・生活歴に基づく意思形成を支援し、情報収集→合意形成→実行→振り返りのプロセスと配慮点を提示。非言語サインへの注意、恥や不安への配慮、丁寧なコミュニケーションが意思決定の質と生活の納得感を高めると整理されています。現場の合意形成に直結する実践的手引きです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
病型差を見越した段取り設計
日本神経学会/Mindsのガイドラインでは、血管性認知症は階段状進行や局在徴候が重要と言われています。ゆえにADと同じ説明・手順では通りにくい場面が生じます。一度に一つの手順と視覚手がかり(カード・掲示)を併用し、日による揺れに合わせて小刻みに進めます
※エビデンス
日本神経学会/Minds
認知症疾患診療ガイドライン2017
認知症各病型の臨床像・鑑別・評価を体系化。血管性認知症は脳血管障害の存在、階段状あるいは動揺性の経過、局所神経徴候が重視され、ADの緩徐進行・記憶障害優位とは異なると明確化。非薬物的アプローチやケアの留意点も提示し、病型差を踏まえた段取り設計の必要性を裏づけています。
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00408/
締めとして、まずは「予告→一指示→称賛」の小さな型をチームで共有しましょう。同じ言葉と手順をそろえるだけで、受け入れ率と安心感が着実に上がります。
事例:現場でよくあるケース3選――“通らない”を“通る”に変える
忙しい現場で使える、認知症の声掛け(血管性認知症向け)の具体例です。どれも「短文・一指示・二択・視覚化」を軸に、予告→実行→称賛の流れで安定化させます。

よくあるケース1:外出準備が進まない
外出前、途中で気が逸れて止まってしまうケース。大阪府の資料では「背後から声をかけない・目線を合わせる・ゆっくり明瞭に」と言われています。そこで時間の予告と二択を組み合わせ、一度に一つの指示で段取りを整えます。
- 例:「10時に出発します。まず靴下にしますか、上着にしますか」→できたら具体的称賛→次の一手へ
- ポイント:視覚化(出発カード・チェックリスト)で手順の見通しを共有
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
「驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない」を基本に、背後からの声掛け回避、目線合わせ、ゆっくり明瞭な話し方、原則一人での声掛け、確認しながら進める姿勢が示されています。初期接近から誘導までの具体的留意点が整理され、拒否や混乱の予防に資する内容です。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
よくあるケース2:食事でむせ込みやすい
食事中にペースが乱れてむせ込みが増えるケース。臨床神経学の総説では皮質下血管性認知症で偽性球麻痺や嚥下関連の問題がみられると言っています。順番の言語化(一口→飲む→一息)と話速を落とす対応で安全と安心を両立します。
- 例:「まず一口食べましょう→お茶を一口→少し休みましょう」
- ポイント:食器の配置を視覚化し、同時処理を避ける
※エビデンス
三重大学大学院医学系研究科神経病態内科
皮質下血管性認知症の診断と治療
白質病変やラクナ梗塞を背景とする皮質下血管性認知症では、遂行機能障害、歩行障害、感情失禁に加え、偽性球麻痺や失禁などの症状が併発しやすいと整理。経過は緩徐または階段状で、危険因子管理とリハビリ・非薬物的対応の意義が示されます。食事場面でも段取り化が有効である根拠になります。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/50/8/50_8_539/_pdf
よくあるケース3:トイレ誘導で拒否が強い
羞恥心が刺激されやすい場面。厚生労働省のガイドラインでは「本人の価値観を基点に合意形成する」と言われています。前方から目線を合わせ、二択で選びやすくし、同伴の範囲を明確化して安心を伝えます。
- 例:「今のうちに済ませましょう。個室までご一緒します。中ではお待ちします」
- ポイント:環境の見える化(案内表示)、プライバシー配慮の言語化
※エビデンス
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の価値観・生活歴に基づく意思形成を支援し、情報収集→合意形成→実行→振り返りのプロセスと配慮点を提示。非言語サインへの注意、恥や不安への配慮、丁寧なコミュニケーションが意思の反映と納得感を高めると整理され、トイレ誘導でも合意を基点とする声掛けが推奨されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
この3つのケースは、認知症の声掛け(血管性認知症)で再現しやすい基本形です。まずはチームで同じ言葉と手順を共有し、小さな成功を積み重ねましょう。
理由:なぜこの声掛けが効くのか――根拠と背景
血管性認知症では、脳梗塞や脳出血などによる脳血管障害の影響で「できる・できない」が揺れ動きやすくなります。そのため、声掛けの仕方が結果を大きく左右します。ここでは、なぜ血管性認知症が起こるのか、そしてなぜ「短文・一指示・二択・視覚化」が有効なのかを整理します。
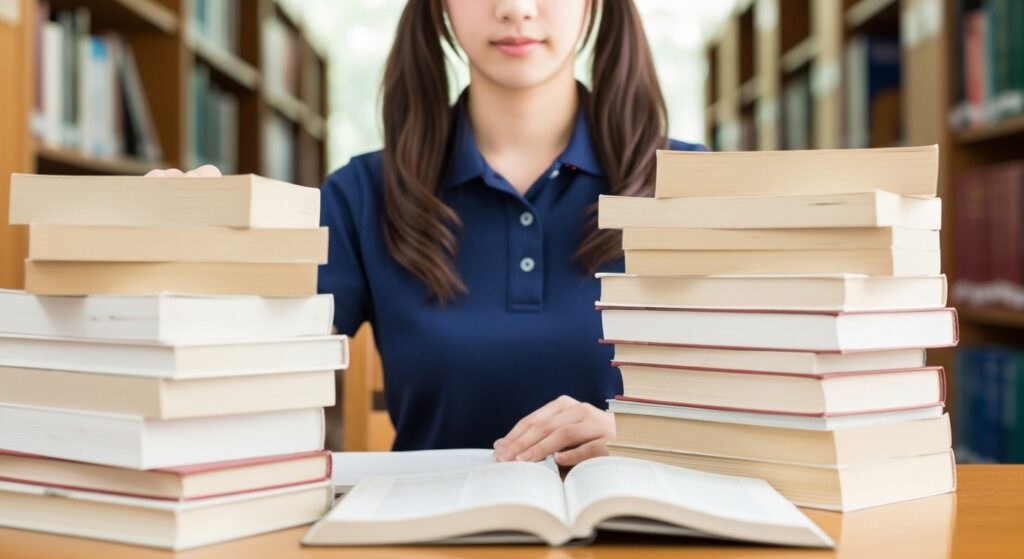
血管性認知症はなぜ起こるのか?
血管性認知症は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで神経細胞が損傷し、脳の働きが部分的に障害されることで発症します。国立長寿医療研究センターによれば、小さな脳梗塞が繰り返し起きる「ラクナ梗塞」や、白質のダメージが蓄積することで、記憶よりも注意・段取り・感情のコントロールに影響が出やすいと言われています。
※エビデンス
国立長寿医療研究センター
意外と身近な「血管性認知症」
血管性認知症は脳梗塞や脳出血など脳血管障害により発症し、小血管病変や白質病変が関与。初期症状では意欲低下や感情の変化、注意力の障害が目立つことがあると解説。アルツハイマー型と異なり症状が一様でなく、部位ごとに違いが生じる点も強調されている。
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/059.html
遂行機能・注意の低下に適合
日本神経学会では、血管性認知症では遂行機能障害や注意障害が顕著と示されています。そのため、複雑な説明や同時に複数の指示を出すと混乱を招きやすいです。短文・一指示でシンプルに伝えることで、理解と実行が安定します。
※エビデンス
三重大学大学院医学系研究科神経病態内科
皮質下血管性認知症の診断と治療
皮質下血管性認知症では遂行機能障害・注意障害が特徴的。歩行障害・感情失禁も併発しやすく、症状は階段状に悪化する。非薬物的対応が重要であり、段階的でシンプルな働きかけが効果的とされている。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/50/8/50_8_539/_pdf
階段状進行・局在徴候の影響
Mindsの診療ガイドラインでは、血管性認知症はアルツハイマー型と異なり「階段状の進行」や「脳血管障害に伴う局在徴候」が重視されると記されています。そのため「昨日はできたのに今日はできない」といった揺れを前提に、小刻みな段取り設計が必要です。
※エビデンス
日本神経学会/Minds
認知症疾患診療ガイドライン2017
血管性認知症は、脳血管障害に関連する症状や階段状・動揺性の経過が特徴。ADとの違いを踏まえ、症状や行動の変化に合わせた柔軟な対応が重要と解説されている。
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00408/
感情失禁への一次対応
血管性認知症では、感情のコントロールが難しく、些細な刺激で涙や怒りが出やすいと報告されています。そこで「共感→安心→方向づけ」の流れで声掛けを行うことが推奨されます。
※エビデンス
三重大学大学院医学系研究科神経病態内科
皮質下血管性認知症の診断と治療
皮質下型では感情失禁や易怒性が生じやすいと記され、環境調整と共感的対応が有効とされている。BPSD対応の一環として非薬物的手段が重要。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/50/8/50_8_539/_pdf
身体症状と安全配慮
片麻痺や小刻み歩行、嚥下障害が同時に現れることが多く、安全確保を前提とした声掛けが必要です。大阪府の指針にもあるように「ゆっくり・目線合わせ・具体的な行動合言葉」で不安を和らげます。
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
身体症状や歩行不安定さを念頭に置き、声掛けはゆっくり・目線を合わせ・短く一つずつ行うことが強調されている。安全と安心を同時に確保する具体的な指針を提示。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
意思決定支援の効果
厚生労働省のガイドラインでは「本人の価値観を軸にした意思決定」が強調されています。選択肢を二択にして、本人が「自分で選べた」と感じることが、受け入れ率や安心感を高めます。
※エビデンス
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の意思や価値観を尊重し、二択や選択肢提示による合意形成を推奨。自尊心を守りながら行動選択を可能にすることで、ケアの質と納得感を向上させる。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
締めとして、血管性認知症は「なぜ起こるのか」を理解し、その構造に合わせた声掛けを実践することが重要です。根拠を踏まえた小さな工夫が、本人の安心と職員のケア効率を同時に高めます。
よくある質問

- Q認知症・血管性認知症の声掛けで“二択(選択肢提示)”はなぜ有効?
- A
短文・一指示・二択・視覚化が基本です。大阪府の資料では「背後から声をかけない・目線を合わせる・ゆっくり話す」と言われています。厚生労働省のガイドラインでは「本人の価値観を基点に合意形成」と示されています。
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
「驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない」を原則に、目線合わせ、ゆっくり明瞭な話し方、一人での声掛けなど具体行動を提示。初期接近から誘導までの留意点を整理し、拒否・混乱の予防に有用。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
- Qアルツハイマー型と血管性認知症で声掛けはどう変える?
- A
日本神経学会/Mindsのガイドラインでは、血管性認知症は階段状進行・局在徴候が重要と言われています。ADは物忘れが中心のため「反復と安心」が軸に、VaDは段取り支援と安全配慮を強め、一度に一つの指示で進めます。
※エビデンス
日本神経学会/Minds
認知症疾患診療ガイドライン2017
病型別の臨床像と鑑別、評価、対応を体系化。VaDは脳血管障害の存在と階段状・動揺性の経過、局所神経徴候を重視。ADの緩徐進行・記憶障害優位と対照的で、病型差を踏まえた非薬物的支援の設計が必要とされる。
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00408/
- Q血管性認知症の感情失禁(怒り・涙)にはどう声を掛ける?
- A
臨床神経学の総説では、皮質下VaDで感情失禁がみられると言っています。共感→安心→方向づけの順で、短い言葉で落ち着け、話速はゆっくりに。環境刺激(音・人の出入り)も同時に下げましょう。
※エビデンス
三重大学大学院医学系研究科神経病態内科
皮質下血管性認知症の診断と治療
白質病変・ラクナを背景とする皮質下VaDでは遂行機能障害、歩行障害、感情失禁が目立つ。経過は緩徐または階段状。危険因子管理とともに、非薬物的アプローチや環境調整の重要性が述べられ、共感的対応の有効性が示唆される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/50/8/50_8_539/_pdf
- Q歩行不安や嚥下が心配な方への安全な声掛けは?
- A
大阪府の資料では前方から目線を合わせ、ゆっくり明瞭にと示されています。「今は立ちます→一歩前へ」など二段階の合言葉に。食事は一口→飲む→一息と順番を言語化し、誤嚥リスクを下げます。
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
接近・立ち位置・話し方の原則を明示し、安全と安心を同時に確保するコミュニケーションを推奨。歩行誘導や見守りの際の留意点が実務レベルで示され、転倒・誤嚥などインシデント予防に資する。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
- Q部位によって症状が違うと聞くが、声掛けはどう調整する?
- A
国立長寿医療研究センターは、小血管病変や白質病変など病巣により症状が異なると説明しています。前頭葉優位なら段取りの分割、基底核なら歩調・合言葉、側頭葉ならゆっくり+語彙を簡潔にと、特徴に合わせて最適化します。
※エビデンス
国立長寿医療研究センター
意外と身近な「血管性認知症」
VaDは脳梗塞・脳出血など脳血管障害で発症。ラクナ・白質病変など小血管病の関与が大きく、初期は意欲や注意、感情の変化が目立つことも。部位により症状が異なる点を解説し、早期相談と生活習慣病管理の重要性も指摘。
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/059.html
まとめ:明日から“予告→一指示→称賛”で現場を安定させる
忙しい現場でも、血管性認知症には「短文・一指示・二択・視覚化」を合わせるだけで受け入れ率が変わります。病型差と本人の価値観を踏まえ、同じ型をチーム全員で共有しましょう。
要点の再確認
「驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない」を合言葉に、前方から目線を合わせ、ゆっくり・はっきり伝えます。
- 短文で一つだけ伝える
- 二択で選びやすくする
- 視覚手がかり(カード・掲示)を添える
- できた直後に具体的称賛で次行動へ
※エビデンス
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
接近方法・話し方・環境配慮を具体的に提示。「背後から声掛けをしない」「ゆっくり明瞭に」「原則1人で声掛け」など、拒否・混乱の予防につながる実務指針を整理。
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
病型差を前提とした設計
血管性認知症は階段状の変化や局在徴候が重要と言われています。アルツハイマー型と同じ進め方では通りにくい場面があるため、段取りを小刻みに調整します
※エビデンス
日本神経学会/Minds
認知症疾患診療ガイドライン2017
VaDは脳血管障害の存在、動揺性・階段状の経過、局所神経徴候を重視。病型差を踏まえた非薬物的支援の設計を推奨。
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00408/
意思決定支援で“その人らしさ”を守る
「本人の価値観を軸に合意形成する」とガイドラインでは言われています。二択で選びやすくし、合意→実行→振り返りを回して納得感を高めます
※エビデンス
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
価値観・生活歴に基づく意思形成を支援し、情報収集→合意形成→実行→振り返りのプロセスと配慮点を具体化。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
出典:
大阪府
認知症の人への対応の心得(リーフレット)
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5468/p10.pdf
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
日本神経学会/Minds
認知症疾患診療ガイドライン2017
https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00408/
国立長寿医療研究センター
意外と身近な「血管性認知症」
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/059.html
三重大学大学院医学系研究科神経病態内科
皮質下血管性認知症の診断と治療
https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/50/8/50_8_539/_pdf
更新履歴
- 2025年9月15日:新規公開
- 2025年10月21日:一部レイアウト修正



