夜勤の定時巡視で「見落としが怖い」「利用者の睡眠を妨げていないか不安だ」と感じることはありませんか?
安全確認はしたい、でも安眠は守りたい…。このジレンマは、多くの介護職員さんが抱える共通の悩みです。
そんな中、この大きな課題を解決する鍵として「眠りセンサー」が注目されています。
この記事では、厚生労働省の報告書や学術論文といった信頼できる情報源だけを基に、眠りセンサーがもたらす「本当の効果」を分かりやすく解説します。
国や研究機関の調査では、以下のような現場の負担を軽くする具体的なデータが数多く報告されています。
中には、「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」に切り替え、業務を大きく変えた施設の事例もあります。
この記事を読めば、こうした根拠あるデータに基づき、あなたの現場の悩みをどう解決できるかのヒントが見つかります。
眠りセンサーで“定時巡回”から“通知ベース訪室”へ

夜勤の定時巡視で見落としが怖い、安眠を妨げていないか不安——多くの現場が抱える課題に、エビデンスに基づく具体策を示します。
結論の要旨
結論から言えば、眠りセンサーの活用により「通知ベースの訪室」へ移行することが有効です。
実際に、厚生労働省の報告書では「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」「利用者の睡眠を妨げることが減少した」という効果が示されています。これにより、職員にとっては「常時把握できる安心感」や「心理的な負担が軽減された」というメリットが、日本看護科学学会誌の研究でも「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」という客観的データと共に報告されています。
p<0.01とは?
「p < 0.01」は、その基準である0.05よりもさらに厳しい基準です。
これは「この結果が偶然で起こる確率は1%未満です」ということを意味します。
例えば、眠りセンサー導入前後の訪室回数を比較して「p < 0.01」という結果が出た場合、 「訪室回数が減ったという結果が偶然によるものである可能性は1%未満と非常に低いため、眠りセンサーの導入が統計的に意味のある影響を与えたと解釈できます」 と結論づけることができます。
論文などで見かける「有意な減少を認めた(p < 0.01)」という記述は、この統計的なお墨付きがあることを示しているのです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」
- 「利用者の睡眠を妨げることが減少した」
- 「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja
- 「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」
- 「利用者の睡眠を妨げずに済む」「精神的に安心できる」
具体的な解決策
まず取り組むべきは、夜間の定時巡回の見直しです。
この点について、厚生労働省の生産性向上に関する報告書は「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」への見直しを具体的な方法として挙げています。
この通知ベース運用が定着したら、収集した睡眠データを「カンファレンスでの活用」や「家族への状況説明」へと連携を広げ、ケアの質をさらに高めていくことが可能です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」
- 「カンファレンスでの活用」「家族への状況説明」
- 「職員の精神的負担の軽減と利用者の睡眠の質の向上」
運用開始時のポイント
運用を成功させる鍵は、初期設定の最適化と職員への研修です。
特にセンサーの誤作動は避けたいポイントですが、これも厚生労働省の報告書にヒントがあります。報告書には「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…利用者の状況に合わせてセンサーの感度を調整することで解消した」という、実践的な知見が記載されています。
エビデンスに基づき、個々の利用者に合わせた設定の最適化を行うことが、スムーズな運用定着に繋がります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…」
- 「利用者の状況に合わせてセンサーの感度を調整することで解消した」
- 研修・運用見直しの重要性
夜勤の負担や安眠への影響は、通知ベース運用と設定最適化で具体的に軽減できます。次セクションでは、現場で起こりやすい創作ケースを基に、実装の流れを示します。
現場でよくあるケース:通知ベース運用で何が変わるか

定時巡視を続けても不安が残る——そんな状況で、通知ベース運用に切り替えた時の典型的な変化を、エビデンスに沿って整理します。
ケースA—定時巡視の見直しで訪室回数が減る
通知に基づいて対応する体制へ移行すると、「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」の事例が報告されています。結果として「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」、「利用者の睡眠を妨げることが減少した」という変化が示され、「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」も示されています。さらに、「常時把握できる安心感」や「心理的な負担が軽減された」という所見も併記されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」
- 「利用者の睡眠を妨げることが減少した」
- 「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja
- 「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」
ケースB—データの可視化で合意形成とケア見直しが進む
睡眠・体動データを「睡眠表」として活用し、本人や家族への説明、医療との情報共有を行うことで、合意形成が進みます。「カンファレンスでの活用」や「家族への状況説明」に役立つ所見があり、ケースによっては睡眠状況の把握から介入を検討し、結果として服薬状況の見直しにつながった記載が示されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「睡眠センサーから得られる…データを『睡眠表』として…本人や家族に状況を説明」
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「カンファレンスでの活用」
- 「家族への状況説明」
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「睡眠薬を飲んでいた3名の利用者が、睡眠薬を飲まれなくても眠れるようになった」
ケースC—連携と設定最適化で対応が速くなる
通知がインカムや記録に連携されると、「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」という流れで対応でき、移動や確認の重複が抑えられます。導入初期に「センサーの誤作動によるアラートが頻発」しても、「利用者の状況に合わせてセンサーの感度を調整することで解消」した記載があり、設定の最適化が安定運用の前提になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」
- 「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…」
- 「…感度を調整することで解消した」
定時巡視に代わる通知ベース運用は、訪室回数や睡眠への影響、連携の質まで段階的に変化をもたらします。次のセクションでは、その背景にある根拠と理由を整理します。
根拠と理由:通知ベース運用を支えるエビデンス
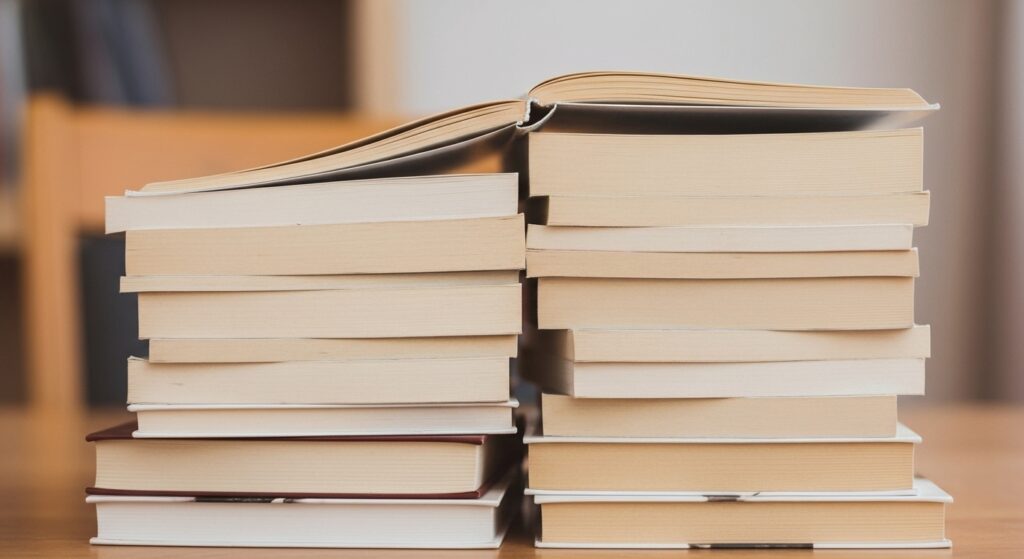
夜勤の負担軽減や安眠の維持は、個別の体験談ではなく公的報告と学術研究で裏づけがあります。本セクションでは、その要点を整理します。
公的報告が示す効果(ICT導入の実態と所見)
厚生労働省の報告書では、「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」、「利用者の睡眠を妨げることが減少した」と記載しています。また、「常時把握できる安心感」や「心理的な負担が軽減された」という所見も示されています。これらの所見は、通知に基づく訪室への移行が現場の負担軽減と安眠の維持に資することを示します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」
- 「利用者の睡眠を妨げることが減少した」
- 「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」
運用設計の見直し(定時巡回から通知ベースへ)
厚生労働省の生産性向上に関する報告書では、「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」への移行事例が記載されています。この見直しは、業務の流れ(誰が通知に対応し、どのように記録・共有するか)を再設計することで、負担軽減と睡眠の質の向上に結びつくことを示しています。カンファレンスや家族説明など、データの共有先をあらかじめ定めることも重要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」
- 「職員の精神的負担の軽減と利用者の睡眠の質の向上」
学術研究が示す量的効果と留意点
日本看護科学学会の研究では、「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」が示されています。加えて、「利用者の睡眠を妨げずに済む」「精神的に安心できる」という所見が挙げられています。一方で、導入初期には学習負荷や運用上の緊張が生じやすいため、初期研修と設定の見直しを組み合わせる運用が要点です。
出典元の要点(要約)
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja
- 「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」
- 「利用者の睡眠を妨げずに済む」「精神的に安心できる」
プライバシー配慮と選定の視点
厚生労働省の報告書には、「プライバシー保護等の観点から、映像を伴わないものの導入割合が最も高く」という記載があります。設置形態では「マットレス下設置タイプ」が多い状況が示されており、プライバシーと設置環境の双方を踏まえた選定が現実的です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「プライバシー保護等の観点から、映像を伴わないものの導入割合が最も高くなっている。」
- 「マットレス下設置タイプ」
連携と共有が効果を広げる
運用では、通知が「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」という流れで共有されると、確認の重複が減ります。カンファレンスや家族説明にデータを用いて共有の質を高めると、以後のアセスメントと計画見直しが円滑になります。これらは、通知ベース運用の効果を組織全体で持続させる要点です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」
通知ベース運用は、公的報告と学術研究により効果と留意点が確認されています。次のセクションでは、実装手順を具体化するための質問と回答を整理します。
よくある質問:通知ベース運用と眠りセンサーの実装
夜勤の負担や安眠への影響、運用面の不明点を、公的報告と学術研究の記載を基に整理します。現場で迷いやすい論点に、根拠を添えて回答します。
- Q通知が多すぎて業務が増えませんか?
- A
厚生労働省の報告書では、「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…」と記載があり、運用初期の負担増に触れています。一方で、「利用者の状況に合わせてセンサーの感度を調整することで解消した」と示され、設定最適化で安定運用に移行できることが分かります。運用面では研修と見直しを前提に整備するのが実際的です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf- 「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…」
- 「…感度を調整することで解消した」
- 研修・運用見直しの重要性
- Q本当に訪室回数は減りますか?
- A
日本看護科学学会の研究では、「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」と報告しています。厚生労働省の報告書にも「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」と記載され、通知ベース運用の効果が量的に確認できます。
出典元の要点(要約)
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja- 「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf- 「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」
- Q安眠は守れますか?
- A
厚生労働省の報告書では、「利用者の睡眠を妨げることが減少した」と記載されています。日本看護科学学会の研究にも、「利用者の睡眠を妨げずに済む」という所見があり、不要訪室の抑制が安眠維持に寄与することが確認できます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf- 「利用者の睡眠を妨げることが減少した」
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja- 「利用者の睡眠を妨げずに済む」
- Q職員の心理的負担は軽くなりますか?
- A
厚生労働省の報告書では、「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」と示され、見落とし不安の低減が読み取れます。通知ベースで必要時に絞って介入できる点が、夜勤の緊張を下げる一因です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf- 「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」
- Qどのように運用を切り替えればよいですか?
- A
厚生労働省の報告書には、「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」の事例が示されています。さらに、「カンファレンスでの活用」「家族への状況説明」とあわせ、共有の場面まで設計します。初期は感度・検知範囲の設定を繰り返し見直し、データの活用を通じて計画に反映します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf- 「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf- 「カンファレンスでの活用」
- 「家族への状況説明」
以上のQ&Aは、訪室回数の削減、安眠の維持、心理的負担の軽減、運用設計について、公的報告と学術研究の記載を根拠として整理しました。次のセクションでは、まとめと実装の第一歩を示します。
まとめ:明日から“通知ベース”へ――運用を整える
夜勤の不安や安眠への影響について、根拠に基づく要点を短く整理します。現場で無理なく始め、継続的に見直す前提で進めましょう。
要点の整理
厚生労働省の報告書には、「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」、「利用者の睡眠を妨げることが減少した」、「常時把握できる安心感」、「心理的な負担が軽減された」と記載があります。日本看護科学学会の研究でも「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」が示され、通知ベース運用の効果を裏づけます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「夜勤職員の巡回・訪室回数が減少した」
- 「利用者の睡眠を妨げることが減少した」
- 「常時把握できる安心感」「心理的な負担が軽減された」
日本看護科学学会
高齢者ケアにおけるセンサーとIoT機器の使用に関する文献検討(2023)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43028/_pdf/-char/ja
- 「訪室回数の有意な減少(p<0.01)」
- 「利用者の睡眠を妨げずに済む」「精神的に安心できる」
最初の一歩(実装の切り替え)
厚生労働省の報告書には、「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」の事例が示されています。まずは夜勤運用を通知ベースに切り替え、「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」の流れを整備します。導入初期に「センサーの誤作動によるアラートが頻発」しても、「…感度を調整することで解消した」という記載があり、設定の最適化を前提に進めます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「定時巡回を廃止し、センサーのアラートが鳴った際に訪室する体制」
- 「インカムに通知が飛ぶ→記録を確認→訪室」
- 「導入当初は、センサーの誤作動によるアラートが頻発し…」
- 「…感度を調整することで解消した」
チームで続ける(共有と見直し)
データは「カンファレンスでの活用」や「家族への状況説明」に用い、必要に応じて「睡眠表」で可視化します。共有の質を上げ、計画の見直しを定例化することで、通知ベース運用の効果を組織全体で維持できます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護現場で活用されるテクノロジー便覧
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/r05_105_02jigyohokokusho.pdf
- 「カンファレンスでの活用」
- 「家族への状況説明」
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「睡眠センサーから得られる…データを『睡眠表』として…本人や家族に状況を説明」
本セクションの内容を土台に、通知ベース運用と設定最適化を段階的に進めてください。小さな見直しを積み重ねることで、現場の負担軽減と安眠の維持に着実に近づけます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
本記事が、厚生労働省の報告書と学術研究に基づく「通知ベース運用」と「設定最適化」を進める際の一助になれば幸いです。現場の皆さまの安全と安眠の両立に、引き続きお役立てください。
※【ご注意】本記事で紹介している効果や事例は、出典元の報告書に記載されたものであり、全ての施設環境で同様の結果を保証するものではありません。
更新履歴
- 2025年10月7日:新規投稿
- 2025年10月8日:一部レイアウト修正



