新人介護士として、日々の業務お疲れ様です。ご利用者の命に直結する「服薬介助」。緊張や不安を感じる場面も多いのではないでしょうか。
この記事は、そんなあなたの「怖い」「不安」を、少しでも「自信」に変えるためのハンドブックです。特別な技術ではなく、明日から誰でも実践できる「誤薬を防ぐための基本的な考え方と行動」を、信頼できる情報だけを基に解説します。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます
この記事を知っていると
- なぜ誤薬が起きるのか、その根本的な原因がわかります。
- 服薬介助で「最低限ここだけは押さえるべき」という、重要なポイントが明確になります。
- どんな状況が特に危険なのかを事前に知ることで、リスクを避けられるようになります。
- あなた自身と、大切なご利用者を守るための具体的な行動が身につきます。
結論:誤薬を防ぐために、最も大切な「3つ」の基本動作

誤薬防止は、たくさんのルールを覚えることではありません。実は、大切なのはたった3つの基本動作だけです。これさえ押さえれば、新人さんでも自信をもって服薬介助ができます。具体的な方法を一つずつ見ていきましょう。
【基本1】「ご利用者本人」の確認を徹底する
服薬介助で最も基本となるのが「ご利用者本人の確認」です。同姓の方がいたり、お部屋を移動されたりするケースは少なくありません。そのため、お部屋の番号や「〇〇さん」という苗字だけの確認では不十分です。
医療事故調査・支援センターの提言では、実際に起きた事故の分析から患者の誤認が事故につながる事例が報告されており、対策としてリストバンドによる本人確認の徹底を挙げています。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 事故防止策として、リストバンドによる本人確認の徹底が挙げられる。
- 複数の業務を同時に行う「ながら作業」はエラーを誘発するため、与薬に集中できる環境を確保することが重要である。
- 事故を個人の責任として追及するのではなく、システム全体の問題として捉え、インシデントレポートを活用した再発防止策を講じる文化の醸成が求められる。
【基本2】「与えるお薬そのもの」を指差し・声出しで確認する
次に大切なのが、「正しいお薬かどうかの確認」です。介護老人保健施設での誤薬を調査した日本看護管理学会の研究では、誤薬の内容として「薬剤名」の確認不足が大きな割合を占めることが示唆されています。
特に見た目や名前が似ているお薬は注意が必要です。日本医療安全調査機構の分析によると、薬剤の取り違え、特に規格(含有量)違いの薬剤を誤って投与する事例が目立っています。思い込みを防ぐためにも、お薬を手に取った時と、ご利用者にお渡しする直前の確認があなたを守ります。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 与薬関連の医療事故は、「与薬時」が58.4%で最も多く、次いで「準備時」が24.7%であった。
- 事故の要因は「確認を怠った」が71.9%と大半を占め、「思い込み・勘違い」や「連携不足」が続く。
- 特に患者の誤認や薬剤の規格(含有量)違い、口頭指示による間違いが多く報告されている。
【基本3】「与える瞬間」に集中できる環境をつくる
どれだけ気をつけていても、作業が中断されるとミスは起こりやすくなります。服薬介助は、ご利用者の体に入るものを扱う、集中力が求められる医療行為の一部です。
日本医療安全調査機構の提言では、複数の業務を同時に行う「ながら作業」は注意力が散漫になりエラーを誘発するため、与薬中は他の作業を中断し、与薬に集中できる環境を確保することが重要だと示しています。「お薬をお渡ししているので、後ほど伺います」と周囲の理解を得ることも、安全を守るための大切なスキルです。
出典元の要点(要約)
日本老年薬学会 「高齢者施設における服薬管理のてびき」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janap/29/1/29_9/_pdf/-char/ja
- 高齢者施設の服薬管理は、入所者本人の意思を尊重し、QOL(生活の質)の維持・向上を目的として行われるべきである。
- 職員は医師や薬剤師と連携し(多職種連携)、薬物療法の適正化を図る役割を担う。
- 服薬介助時には誤嚥のリスクを常に考慮し、嚥下機能の確認や口腔ケアが重要となる。また、ポリファーマシー(多剤併用)は有害事象のリスクを高めるため、定期的な処方見直しが不可欠である。
「本人確認」「薬剤確認」「集中できる環境」。この3つは、安全な服薬介助の土台です。最初は緊張するかもしれませんが、一つ一つの動作を意識することで、あなたとご利用者を守る確かな力になります。
こんな時が危ない!誤薬が発生しやすい典型的な状況

誤薬は、特別な状況ではなく、日常業務の中に潜む「うっかり」や「思い込み」から発生します。医療事故調査・支援センターなどの分析によると、事故が起きやすい状況にはいくつかの共通したパターンがあります。これらを事前に知っておくことで、危険を予測し、安全なケアにつなげることができます。
思い込みと勘違い:「いつも通り」が落とし穴に
最も注意したいのが、慣れからくる「思い込み」です。公益財団法人 日本医療機能評価機構が分析した与薬事故の報告では、その原因として「確認を怠った」が約72%、「思い込み・勘違い」が約28%と、突出して高い割合を占めています。
「いつもこの薬だから」「さっき確認したから大丈夫」といった無意識の思い込みが、確認作業を省略させてしまう一番の落とし穴です。どんなに慣れた作業でも、服薬介助は毎回が「初めて」のつもりで、基本に忠実な確認をすることが大切です。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 与薬関連の医療事故は、「与薬時」が58.4%で最も多く、次いで「準備時」が24.7%であった。
- 事故の要因は「確認を怠った」が71.9%と大半を占め、「思い込み・勘違い」や「連携不足」が続く。
- 特に患者の誤認や薬剤の規格(含有量)違い、口頭指示による間違いが多く報告されている。
連携不足と伝言ゲーム:口頭指示の危険性
スタッフ間の連携不足も、誤薬の大きな原因の一つです。特に危険なのが、急いでいる時などに口頭でされた指示です。
日本医療安全調査機構の分析によると、薬剤名の聞き間違いや、投与量の聞き間違いといった口頭指示に起因する事故が報告されています。「〇〇さん、あの薬お願い」といった曖昧な指示は、受け取り方次第で全く違う意味になってしまう可能性があります。薬に関する指示は、必ず文書で確認することを基本とし、緊急時などで口頭指示を受けざるを得ない場合は、必ず復唱して内容を確認する習慣をつけましょう。
出典元の要点(要約)
日本老年薬学会 「高齢者施設における服薬管理のてびき」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janap/29/1/29_9/_pdf/-char/ja
- 施設における医薬品の管理責任者は施設長であるが、実際の管理は看護職員や介護職員が担うことが多い。関係職種がそれぞれの役割と責任を明確にすることが重要である。
- 施設内での服薬事故やインシデントが発生した場合は、速やかに報告し、原因を分析して再発防止策を策定・共有する。これを職員教育の機会としても活用する。
- 家族に対して、薬物療法の目的や内容、注意すべき副作用などについて十分に説明し、理解と協力を得ることで、より安全な服薬管理が可能となる。
似た名前・似た薬:見た目で判断するリスク
薬の中には、名前やパッケージ、錠剤の色や形がよく似ているものが数多く存在します。これらを慣れや見た目の印象だけで判断してしまうと、取り違え事故につながります。
日本医療安全調査機構の提言でも、薬剤の取り違え、特に名称の類似や外観の類似による事故、そして同じ薬でも量の違う規格(含有量)違いの事故が目立つと指摘されています。下の表のような間違いが起こりうることを、常に意識しておきましょう。
| 起こりやすい間違いの種類 | 具体的な注意点 |
| 名称の類似 | 発音が似ている薬剤名 (例:「アレビアチン」と「アテレック」) |
| 外観の類似 | PTPシート(薬の包装)や錠剤の色・形が似ている薬剤 |
| 規格(含有量)の違い | 同じ薬剤名でも「10mg」と「20mg」など、量が違うもの |
出典元の要点(要約)
医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構) 「医療事故の再発防止に向けた提言 第 15 号 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析結果からは、システムの不備や多重の確認が機能しなかったことなど、組織全体のリスク管理の課題が示唆されている。
- 名称が類似した薬剤の取り違えや、投与量の誤りなど、基本的な確認手順の不徹底が重大な結果につながる。
- 事故防止には、個人の注意深さだけに頼るのではなく、バーコード認証などの物理的な安全対策や、危険な薬剤に関する情報の共有が不可欠である。
これらの典型的な状況は、どれも「基本の動作」を徹底することで防げるものばかりです。危険なパターンを知り、「もしかしたら」と予測する意識を持つことが、あなたとご利用者を守る大きな力になります。
なぜ?がわかると行動が変わる。誤薬が起こるメカニズム

「ルールだから守る」だけでなく、「なぜこのルールが必要なのか」を理解すると、日々の行動の質は大きく変わります。ここでは、誤薬が起きてしまう背景にある「人間の特性」と、それを補う「安全な仕組み(システム)」の考え方について、エビデンスを基に見ていきましょう。
「人間はエラーをおこす」という前提に立つことの重要性
まず最も大切な考え方は、「人は誰でも間違える可能性がある」という前提に立つことです。どんなに注意深いベテランの職員でも、思い込みや勘違いを完全になくすことはできません。
医療事故調査・支援センターの提言でも、事故を個人の責任として追及するのではなく、システム全体の問題として捉え、再発防止策を考えることの重要性が示されています。誤薬防止の目的は、ミスをしない完璧な人間を目指すことではなく、万が一ミスが起きてもご利用者に害が及ばないような仕組みを職場全体で作り、守っていくことです。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 事故防止策として、リストバンドによる本人確認の徹底が挙げられる。
- 複数の業務を同時に行う「ながら作業」はエラーを誘発するため、与薬に集中できる環境を確保することが重要である。
- 事故を個人の責任として追及するのではなく、システム全体の問題として捉え、インシデントレポートを活用した再発防止策を講じる文化の醸成が求められる。
エラーを誘発する「人の状態」と「作業環境」
「人は誰でも間違える」とは言っても、特にエラーが起きやすくなる条件があります。日本医療安全調査機構の分析によると、エラーの誘因となる個人の状態や、作業環境には以下のようなものがあります。
| 要因の種類 | 具体的な注意点 |
| 人の状態 | 疲労、健康状態の不良、経験不足、「これくらい大丈夫」といった慣れや過信 |
| 作業環境 | スタッフからの問いかけや電話による作業の中断、複数の業務を同時に行う「ながら作業」 |
自分自身が疲れている時や、周囲が慌ただしい時こそ、「今が一番危ないかもしれない」と意識することが、事故を未然に防ぐための第一歩です。集中できる環境を確保することは、安全な介助を行う上での基本となります。
出典元の要点(要約)
日本老年薬学会 「高齢者施設における服薬管理のてびき」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janap/29/1/29_9/_pdf/-char/ja
- 服薬介助にあたっては、誤嚥のリスクを常に念頭に置き、入所者の覚醒状態や嚥下機能、姿勢などを確認する。
- 錠剤の粉砕やカプセルの開封は、薬剤の安定性や吸収に影響を与える可能性があるため、自己判断で行わず、必ず薬剤師に確認する。
- 服薬を拒否する入所者に対しては、その理由を傾聴し、背景にある不安や不満、思い込みなどを理解しようと努めることが第一歩である。
事故を個人の責任にせず「仕組み(システム)」で防ぐ
個人の注意深さだけに頼るのには限界があります。そこで重要になるのが、エラーが発生しても事故に発展しないようにするための「仕組み(システム)」です。
日本医療安全調査機構の提言では、個人の注意深さだけに頼るのではなく、物理的な安全対策の重要性を示しています。例えば、以下のような取り組みが「仕組み」にあたります。
- 似た名前・似た形の薬は、保管場所を物理的に離す
- 特に注意が必要な薬には、目立つ色のシールを貼る
- バーコード認証などを活用して、機械的にチェックする
これらの仕組みは、注意力が低下している時でも、間違いを未然に防いでくれるセーフティーネットの役割を果たします。
出典元の要点(要約)
医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構) 「医療事故の再発防止に向けた提言 第 15 号 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析結果からは、システムの不備や多重の確認が機能しなかったことなど、組織全体のリスク管理の課題が示唆されている。
- 名称が類似した薬剤の取り違えや、投与量の誤りなど、基本的な確認手順の不徹底が重大な結果につながる。
- 事故防止には、個人の注意深さだけに頼るのではなく、バーコード認証などの物理的な安全対策や、危険な薬剤に関する情報の共有が不可欠である。
安全な服薬介助は、個人の頑張りだけで成り立つものではありません。「人は間違えるもの」と理解し、それを補うための「仕組み」を職場全体で実践していくことが、あなたとご利用者の両方を守ることにつながります。
これってどうすれば?現場のギモンに答えます
現場で働く中で、「こんな時、どうすればいいんだろう?」と迷う場面はたくさんあります。ここでは、新人さんが特に抱きやすい疑問について、エビデンスを基に回答します。自己判断せず、迷ったら必ず先輩や看護師に確認する、という基本も忘れないでくださいね。
- Q夜勤など、一人で対応する時はどうすればいいですか?
- A
ダブルチェックができない一人勤務の時こそ、これまで解説してきた「3つの基本動作」が真価を発揮します。安全な服薬介助は、人数ではなく「安全な仕組み」と「確実な手順」によって支えられています。
日本医療安全調査機構の提言でも、事故防止には個人の注意深さだけに頼るのではなく、バーコード認証のような物理的な安全対策や、危険な薬剤に関する情報の共有が重要であると示されています。一人勤務の際は、特に「思い込み」を排除するために、一つひとつの手順を指差し・声出しで丁寧に行い、集中できる環境を自分で作る意識が大切になります。
出典元の要点(要約)
医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構) 「医療事故の再発防止に向けた提言 第 15 号 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析結果からは、システムの不備や多重の確認が機能しなかったことなど、組織全体のリスク管理の課題が示唆されている。
- 名称が類似した薬剤の取り違えや、投与量の誤りなど、基本的な確認手順の不徹底が重大な結果につながる。
- 事故防止には、個人の注意深さだけに頼るのではなく、バーコード認証などの物理的な安全対策や、危険な薬剤に関する情報の共有が不可欠である。
- Qご利用者がお薬を飲むのを嫌がった時はどうすればいいですか?
- A
無理にお薬を飲ませようとするのは、誤嚥などの危険も伴うため避けるべきです。日本老年薬学会のてびきでは、服薬を拒否する入所者に対しては、その理由を傾聴し、背景にある不安や不満、思い込みなどを理解しようと努めることが第一歩であると示されています。
なぜ飲みたくないのか、ご本人の言葉に耳を傾けてみましょう。「味が苦手」「量が多い」「飲むのが辛い」など、理由が分かるかもしれません。まずはご本人の意思を尊重し、その状況をありのまま看護師やリーダーに報告・相談することが、介護士としての大切な役割です。
出典元の要点(要約)
日本老年薬学会 「高齢者施設における服薬管理のてびき」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janap/29/1/29_9/_pdf/-char/ja
- 錠剤の粉砕やカプセルの開封は薬剤特性に影響するため、自己判断で行わず、必ず薬剤師に確認する必要がある。
- 服薬拒否に対しては、その理由を傾聴し、背景にある不安や不満を理解しようと努めることが第一である。
- 事故やインシデントが発生した場合は、速やかに報告し、原因を分析して再発防止策を策定・共有する体制が重要である。
- Q錠剤を砕いたり、カプセルを開けてもいいですか?
- A
自己判断で錠剤を砕いたり、カプセルを開けたりすることは、絶対にしてはいけません。
日本老年薬学会のてびきでは、錠剤の粉砕やカプセルの開封は、薬剤の安定性や吸収に影響を与える可能性があるため、自己判断で行わず、必ず薬剤師に確認すること、と明確に定められています。薬によっては、効果がなくなったり、逆に作用が強く出すぎてしまったりと、ご利用者の体に悪影響を及ぼす危険があります。嚥下の問題でどうしても内服が難しい場合は、必ず看護師や薬剤師に相談し、医師の指示を仰いでください。
出典元の要点(要約)
厚生労働省 「高齢者施設の服薬簡素化提言」 https://www.mhlw.go.jp/content/11125000/001266084.pdf
- 高齢者施設ではポリファーマシー(多剤併用)の状態にある利用者が多く、薬物有害事象のリスクが高い。
- 服薬アドヒアランスの低下(正しく薬を服用できないこと)や誤嚥、介護者の負担増大などが課題となっている。
- 医師・薬剤師・看護師・介護士などの多職種が連携し、定期的に処方を見直し、不要な薬剤を減らしていくことが推奨される。
- Qもし「間違えたかも」と思ったら、どうすればいいですか?
- A
「間違えたかもしれない」と気づいた時点で、すぐにリーダーや看護師に報告してください。これが最も重要で、勇気ある正しい行動です。
自分のミスを報告するのは怖いことかもしれません。しかし、一番大切なのはご利用者の安全です。報告が早ければ早いほど、適切な対応が取れ、健康への影響を最小限に食い止められる可能性が高まります。日本老年薬学会のてびきでも、施設内での服薬事故やインシデントが発生した場合は、速やかに報告し、原因を分析して再発防止策を策定・共有することの重要性が示されています。あなたの勇気ある報告が、将来の事故を防ぐための貴重な情報になります。
出典元の要点(要約)
公益財- 団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 事故防止策として、リストバンドによる本人確認の徹底が挙げられる。
- 複数の業務を同時に行う「ながら作業」はエラーを誘発するため、与薬に集中できる環境を確保することが重要である。
- 事故を個人の責任として追及するのではなく、システム全体の問題として捉え、インシデントレポートを活用した再発防止策を講じる文化の醸成が求められる。
現場での疑問は、一つひとつが安全なケアを学ぶ大切な機会です。「これくらい大丈夫だろう」と自己判断せず、分からないことは必ず確認する姿勢が、あなたとご利用者を守る最も確実な方法です。
まとめ:明日からできる、安全な服薬介助の第一歩
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。服薬介助には多くの注意点がありますが、すべてを一度に覚える必要はありません。最後に、あなたとご利用者を守るために最も大切なポイントを振り返りましょう。
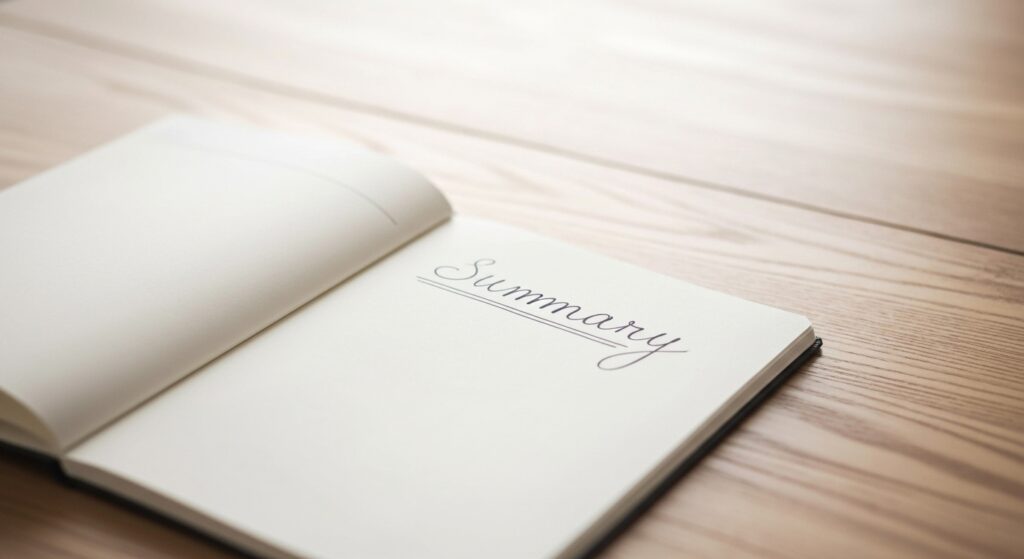
最重要ポイントの再確認:「本人確認」「薬剤確認」「集中できる環境」
この記事で繰り返しお伝えしてきた、誤薬を防ぐための最も重要な3つの基本動作です。この3点セットを常に意識することが、安全な介助の土台となります。
| 最重要ポイント | なぜ大切か?(エビデンスに基づく理由) |
| 1. ご利用者本人の確認 | 患者の誤認(思い込みによる人の間違い)を防ぐため |
| 2. お薬そのものの確認 | 薬剤の取り違え(名称・外観・規格(量)の間違い)を防ぐため |
| 3. 集中できる環境 | 作業の中断や「ながら作業」によるヒューマンエラーを防ぐため |
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 「医療安全情報No.15 2007年2月 与薬(注射・点滴・内服薬)に関連した医療事故」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 事故防止策として、リストバンドによる本人確認の徹底が挙げられる。
- 複数の業務を同時に行う「ながら作業」はエラーを誘発するため、与薬に集中できる環境を確保することが重要である。
- 事故を個人の責任として追及するのではなく、システム全体の問題として捉え、インシデントレポートを活用した再発防止策を講じる文化の醸成が求められる。
事故防止は「仕組み(システム)」が大切
安全な服薬介助は、個人の頑張りや注意深さだけで成り立つものではありません。「人は誰でも間違える」という前提に立ち、それを補うための「仕組み(システム)」を職場全体で実践していくことが何よりも重要です。
医療事故調査・支援センターの提言でも、個人の注意深さだけに頼るのではなく、物理的な安全対策や情報の共有が不可欠であると示されています。似た薬の保管場所を分ける、注意喚起のラベルを貼る、といった一つひとつの工夫が、あなたを助けるセーフティーネットになります。
出典元の要点(要約)
医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構) 「医療事故の再発防止に向けた提言 第 15 号 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」 https://www.medsafe.or.jp/teigen/teigen15.pdf
- 薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析結果からは、システムの不備や多重の確認が機能しなかったことなど、組織全体のリスク管理の課題が示唆されている。
- 名称が類似した薬剤の取り違えや、投与量の誤りなど、基本的な確認手順の不徹底が重大な結果につながる。
- 事故防止には、個人の注意深さだけに頼るのではなく、バーコード認証などの物理的な安全対策や、危険な薬剤に関する情報の共有が不可欠である。
新人だからこそ、基本に忠実な実践を
新人であることは、安全な服薬介助を身につける上で大きな強みです。なぜなら、自己流の癖がなく、基本に忠実な手順をゼロから確実に身につけることができるからです。
分からないこと、不安なことをそのままにせず、先輩や看護師、薬剤師に質問・相談することは、とても大切な姿勢です。日本老年薬学会の提言でも、安全なケアのためには多職種が連携することの重要性が示されています。ぜひ、基本を大切に、チームの一員として安全なケアを実践していってください。
出典元の要点(要約)
日本老年薬学会 「高齢者施設における服薬管理のてびき」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janap/29/1/29_9/_pdf/-char/ja
- 高齢者施設の服薬管理は、入所者本人の意思を尊重し、QOL(生活の質)の維持・向上を目的として行われるべきである。
- 職員は医師や薬剤師と連携し(多職種連携)、薬物療法の適正化を図る役割を担う。
- 服薬介助時には誤嚥のリスクを常に考慮し、嚥下機能の確認や口腔ケアが重要となる。また、ポリファーマシー(多剤併用)は有害事象のリスクを高めるため、定期的な処方見直しが不可欠である。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月12日:新規公開



