毎日の清拭、本当に意味があるのだと感じている方、いらっしゃいますよね?
人手も時間も限られるなかで、どこを・いつ・どう拭けばよいかが曖昧だと、負担だけが残りがちです。この記事は、介護施設で働く介護職員が現場で再現できるやり方に落とし込めるよう、一次情報に基づいて整理します。
結論はシンプルです。本記事では、“場面連動×高頻度接触面”を運用化し、噴霧ではなく湿式の拭き取りを基本に、手指衛生・マスク・換気・ワクチンを重ねることが、接触感染の鎖を断つ実装的な方法として提案します。
厚生労働省の手引きや東京都のガイドブック、国立の解説には、そのための具体的な根拠と手順が明記されています。
さらに本文では、食前後・トイレ後・送迎後に合わせた清拭と、ワゴン配置・巡回表による運用の定着化まで踏み込みます。読了後に、「やるべきことが明確」「やり方が統一」「運用が回る」状態を一緒につくりましょう。
出典
「患者の咳、くしゃみ、鼻水…環境中(机、ドアノブ、スイッチ)…手で自分の眼や口や鼻を触ることで…(接触感染)」
出典:『インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成25年11月改訂)』/厚生労働省・日本医師会/p.4
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf「消毒液の噴霧は絶対に行ってはいけません。…消毒液は、クロス等に染み込ませてから使いましょう。」
出典:『高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)』/東京都保健医療局/p.28
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf「各所、原則1日1回以上の湿式清掃…清掃の基本はふき取りによる埃の除去です。」
出典:『高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)』/厚生労働省 老健局/p.23
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf「一旦、感染症が介護現場に持ち込まれると、集団発生となり得るので、まずは予防すること…」
出典:『介護現場における感染対策の手引き(第3版・2023年)』/厚生労働省 老健局/p.6
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf「インフルエンザ…『重くなりやすい疾患』である。」
出典:『インフルエンザ(詳細版)』/国立健康危機管理研究機構(感染症情報サイト)
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/010/index.html
結論:まず現場で応用できる“場面連動×高頻度接触面”を運用化する

限られた人手と時間で成果を出すには、回数ではなく場面で統一し、高頻度接触面を湿式清拭で押さえることが近道です。手指衛生・マスク・換気・ワクチンを重ね、持ち込み予防と発生時の最小化を両立します。
最初の一手
今日から現場の特性に合わせて、利用者の接触機会が多い場面に連動させ(例:食前後・トイレ後・送迎後など)、手すり・テーブル・ドアノブを拭く運用を定時化することを提案します。噴霧は禁止とし、クロスに浸して拭き取りを徹底。接触感染の鎖(環境→手指→粘膜)を現場で断ちます。
出典
厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.16
「日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置くこと。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「各所、原則1日1回以上の湿式清掃を行った後、換気(空気の入れ換え)を行い乾燥させます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.9
「共同のロッカーやテーブル、パソコン等は時間を決めて清掃する」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf
実行のハードルを下げる工夫
フロアごとに清拭ワゴンの定位置配置、ワイプ枚数と手袋サイズの事前割当、巡回表で担当・時間帯の固定化を行い、場面で運用します。毎日時間を決めた清掃、湿式清掃+換気を基本に、噴霧禁止や体液付着時の拭き取りを掲示。マニュアルは手に取りやすい場所に置いて定着させます。
出典
厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.16
「日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置くこと。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「各所、原則1日1回以上の湿式清掃を行った後、換気(空気の入れ換え)を行い乾燥させます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.9
「共同のロッカーやテーブル、パソコン等は時間を決めて清掃する」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf
到達イメージ
環境表面→手指→粘膜の拡大の鎖が清拭で遮断され、二次感染が抑制されます。ワクチン・不織布マスク・こまめな換気・早期受診・個室対応を重ね、まずは予防し、発生時も最小限に食い止める運用が定着。記録と配置の標準化で、ムラが減り、欠員時も同品質を実現します。
出典
厚生労働省 老健局
介護現場における感染対策の手引き(第3版・2023年)、p.6
「一旦、感染症が介護現場に持ち込まれると、集団発生となり得るので、まずは予防すること、そして発生した場合には、最小限に食い止めることが必要です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf厚生労働省 老健局
介護現場における感染対策の手引き(第3版・2023年)、p.95
「予防策としては、利用者と職員にワクチンの接種を行うことが有効です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf国立健康危機管理研究機構
インフルエンザ(詳細版)(Web)
「インフルエンザ(influenza)は…『重くなりやすい疾患』である。」
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/010/index.html
この結論を土台に、次セクションでは物品配置・チェック項目・巡回表まで具体化し、人が変わっても回る運用へつなげます。
事例:現場で実践できる!応用アイデア3選

「消毒は本当に意味があるのか?」という疑問は、現場の実感から生まれます。ここでは食前後・送迎後・体液対応など、日々の典型的な場面でのケースを取り上げ、清拭の効果を具体的に確認していきます。
ケース1|食前後の清拭ルーティンで食堂の発熱抑制
昼食前後に食堂テーブルや手すりを湿式清拭する習慣は、接触機会の多い場面での標準化として有効な運用提案です。
出典
厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「清掃の基本はふき取りによる埃の除去です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
ケース2|送迎後の一筆書き巡回で“持ち込み”を遮断
送迎直後、玄関から廊下、スイッチ、車椅子グリップを「一筆書き」で清拭する運用を導入。外部からの持ち込みを遮断し、感染拡大の初動を抑えたケースが見られます。物品を定位置に配置し、職員間で動線を共有することで実現可能になります。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.9
「共同のロッカーやテーブル、パソコン等は時間を決めて清掃する」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf
ケース3|噴霧中心から拭き取りへ切り替え効果を実感
以前は消毒液の噴霧を中心に清掃していた施設が、湿式清拭に切り替えたところ、再発率が下がったケースがあります。噴霧は禁止とされており、一方向清拭+布の交換を徹底することで、ウイルス残存の抑制につながります。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.28
「消毒液の噴霧は絶対に行ってはいけません。…消毒液は、クロス等に染み込ませてから使いましょう。」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf
注:これらは公的な統計データに基づく「事例」ではなく、公的マニュアルの原則に基づき、現場での実践を想定した「応用アイデア」として記述しています。
これらのケースが示すのは、消毒は“やるかやらないか”ではなく、“どう実行するか”が結果を左右するという点です。次のセクションでは、なぜこの方法が有効なのか、その理由と仕組みを掘り下げます。
理由:なぜこの方法が有効なのか
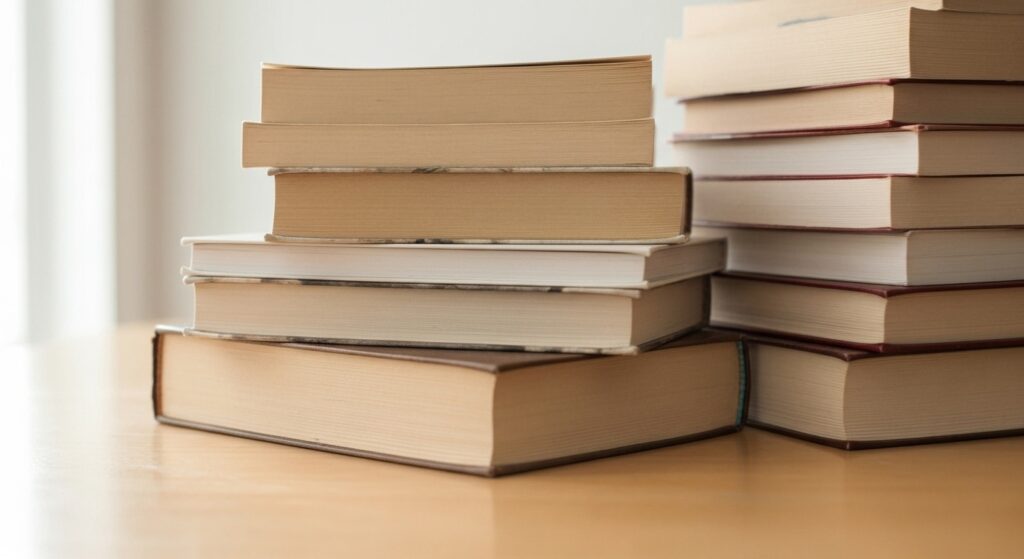
接触の鎖が成立する場面を押さえ、湿式清拭で物理的に断ち、複合対策で底上げする——この順が現場で再現しやすく、効果も説明できます。一次情報に沿って、背景・仕組み・限界を整理します。
背景と前提:接触の鎖が成立する現場特性
介護施設では複数の利用者を一人の職員が担当し、環境表面→手指→粘膜という接触感染の鎖が成立しやすい前提があります。インフルエンザは「重くなりやすい疾患」で、流行が周期的に現れるため、まずは予防し、発生時は最小限に食い止める構えが不可欠です。
出典
厚生労働省 老健局
介護現場における感染対策の手引き(第3版)、p.6
「介護現場においては、1人の職員が複数の利用者を担当することが常であり、職員を介して感染症が広がること(媒介)もあります。一旦、感染症が介護現場に持ち込まれると、集団発生となり得るので、まずは予防すること、そして発生した場合には、最小限に食い止めることが必要です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
厚生労働省・日本医師会
インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成25年11月改訂)、p.4
「患者の咳、くしゃみ、鼻水などに含まれたウイルスが付着した手で環境中(机、ドアノブ、スイッチなど)を触れた後に、その部位を別の人が触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによってウイルスの感染が起こる(接触感染)。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf国立健康危機管理研究機構
インフルエンザ(詳細版)(Web)
「インフルエンザ(influenza)は、インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症であるが、『一般のかぜ症候群』とは分けて考えるべき『重くなりやすい疾患』である。」
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/010/index.html
効果のメカニズム:湿式清拭で量を減らし、一方向で取り切る
湿式清掃を基本に、消毒液はクロスに染み込ませて一方向に拭きます。噴霧は禁止です。体液付着時はアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムで拭き取り、金属は10分後に水拭きして乾燥まで行うと、再汚染や健康被害のリスクを避けつつ表面のウイルス量を低減できます。これを場面連動で定時化すると、接触感染の鎖を切る実効性が上がります。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.28
「床、壁、ドア面等は湿式清掃が基本です。(消毒液の使用は必要ありません。)」「消毒液の噴霧は絶対に行ってはいけません。」「消毒液は、クロス等に染み込ませてから使いましょう。」「アルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取りましょう。」「次亜塩素酸ナトリウム液で消毒した金属等は腐食を防ぐために、10分後に水拭きして乾燥させます。」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「各所、原則1日1回以上の湿式清掃を行った後、換気(空気の入れ換え)を行い乾燥させます。…清掃の基本はふき取りによる埃の除去です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
リスクと限界:噴霧の禁止と“単独対策”の弱さ
噴霧は禁止で、クロスに浸した拭き取りが前提です。清掃の基本はふき取りで、見た目の汚れを除去しつつ湿式清掃+換気を合わせます。さらに、ワクチン・不織布マスク・こまめな換気・早期受診・個室対応などを重ねることで、持ち込み予防と発生時の最小化を現実的に達成します。拭き取り“だけ”では限界がある点を、複合対策で補います。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.28
「消毒液の噴霧は絶対に行ってはいけません。…消毒液は、クロス等に染み込ませてから使いましょう。」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.22–23
「日常的には、見た目に清潔な状態を保てるように清掃を行います。消毒薬による消毒よりも目に見える埃や汚れを除去し、居心地の良い、住みやすい環境づくりを優先します。」「各所、原則1日1回以上の湿式清掃を行った後、換気(空気の入れ換え)を行い乾燥させます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf厚生労働省 老健局
介護現場における感染対策の手引き(第3版)、p.95
「予防策としては、利用者と職員にワクチンの接種を行うことが有効です。…また、咳をしている人には、不織布マスクをしてもらう方法が効果的です。…さらに、日頃からこまめに換気を行うことも重要です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
以上を踏まえると、接触の鎖を湿式清拭で断ち、複合対策で底上げする設計が、現場で回るもっとも実用的な道筋になります。次はFAQで、運用時の具体的な疑問を整理します。
よくある質問(FAQ)

- Q介護施設で手すりやドアノブを拭くことは、本当にインフルエンザの予防に役立ちますか?
- A
役立ちます。接触感染は「患者の分泌物が付着した手が環境表面を汚染→他者が触れ→自分の眼や口や鼻を触る」流れで成立します。高頻度接触面の拭き取りを運用に組み込むことが、接触の鎖を断つ実践策になります。
出典
厚生労働省・日本医師会
インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成25年11月改訂)、p.4
「患者の咳、くしゃみ、鼻水などに含まれたウイルスが付着した手で環境中(机、ドアノブ、スイッチなど)を触れた後に、その部位を別の人が触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによってウイルスの感染が起こる(接触感染)。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf
- Q清掃・消毒の頻度はどのくらいを目安にすればよいですか?
- A
日常の目安として「各所、原則1日1回以上の湿式清掃」が示されています。汚染がひどい場合や新たな汚染が発生しやすい場合は回数を増やし、清掃の基本はふき取りで、換気も合わせて実施します。
出典
厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「各所、原則1日1回以上の湿式清掃を行った後、換気(空気の入れ換え)を行い乾燥させます。汚染がひどい場合や新たな汚染が発生しやすい場合には、清掃回数を増やし、汚染が放置されたままにならないようにします。清掃の基本はふき取りによる埃の除去です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
- Q噴霧ではなく、どのように拭き取ればよいですか?
- A
噴霧は絶対に行ってはいけません。消毒液はクロス等に染み込ませて使用し、一方向に拭き取ります。床・壁・ドア面は湿式清掃が基本で、体液付着時の処置や金属は10分後に水拭きして乾燥まで行う手順が示されています。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.28
「床、壁、ドア面等は湿式清掃が基本です。(消毒液の使用は必要ありません。)」「消毒液の噴霧は絶対に行ってはいけません。」「消毒液は、クロス等に染み込ませてから使いましょう。」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf
- Qアルコールだけで足りますか?次亜塩素酸ナトリウムとの使い分けはどうすればよいですか?
- A
体液付着時は「アルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取り」ます。用途例としてトイレのドアノブでは消毒用エタノールで清拭する記載があります。材質や場面に応じた拭き取りが基本です。
出典
東京都保健医療局
高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック(令和6年2月)、p.28
「血液や分泌物、尿等が付着した場合 アルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取りましょう。」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/kansenshoguidebook.files/20240201zentaiver.pdf厚生労働省 老健局
高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版(2019年)、p.23
「トイレのドアノブ、取手等は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行います。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
- Q消毒とあわせて、現場で何を重ねると効果が高まりますか?
- A
予防策としては、利用者と職員にワクチンの接種を行うことが有効で、不織布マスク、こまめな換気、早めに医師の診察、個室対応などを発生前〜発生時まで一連で実行します。拭き取り“だけ”ではなく、複合対策が要点です。
出典
厚生労働省 老健局
介護現場における感染対策の手引き(第3版)、p.95
「予防策としては、利用者と職員にワクチンの接種を行うことが有効です。…また、咳をしている人には、不織布マスクをしてもらう方法が効果的です。…さらに、日頃からこまめに換気を行うことも重要です。」「インフルエンザを疑う症状があった場合は、早めに医師の診察を受けます。」「インフルエンザを疑う場合(および診断された場合)には、基本的には個室対応とします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
まとめ:要点の再確認と次の一歩
現場で迷いがちな「どこを、いつ、どう拭くか」を場面連動×高頻度接触面で標準化し、湿式清拭と拭き取りを基本に据えることで、接触の鎖を現実的に断ち切れます。ワクチン・不織布マスク・換気・早期受診・個室対応を重ね、属人化しない仕組みに落とし込みましょう。
要点の3行サマリ
- 場面連動×高頻度接触面を定時化して、運用のムラを抑える。
- 湿式清拭と噴霧の禁止、クロスに染み込ませ一方向で拭き取りを徹底する。
- ワクチン・不織布マスク・換気・早期受診・個室対応を重ねる複合対策で実装度を高める。
今日からできるチェックリスト
- 現場で検討できる仕組み化のヒント ・ 食前後・トイレ後・送迎後に、手すり/ドアノブ/テーブルの拭き取りを定時化
- 各フロアに清拭ワゴンを固定配置(クロス・手袋・廃棄袋を定数補充)
- 巡回表で「誰が・いつ・どこを」を固定し、欠員時の代替手順を明文化
今日の内容、いかがでしたか。現場での工夫や課題、実際に運用してみた感触を教えてください。コメントやシェアが、ほかの介護職の力になります。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月2日:新規公開










