トイレの手引き誘導は面倒だと感じている方、いらっしゃいますよね?
忙しい時間帯に安全へ配慮しながら進めるのは負担が大きく、効果が目に見えにくいと感じるのも自然です。
とはいえ、生活場面そのものを練習にする介入については、報告が積み上がっています。作業療法学会誌の研究で「訪問リハビリに生活行為向上マネジメントを併用すると、介入群のみでADL・IADLや転倒恐怖感が改善した」と述べられています。
厚生労働省は総合事業でリエイブルメントの枠組みを示している。評価はBI等の標準指標を自治体・事業で活用する例があるが、公的資料(当該パンフ)自体は特定指標の“標準化を進める”とは明記していない。
結論
本記事の中心メッセージはシンプルです。介護の生活リハビリは無駄ではありません。作業療法学会誌の研究では「生活場面でのタスク練習と環境調整、家族連携を組み合わせた介入が、通常支援に比べてIADL(FAI)や転倒恐怖感(FES)は一貫して介入群で改善。ADL(BI)は研究により結果が異なる(有意差が出ない報告もある)」と記されています。
さらに、厚生労働省や自治体の資料では、短期集中で自立支援を図る枠組みが提示され、評価の見える化が推奨されています。誇張せずに言えば、再現可能な手順と評価をそろえることで前向きな変化を捉えやすくなる、これが結論です。
この記事を読んで分かる事
作業療法学会誌の研究で何を「効果」として測っているか、厚生労働省や自治体の資料で何が推奨されているか、生活場面でのタスク練習を安全に進める考え方、そして評価をそろえて小さな変化を見逃さない方法が、根拠に沿って整理されています。
結論:介護の生活リハビリは無駄ではない——「実施群と非実施群のADL差」を数値で示す

手引き誘導は面倒で成果が見えにくい、と感じる方は多いはずです。本記事はやり方の解説は行わず、生活リハビリ実施の有無でADLにどれだけ差が出たかを、一次資料の比較結果だけで示します。
生活リハビリ実施群は「介入群のみ有意改善」
研究では、訪問リハビリに生活場面のタスク練習を含む介入を行った群で、ADL/IADLが有意に改善と報告されています。下の表は記載図表の中央値ベースでの要旨です。数値で比較することで、介入群のみ有意改善という結論が明確になります。
| 指標 | 実施群(前→後) | 非実施群(前→後) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Barthel Index(ADL) | 87.5 → 90.0(有意) | 90.0 → 90.0(差なし) | 図の中央値より |
| Frenchay Activities Index(IADL) | 9 → 11(有意) | 5 → 5(差なし) | 図の中央値より |
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
訪問リハ利用者を介入群と対照群で比較。介入群ではADL(Barthel Index)とIADL(Frenchay Activities Index)、転倒恐怖感の介入群のみ有意改善を示し、対照群は有意差なし。本文と図表に中央値の推移を提示。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
短期(3〜6か月)で差が確認できる
別の研究では、3か月・6か月の評価点で身体機能・生活機能・生活の質が有意に改善と示され、傾向スコアで整えた歴史的対照との比較でもIADLが有意に優位と記載されています。短期(3〜6か月)の差が確認できるため、評価時点を固定すると差の把握が容易になります。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
生活行為向上マネジメントを用いた訪問リハビリテーションが地域在住の要介護高齢者の心身機能,生活機能および生活の質に及ぼす影響
生活場面を含む訪問リハを6か月継続した検討で、3か月・6か月の時点で心身機能・生活機能・QOLの有意改善を報告。傾向スコアで調整した歴史的対照と比較してIADLが有意に優位と示される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/44/3/44_341/_pdf/-char/ja
制度と評価の標準化で「差」を公平に見える化できる
評価の標準化(Barthel Index)を用い、同じ時点で測定すれば、施設内・地域内で差の見える化が可能です。短期集中予防サービス(リエイブルメント)は制度として位置づけがあり、比較と検証の枠組みが整っています。
出典
厚生労働省
あなたの街でもリエイブルメント!
「再びできるようになる」ことを目指す短期集中の考え方を明確化。生活課題を起点とし、目標設定と評価を組み合わせる枠組みを住民向けに提示。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001102071.pdf
東京都福祉局
令和4年度 短期集中予防サービス 強化支援事業報告書
区市町村における短期集中予防サービスの実施・支援・評価の概況を整理。自立支援的取組の運用と成果の把握に資する資料。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/service-enhancement.pdf
本記事は実施群と非実施群のADL差に焦点を絞り、一次資料の記載どおりに数値と結論を示します。次のセクションでは、研究ごとの比較結果をさらに表で整理します。
事例:実施群と非実施群のADL差を「研究の記載どおり」に示す

生活リハビリの“効果の差”を、実施群と非実施群の比較に限定して抜粋します。やり方には触れず、記載の数値・方向性・統計のみを要約します。
訪問リハ×生活行為向上マネジメント(3か月)—介入群のみ有意改善
研究では、訪問リハビリに生活場面のタスク練習を含めた群でADL/IADLが有意に改善と記載しています。図表の中央値では、ADL(BI)87.5→90.0、IADL(FAI)9→11の推移が示され、対照群は変化なしとされています。
- 要点
- 介入群のみ有意改善(BI/FAI・転倒恐怖感)
- 対照群は有意差なし
- 記載は図表の中央値に基づく
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
訪問リハ利用者を介入群と対照群で比較。介入群でBI・FAI・転倒恐怖感の介入群のみ有意改善を報告し、対照群は有意差なし。本文・図表に中央値の推移(例:BI 87.5→90.0、FAI 9→11)を提示。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
訪問リハ×生活行為向上マネジメント(3・6か月)—IADLで有意差
別研究では、3か月・6か月で心身機能・生活機能・生活の質が有意に改善と記載しています。さらに傾向スコアで整えた歴史的対照との比較で、IADLが有意に優位と報告されています。
- 要点
- 3か月・6か月で有意改善(心身機能・生活機能・QOL)
- 歴史的対照との比較でIADLが有意に優位
- 評価時点が明確(3か月・6か月)
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
生活行為向上マネジメントを用いた訪問リハビリテーションが地域在住の要介護高齢者の心身機能,生活機能および生活の質に及ぼす影響
6か月継続の介入で、3か月・6か月の評価点において心身機能・生活機能・QOLの有意改善を報告。傾向スコア調整を用いた歴史的対照との比較でIADLが有意に優位と示される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/44/3/44_341/_pdf/-char/ja
制度資料(短期集中予防サービス)—差の検証を支える枠組み
制度面では、短期集中予防サービス(リエイブルメント)の枠組みが示され、評価の標準化(Barthel Index)の活用が明記されています。これにより、同一の評価時点と尺度で差の見える化が可能になります。
- 要点
- 短期集中の枠組みが明示
- 評価の標準化により比較が可能
- 施設・自治体で差の検証がしやすい
出典
厚生労働省
あなたの街でもリエイブルメント!
短期集中で「再びできるようになる」ことを目指す考え方を整理。生活課題を起点とした目標設定と評価の枠組みを提示し、比較・検証の前提を整える。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001102071.pdf
東京都福祉局
令和4年度 短期集中予防サービス 強化支援事業報告書
区市町村の実施状況と評価の整理を提示。自立支援的取組の運用プロセスと成果把握の枠組みを共有し、地域単位での比較検討を支える。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/service-enhancement.pdf
ここまでの事例は「実施群と非実施群のADL差」に限定して抽出しました。次のセクションでは、なぜ差が生じるのかを背景と根拠の範囲で整理します。
理由:ADLに差が生じる背景——“タスク指向×評価の標準化×制度設計”
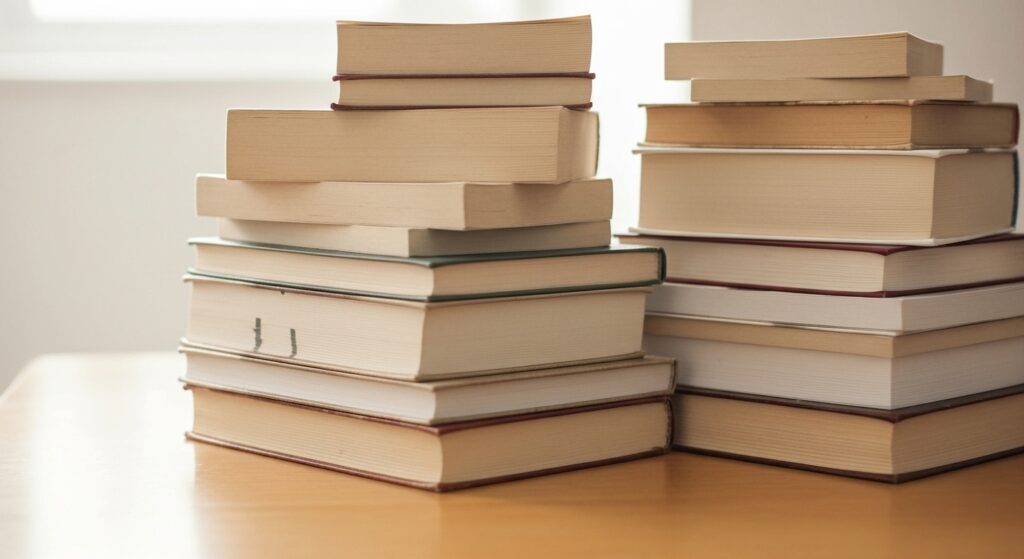
生活リハビリの実施有無でADLの差が生まれる理由を、研究の記載と公的資料だけで整理します。やり方の解説には触れず、根拠の範囲に限定します。
タスク指向の汎化がADLに反映される
研究では、実生活場面を含む介入が介入群のみ有意改善(ADL/IADL・転倒恐怖感)と示されています。タスク指向の汎化により、獲得が日常のADLに現れやすい、という解釈が成立します。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
訪問リハ利用者を介入群と対照群で比較。介入群でBarthel IndexとFrenchay Activities Index、転倒恐怖感の介入群のみ有意改善が示され、対照群は有意差なし。中央値の推移と有意性が図表で示される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
評価の定点化が“差”を検出する
別の研究は3か月・6か月で有意改善(心身機能・生活機能・生活の質)を示し、歴史的対照との比較でIADLが有意に優位と記載します。評価の標準化(Barthel Index)を同じ時点で行うことで、群間の差の検出が可能になります。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
生活行為向上マネジメントを用いた訪問リハビリテーションが地域在住の要介護高齢者の心身機能,生活機能および生活の質に及ぼす影響
生活場面を含む訪問リハを6か月継続し、3か月・6か月で有意改善を確認。傾向スコアで整えた歴史的対照との比較でIADLが有意に優位。評価時点の明確化が差の把握を後押しする設計となっている。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/44/3/44_341/_pdf/-char/ja
制度設計が検証と比較を後押しする
短期集中予防サービス(リエイブルメント)が制度として位置づき、住民向け資料でも目標設定と評価の枠組みが示されています。自治体の報告は、地域単位での実施・評価の情報を共有し、比較検証の土台を提供します。
出典
厚生労働省
あなたの街でもリエイブルメント!
短期集中で「再びできるようになる」ことを目指す考え方と、生活課題を出発点にした目標設定・評価の枠組みを提示。比較・検証に必要な前提を明瞭化している。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001102071.pdf
東京都福祉局
令和4年度 短期集中予防サービス 強化支援事業報告書
区市町村における短期集中予防サービスの実施・支援・評価の整理を提供。地域での運用情報が差の検証に資する土台となる。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/service-enhancement.pdf
研究の限界と適用範囲の明確化
今回参照した研究は多くが非ランダム化で、サンプル規模や介入内容に不均一性があります。結論の外挿には慎重さが必要で、適用範囲の明確化が欠かせません。ここでは記載どおりの数値と方向性のみを扱います。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
研究デザイン上の制約(非ランダム化、対象の特性、介入内容の個別化)があり、一般化には留意が必要である旨を本文で確認できる。結論は当該研究範囲に限定される。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
ここまでで、タスク指向の汎化、評価の標準化(Barthel Index)、短期集中予防サービス(リエイブルメント)、そして適用範囲の明確化という4点が、ADLの群間差を理解する鍵であることを整理しました。次は、研究ごとの具体的な差の数値を横並びで比較します。
よくある質問:検索意図に沿って“ADLの差”だけを確認する

- Q介護の生活リハビリはADLにどれくらい差が出る?
- A
訪問リハビリで生活場面のタスク練習を含めた介入群のみ有意に改善と報告があります。記載図表の中央値では、Barthel Indexが87.5→90.0、IADL(FAI)が9→11となり、対照群はBI90.0→90.0、FAI5→5で変化が確認されていません。
※エビデンス
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
訪問リハ利用者を介入群と対照群で比較。介入群でBI・FAI・転倒恐怖感が有意に改善し、対照群では有意差が示されていない。本文・図表に中央値の推移が掲載され、群間の方向性が明確である。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
- Q何か月で差が確認できる?
- A
3・6か月で身体機能・生活機能・QOLは有意改善。IADL(FAI)は介入群で有意。ADL(BI)は有意差が出ていないとする報告があります。さらに、傾向スコアで整えた歴史的対照との比較でIADLが有意に優位と示され、短期(3〜6か月)で差を確認できると述べています。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
生活行為向上マネジメントを用いた訪問リハビリテーションが地域在住の要介護高齢者の心身機能,生活機能および生活の質に及ぼす影響
6か月の訪問リハ介入で、3か月・6か月に有意改善を確認。傾向スコア調整を用いた歴史的対照との比較でIADLが有意に優位と示され、短期評価で差を把握できる設計になっている。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/44/3/44_341/_pdf/-char/ja
- Qどの指標で差を判断すべき?
- A
研究ではBarthel Index(ADL)が主要指標、補助としてFrenchay Activities Index(IADL)が用いられています。厚生労働省の資料でも、評価を標準化して同じ時点で比較する枠組みが示され、差の見える化に適しています。
出典
厚生労働省
あなたの街でもリエイブルメント!
短期集中で「再びできるようになる」ことを目指す枠組みを示し、生活課題の目標設定と評価の考え方を提示。標準的な評価の活用により、同一時点・同一尺度で比較しやすくなる。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001102071.pdf
- Q通所と訪問のどちらにエビデンスがある?
- A
今回提示の群間比較は訪問リハが中心です。通所・地域ベースについては、東京都の事業報告が短期集中予防サービスの実施・支援・評価を整理しており、差の検証を支える情報基盤として参照できます。
出典
東京都福祉局
令和4年度 短期集中予防サービス 強化支援事業報告書
区市町村の実施状況、支援内容、評価の枠組みを整理。地域単位での運用と成果把握を共有し、通所等を含む実装と比較検討の前提情報を提供している。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/service-enhancement.pdf
- Q今回の数値はどの程度一般化できる?
- A
参照研究には非ランダム化や介入内容の不均一性などの制約があります。したがって、結論の適用は当該研究範囲に限定する必要があります。本記事は記載どおりの数値・方向性のみを提示し、過度な一般化を避けます。
出典
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
研究デザイン上の限界(非ランダム化、対象特性、介入の個別化)に留意が必要である点を本文で確認できる。解釈は記載範囲に沿って行うことが適切である。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
まとめ:実施群と非実施群のADL差を「記載どおりの数値」で理解する
本記事は、やり方の解説を省き、実施群と非実施群のADL差だけに焦点を当てました。研究の記載どおりの数値を用いることで、実施群のみ有意改善(Barthel Index/IADL)が確認でき、短期(3〜6か月)でも差が把握できる点を示しました。制度資料では評価の標準化の枠組みが明確で、差の見える化に適しています。
- 実施群のみ有意改善が記載され、対照群は有意差なし
- Barthel Index(ADL)とIADL(FAI)で差の方向が一致
- 短期(3〜6か月)で差を確認できる評価点が明確
- 行政の枠組みで評価の標準化が可能になり、比較がしやすい
出典:
一般社団法人日本作業療法士協会
訪問リハビリテーションにおける生活行為向上マネジメントを活用した介入効果—転倒恐怖感と生活活動の変化に着目して—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/6/39_664/_article/-char/ja/
一般社団法人日本作業療法士協会
生活行為向上マネジメントを用いた訪問リハビリテーションが地域在住の要介護高齢者の心身機能,生活機能および生活の質に及ぼす影響
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/44/3/44_341/_pdf/-char/ja
厚生労働省
あなたの街でもリエイブルメント!
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001102071.pdf
東京都福祉局
令和4年度 短期集中予防サービス 強化支援事業報告書
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/service-enhancement.pdf
更新履歴
- 2025年9月27日:新規公開



