「利用者のために」と日々、真心を込めて行う食事介助。しかし、その一生懸命さが、時として利用者を危険にさらしている可能性があったとしたら、どうでしょうか。
忙しい現場の中で、食事や口腔のケアについて、こんな悩みを抱えていませんか?
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます
もし一つでも当てはまるなら、ご安心ください。 この記事では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会および日本老年歯科医学会の最新ガイドラインに基づき、現場で陥りがちな「良かれと思った介助」に潜むリスクと、あなたの悩みを解決するための具体的な安全なケアを解説します。
この記事を読めば
日々のケアに対する不安が、科学的根拠に裏付けされた「自信」に変わります。
良かれと思って…実は危険な食事介助5つの落とし穴
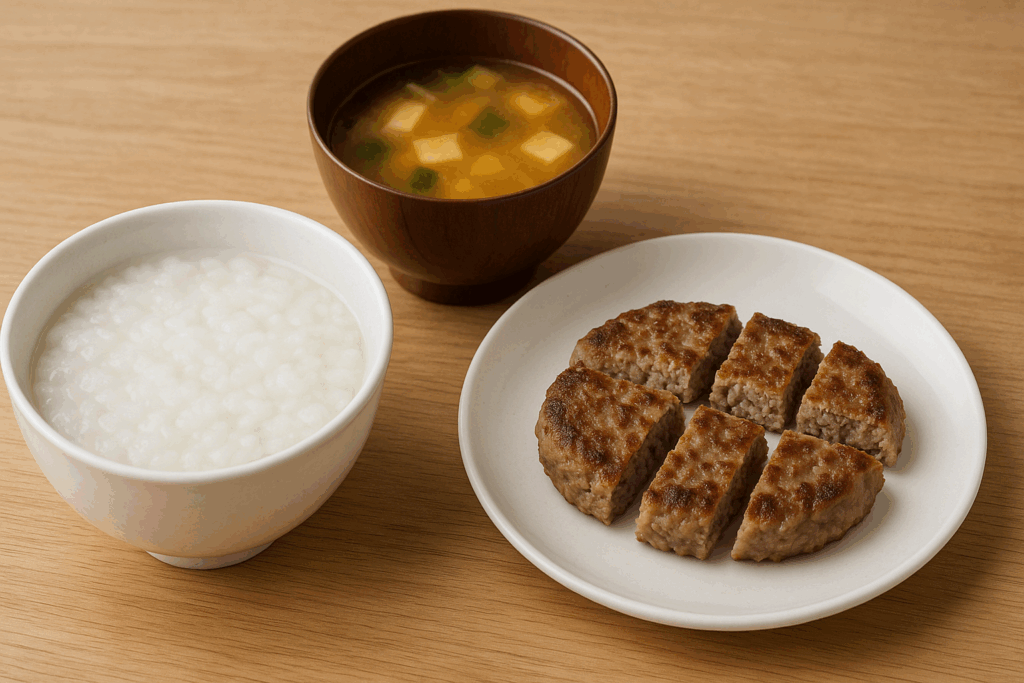
「利用者のために」と毎日懸命に行う食事介助。しかし、その親切心や当たり前だと思っていた習慣に、思わぬリスクが潜んでいることがあります。ここでは、多くの介護現場で見られる5つの具体的な場面を振り返ってみましょう。
「きざみ食・ミキサー食だから安心」という思い込み
食べやすくしたつもりの「きざみ食」が、口の中でまとまりにくく、かえって咽頭でばらけてしまうことがあります。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「嚥下調整食分類2021」では、食事の安全性は調理法ではなく、最終的な食事の物性(ぶっせい)、特に「凝集性(ぎょうしゅうせい)」という、まとまりやすさで判断することが示されています。見た目が細かければ安全というわけではなく、むしろリスクを高めてしまう可能性があるのです。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 出典元のタイトル: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類 2021
- URL: https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf
- 出典の要点:
- 食事の提供形態として「きざみ食」や「ミキサー食」という呼称が広く用いられているが、その物性は施設によって様々であり、情報伝達の際に誤解を生むリスクがあった。
- 学会分類は、これらの呼称に代わり、物性に基づいたコードで食形態を標準化し、施設間連携の安全性を高めることを目指す。
- 調理方法ではなく、最終的に提供される食事の物性(テクスチャー)で分類することが本分類の核心である。
早く食べさせようとする「詰め込み介助」
食事介助の主役は、介助者ではなく利用者本人です。しかし、忙しい業務の中では、つい介助者のペースで食事を進めてしまいがちです。日本老年歯科医学会のガイドラインでは、食事のペースは利用者に合わせ、完全に嚥下したことを確認してから次の一口を提供することが重要だと示されています。一口ごとの飲み込みをしっかり待つ「待つ介助」こそが、安全の基本です。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 食事介助における基本姿勢は、安定した座位が基本であり、頸部はやや前屈位を保つことが誤嚥予防に有効である。
- 一口量は、ティースプーンの半分程度を目安とし、利用者の嚥下状態を観察しながら調整する。
- 食事のペースは利用者に合わせ、完全に嚥下したことを確認してから次の一口を提供する「待つ介助」が重要である。
飲み込みやすいようにと「上を向かせる介助」
良かれと思って利用者の顎を上げさせると、喉の構造上、気道が広がり食べ物が気管に入りやすくなってしまいます。ガイドラインでは、安全な嚥下のために「頸部はやや前屈位を保つことが誤嚥予防に有効である」と明確に示されています。介助の際は、利用者が軽くお辞儀をするような、少し顎を引いた姿勢になっているかを確認することが大切です。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 食事介助における基本姿勢は、安定した座位が基本であり、頸部はやや前屈位を保つことが誤嚥予防に有効である。
- 一口量は、ティースプーンの半分程度を目安とし、利用者の嚥下状態を観察しながら調整する。
- 食事のペースは利用者に合わせ、完全に嚥下したことを確認してから次の一口を提供する「待つ介助」が重要である。
とりあえず清潔にするための「食後の歯磨き」
口腔内を清潔に保つ「器質的口腔ケア」は非常に重要です。しかし、その際に「最近、食べこぼしが増えたな」「わずかにむせることがあるな」といった些細な変化を見逃していないでしょうか。3学会合同のステートメントでは、これらが身体的な虚弱の前段階である「オーラルフレイル」の具体的な事象であると指摘しています。ただ清掃するだけでなく、機能の低下を示すサインを観察する視点が求められます。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年医学会, 日本サルコペニア・フレイル学会, 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント
- URL: https://www.gerodontology.jp/committee/file/OralFrailty_statement.pdf
- 出典の要点:
- オーラルフレイルの具体的な事象として、「滑舌低下」「食べこぼし」「わずかなむせ」「かめない食品の増加」などが挙げられる。
- これらの些細な口腔の衰えは、社会参加の減少や活動意欲の低下にもつながり得る。
- オーラルフレイルは、口腔機能の低下だけでなく、食生活の変化や社会性の低下といった複合的な問題を内包している。
水分補給のための「安易なお茶・水」
嚥下機能が低下した方にとって、とろみのないサラサラした液体は、咽頭への流入スピードが速すぎるため、最も誤嚥のリスクが高いものの一つです。日本摂食嚥下リハビリテーション学会は、水分のとろみについても「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」の3段階で分類しています。利用者の状態に合わせて、適切なとろみ調整を行うことが安全な水分補給の鍵となります。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 出典元のタイトル: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類 2021
- URL: https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf
- 出典の要点:
- 水分のとろみについては、「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」の3段階で分類される。
- 「薄いとろみ」はスプーンを傾けると”すっと”流れ落ち、フォークの背から”速やかに”流れ落ちる程度である。
- 「濃いとろみ」はスプーンを傾けても形状がある程度保たれ、流れにくい状態を指す。
これらの落とし穴は、決して特別なことではなく、日々の業務の中に潜んでいます。次の章では、なぜこれらの「良かれと思った介助」が危険なのか、その科学的な根拠をさらに詳しく見ていきましょう。
なぜ危険なの?科学的根拠からリスクを理解する

前の章で見た5つの落とし穴には、それぞれ明確な理由があります。ここでは、なぜその介助がリスクに繋がるのか、専門家の知見を基にその背景を紐解いていきましょう。一つひとつのケアに科学的な意味があることを知れば、介助の質はさらに高まります。
口の中で「まとまる」ことが重要な理由(嚥下調整食の物性)
安全な嚥下のためには、口の中に入れた食べ物がバラバラにならず、適度なまとまり=食塊(しょっかい)を形成し、スムーズに咽頭へ送り込まれることが非常に重要です。日本摂食嚥下リハビリテーション学会が策定した「嚥下調整食分類2021」は、このプロセスを安全に行うため、食事の物性、特にまとまりやすさを示す「凝集性(ぎょうしゅうせい)」を客観的な指標で定義しています。つまり、ただ柔らかい、細かいだけでは不十分で、口の中で適切にまとまるかどうかが、誤嚥のリスクを左右するのです。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 出典元のタイトル: 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類 2021
- URL: https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf
- 出典の要点:
- 本分類の目的は、嚥下調整食の的確な選択、使用、提供にあり、多職種間での円滑な情報共有に貢献することである。
- 本分類は「許可する食形態の物性」「禁止する副食」「対応する嚥下レベル」の3つの情報で定義される。
- 表示の基本は食事(コード)ととろみ(ネガティブラベル)であり、嚥下調整食の表示に際しては「嚥下調整食分類2021(学会分類)」と記載することが推奨される。
「オーラルフレイル」のサインを見逃すことの本当のリスク
「食べこぼし」や「わずかなむせ」といったサインは、単なる老化現象として見過ごされがちです。しかし、3学会合同ステートメントでは、この「オーラルフレイル」を放置すると、低栄養状態を招き、それが「身体的フレイルやサルコペニア(筋肉減少)」を加速させるという悪循環を生むと指摘しています。重要なのは、オーラルフレイルが「健康」と「機能障害」の中間に位置し、適切な対応によって健康な状態に戻れる「可逆性」を持つ段階であるということです。早期に気づき、介入することが、利用者の自立した生活を守ることに繋がります。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年医学会, 日本サルコペニア・フレイル学会, 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント
- URL: https://www.gerodontology.jp/committee/file/OralFrailty_statement.pdf
- 出典の要点:
- オーラルフレイルは、「健康」と「機能障害(要介護)」の中間に位置し、「可逆性」を有する段階である。
- 適切な対応により健康な状態に回帰できる可能性がある一方で、放置すると機能障害へと進行するリスクをはらんでいる。
- この段階での早期発見と適切な介入が、健康長寿の延伸において極めて重要である。
たった数度の角度が命取りに。「嚥下しやすい姿勢」の科学
食事介助の基本は、安定した座位から始まります。特に、頸部の角度は誤嚥リスクに直結します。日本老年歯科医学会のガイドラインでは、「頸部をやや前屈位」、つまり軽く顎を引いた姿勢を保つことが、誤嚥予防に有効であると示されています。この姿勢をとることで、喉の構造上、気管の入り口が覆われ、食塊が自然に食道へと誘導されやすくなります。逆に顎が上がると気道が開いてしまい、食べ物が入り込むリスクが格段に高まるのです。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 食事介助における基本姿勢は、安定した座位が基本であり、頸部はやや前屈位を保つことが誤嚥予防に有効である。
- 一口量は、ティースプーンの半分程度を目安とし、利用者の嚥下状態を観察しながら調整する。
- 食事のペースは利用者に合わせ、完全に嚥下したことを確認してから次の一口を提供する「待つ介助」が重要である。
このように、何気ない介助の一つひとつに科学的な背景があります。これらのリスクを理解した上で、次の章では、明日から実践できる具体的な安全なケアの方法を見ていきましょう。
今日からできる!誤嚥を防ぐ安全なケア3つの原則

リスクの背景を理解すれば、次に見えてくるのは具体的な実践方法です。特別な技術や器具は不要です。明日からの介助にすぐ活かせる、3つの基本原則をご紹介します。これらを意識するだけで、あなたのケアはより安全な「支援」へと変わります。
原則①:食事の前に「環境と口腔」を整える(準備の原則)
安全な食事は、利用者がスプーンを口にする前から始まっています。まず、足が床につき、深く腰掛けた安定した座位になっているかを確認し、軽く顎を引いた姿勢を保ちます。さらに、日本老年歯科医学会のガイドラインでは、食事の前に嚥下に関わる器官の準備運動を行う「機能的口腔ケア」が示されています。唾液の分泌を促し、嚥下反射を誘発しやすくする「嚥下体操」などを取り入れることで、誤嚥のリスクを食事の前に低減させることができます。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 嚥下体操は、嚥下に関わる器官の準備運動であり、①深呼吸、②首の運動、③肩の運動、④頬の運動、⑤舌の運動、⑥発声練習、⑦咳払い、から構成される。
- 食前に行うことで、唾液の分泌を促進し、嚥下反射を誘発しやすくする効果がある。
- 安全な食事摂取のための準備として、日常的に取り入れることが推奨される。
原則②:「一口・一口」をしっかり観察する(観察の原則)
介助中は、利用者の食べる様子を注意深く観察することが最も重要です。ガイドラインでは「一口量は、ティースプーンの半分程度を目安」とすることが示されています。スプーンを口に運んだ後は、利用者の喉の動きを見て、完全に嚥下したことを確認してから次の一口に進みましょう。介助者のペースではなく、利用者のリズムに合わせた「待つ介助」を徹底し、利用者の嚥下状態を観察しながら食事を進めることが、誤嚥を防ぐ上で不可欠です。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 食事介助における基本姿勢は、安定した座位が基本であり、頸部はやや前屈位を保つことが誤嚥予防に有効である。
- 一口量は、ティースプーンの半分程度を目安とし、利用者の嚥下状態を観察しながら調整する。
- 食事のペースは利用者に合わせ、完全に嚥下したことを確認してから次の一口を提供する「待つ介助」が重要である。
原則③:小さな「変化」を記録し、チームに共有する(連携の原則)
介護職員は、多職種連携における重要なチームの一員です。なぜなら、利用者に最も身近な存在として、日々の小さな変化に気づけるからです。ガイドラインでは、介護職員が食事介助や口腔ケアを日常的に実施し、日々の変化を観察・報告することの重要性が示されています。食事に時間がかかるようになった、特定の食品でむせやすくなった、といった気づきを記録・共有することが、歯科医師や言語聴覚士、管理栄養士など他職種の専門的なアプローチに繋がり、利用者を守ることに繋がります。
出典元の要点(要約)
- 組織名: 日本老年歯科医学会
- 出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
- URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
- 出典の要点:
- 看護師は、全身状態の管理、日常的な食事介助や口腔ケアの実践、他職種への情報提供など、連携のハブとしての役割を担う。
- 介護職員は、利用者に最も身近な存在として、食事介助や口腔ケアを日常的に実施し、日々の変化を観察・報告する重要な役割を持つ。
- これらの職種による日常的な観察とケアが、専門的介入の基盤となる。
これらの3つの原則は、日々の介助にすぐに取り入れられるものです。意識するだけで、ケアの質は大きく変わります。最後に、現場でよくある具体的な疑問にお答えします。
現場の「もしも…」に答えるQ&A
ここまでの原則を踏まえ、実際の現場で判断に迷う具体的な場面について、ガイドラインの考え方に基づきQ&A形式でお答えします。いざという時に自信を持って対応するための知識として、ぜひ参考にしてください。
- Q食事中にむせが頻発する場合、まず何をすべきですか?
- A
直ちに食事を中断し、無理に続けようとしないでください。日本老年歯科医学会のガイドラインでは、摂食嚥下障害が疑われた場合、重篤な合併症である誤嚥性肺炎や窒息を予防するために、早期の相談と専門的評価が重要であると示されています。まずは利用者の呼吸状態が落ち着くのを待ち、口腔内に残っているものがあれば、可能なら取り除きます。そして、その出来事を必ず記録し、看護師やリーダー、ケアマネジャーに報告・相談してください。
出典元の要点(要約)
組織名: 日本老年歯科医学会
出典元のタイトル: 生活期におけるリ-ハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
出典の要点:
- 摂食嚥下障害が疑われた場合、まずはかかりつけ医やケアマネジャーに相談し、必要に応じて歯科医師や耳鼻咽喉科医、リハビリテーション科医などの専門医へつなぐ。
- 早期の相談と専門的評価が、重篤な合併症である誤嚥性肺炎や窒息、低栄養、脱水を予防するために重要である。
- 介護職員や家族は、日々の「気づき」を専門職に伝える重要な役割を担う。
- Q口腔ケアを嫌がる方には、どう対応すればよいですか?
- A
認知症を有する高齢者など、ケアを拒否される場合があります。その際は、まず安心できる環境を整えることが大切です。ガイドラインでは、食事拒否がある場合、その背景にある原因(口腔内の痛み、体調不良、心理的要因など)を多角的にアセスメントする必要がある、と示唆されています。無理強いはせず、まずは保湿ジェルを塗るだけ、うがいだけ、といった受け入れやすいケアから試してみましょう。そして、なぜ拒否があるのかをチームで考察し、歯科医師や歯科衛生士といった専門職に相談することも重要です。
出典元の要点(要約)
組織名: 日本老年歯科医学会
出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
出典の要点:
- 認知症を有する高齢者への対応では、まず安心できる環境を整え、食事に集中できるよう配慮する。
- 食具の認識が困難な場合は、自助具の活用や介助者のサポートが有効である。
- 食事拒否がある場合は、その背景にある原因(口腔内の痛み、体調不良、心理的要因など)を多角的にアセスメントする必要がある。
- Q専門職には、いつ、どのように相談すればよいですか?
- A
摂食嚥下障害のスクリーニング(簡易的な検査)で、嚥下障害が疑われる結果が出た場合は、専門職への相談を検討します。例えば「反復唾液嚥下テスト(RSST)」で、30秒間に唾液を飲み込む回数が3回未満だった場合などが一つの目安です。相談する際は、「最近、お茶でむせることが週に3回あります」「硬いものを食べた後、口の中に残りやすくなっています」というように、具体的な観察事項を伝えることが、その後のスムーズな連携に繋がります。
反復唾液嚥下テスト(RSST)とは?
反復唾液嚥下テスト(RSST)は、特別な器具を使わずに嚥下障害(飲み込みの障害)の可能性を調べるための簡単なスクリーニング検査です。
検査方法
- 被験者を座らせ、人差し指と中指を喉仏(甲状軟骨)と舌骨の上に軽く置きます。
- 「今から30秒間で、できるだけたくさん唾を飲み込んでください」と指示します。
- 指先で喉仏が上下に動くのを数え、30秒間に何回嚥下できたかを測定します。
評価の目安
30秒間で3回未満の場合、嚥下障害の疑いがあると判断され、より詳しい検査が推奨されます。このテストは、唾液の分泌量や、嚥下反射を意図的に起こす能力を評価しています。
出典元の要点(要約)
組織名: 日本老年歯科医学会
出典元のタイトル: 生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン ダイジェスト版
URL: https://www.gerodontology.jp/publishing/file/careguideline_202403.pdf
出典の要点:
- 摂食嚥下障害のスクリーニングには、質問紙法とテスト法がある。
- 質問紙法としては「聖隷式嚥下質問紙」や「EAT-10」が有用であり、患者の自覚症状を評価する。
- テスト法としては「反復唾液嚥下テスト(RSST)」や「改訂水飲みテスト(MWST)」があり、嚥下機能を客観的に評価する。
まとめ:明日から、あなたのケアは「支援」に変わる
本記事では、「良かれと思って」行っている日常のケアに潜むリスクと、その科学的根拠について解説してきました。最も大切なのは、食事介助の目的を「食べさせること」から、「ご本人が安全に、自分の力で食べられる環境を整える支援」へと転換することです。これは、日本老年歯科医学会のガイドラインが示す、ケアの基本となる考え方です。
完璧な介助を目指す必要はありません。まずは3つの原則のうち、「一口ごとの嚥下をしっかり観察する」ことから意識してみてください。あなたのその専門的な観察眼こそが、利用者の誤嚥性肺炎や窒息のリスクを減らし、「オーラルフレイル」の進行を防ぐための最も強力な武器となります。
チームの一員として、あなたの「気づき」は利用者の「食べる喜び」と尊厳を守ることに直結します。明日からのあなたのケアが、より自信に満ちた、温かい「支援」となることを願っています。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月9日:新規投稿



