「もっと元気になってほしい」「少しでも楽に過ごしてほしい」。
介護現場で私たちが抱くその想いが、なぜかご本人に届かず、空回りしてしまう…。パーキンソン病などでADL(日常生活動作)が低下していく方を前に、そんなもどかしさを感じていませんか?
一つでも当てはまったら、この記事がきっとお役に立ちます。
もしあなたが一つでも「あるある」と感じたなら、ご安心ください。そのすれ違いには、ちゃんとした理由があります。この記事では、その根本原因と、明日から試せる具体的な解決策を、科学的根拠(エビデンス)に基づいて解説していきます。
この記事を知っていると
結論:すれ違いの原因は「生活ペース」のズレでした

私たちが日々感じるご本人との心のすれ違い。その根本的な原因は、支援の「内容」や「熱意」の問題ではありません。実は、私たちとご本人の「生活ペース」のズレにこそ、その答えが隠されています。ケアの視点を少し変えるだけで、明日からの関わりが大きく変わるかもしれません。
ADL低下がもたらす喪失感とは、「自分らしさ」を失う痛み
ADLが低下し、「昨日までできていたこと」ができなくなる。それは単に身体が動きにくくなる以上の、ご本人の“自分らしさ”や“人生の主導権”が失われていく深い痛みを伴います。日本精神神経学会の報告では、パーキンソン病を持つ方の約3人に1人がうつ症状や不安を経験するとされており、私たちが関わる方の多くが、目に見えない心の痛みを抱えているのが現実です。
出典元の要点(要約)
日本精神神経学会
あいまい化する精神疾患と神経疾患の境界
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1270070473.pdf
総説は、パーキンソン病で「ほぼすべての…非運動症状」がみられ、精神症状が高頻度であると述べる。特に「うつ症状・不安は…点有症率は 30~35%」とし、ADL 低下局面で観察される抑うつ・不安を医学的背景から位置づける。
良かれと思った支援が、ご本人の意欲を奪っていないか?
日本神経学会の『パーキンソン病診療ガイドライン2018』では、リハビリテーションは「患者本人が参加できる治療法」であり、「患者本人の意欲やモチベーションが影響する」と明確に記されています。私たちが効率を優先し、「さあ、時間ですよ」と急かしてしまうと、知らず知らずのうちにご本人が主体的に参加する機会を奪い、大切な意欲を削いでしまう可能性があるのです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
リハビリは「患者本人が参加できる治療法」であり、「患者本人の意欲やモチベーションが影響する」。さらに「患者の積極性を引き出す」と述べ,参加型の設計と動機づけの重要性を強調する。入居者の主体性を尊重した計画立案に資する記述である。
ケアの視点を「動作の介助」から「QOLの向上」へ
私たちの役割は、単に動作を介助することだけではありません。ガイドラインが示すリハビリの最終的な目的は、「QOL(生活の質)の向上」です。つまり、できないことを補うだけでなく、その人らしい時間を少しでも豊かに過ごせるよう、生活全体をデザインしていく視点が求められます。ご本人のペースを尊重することは、その人らしい生活を取り戻すための、最も重要な第一歩なのです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
本章は、リハビリテーションが内科・外科治療に加えることで「症状のさらなる改善や QOL の向上が期待できる治療法」であると位置づける。患者本人が参加できる治療であり、「患者本人の意欲やモチベーション」が重要。PT・OT・ST等のチームで介入し、OT は上肢機能など「ADL の訓練」を担う。
ご本人との関わりの中で大切なのは、「何をやるか」以上に「どんな時間を作るか」という視点です。ケアの中心に「ご本人のペース」を置くことで、これまで届かなかった想いが、きっと伝わるようになります。
現場の事例:3つの「すれ違い」とその医学的背景

理論は分かっていても、現場では予測不能な出来事が起こります。ここでは、多くの介護士が経験する具体的な3つのケースを取り上げ、その行動の裏に隠された医学的な背景を探ってみましょう。ご本人の世界を理解するヒントがここにあります。
事例1:朝の着替えで、急に身体が固まってしまうAさん
「Aさん、腕を上げてくださいね」。更衣介助をしようとすると、Aさんの身体が急にこわばり、一点を見つめたまま動かなくなってしまいました。急いでいる時に限ってこうなるため、「わざとやっているの?」とつい思ってしまいます。しかし、これはご本人の意思とは関係なく起こる「すくみ足」や「無動」といったパーキンソン病の代表的な運動症状の一つです。焦りやプレッシャーを感じると症状が出やすくなるため、私たちの関わり方が鍵となります。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
ADLの柱である移動能力に対し、「移動訓練」「リズムをもったパターンでの歩行」「筋力訓練」が具体的に挙げられる。歩行の開始・継続が困難な入居者には外部キューの導入が考慮され,個別化した練習計画が推奨される。
事例2:リハビリを突然「もうやらない」と言い出したBさん
昨日までは「頑張るわ」と意欲的だったBさんが、今日は「もうやっても無駄だから」とリハビリを拒否。励ましても「どうせ良くならないし」とふさぎ込んでいます。これは、単なる気まぐれではありません。厚生労働省の資料でも、パーキンソン病の症状として「意欲の低下」が挙げられています。目に見えない心のエネルギーが低下している状態であり、精神的な休息が必要なサインなのかもしれません。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
6 パーキンソン病
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173440.pdf
資料は、パーキンソン病が運動症状だけでなく「非運動症状も注目」される疾患であるとし、「意欲の低下、認知機能障害、幻覚、妄想」等を列挙し「パーキンソン複合病態として認識すべき」とまとめる。ADL 低下と並行する心理・精神症状の理解に不可欠な枠組みを提供する。
事例3:「隅っこに誰かいる」と不安を訴えるCさん
認知症のないCさんが、夜間に「あそこに誰か座っている」とカーテンの隅を指差して不安そうにしています。「誰もいませんよ」と説明しても、Cさんは納得せず、かえって興奮してしまいました。これは「軽症幻覚(minor hallucinations)」と呼ばれる症状の可能性があります。ご本人にとってはっきりと見えているため、否定せずに気持ちを受け止め、安心できる環境を整えることが大切です。
出典元の要点(要約)
日本精神神経学会
あいまい化する精神疾患と神経疾患の境界
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1270070473.pdf
PDでは「実体意識性」「通過幻覚」「錯視」などの軽微な知覚異常が報告され,これらは「軽症幻覚(minor hallucinations)」と総称される。入居者の訴えが曖昧な場合でも,現場は現象の名称と性質を把握し,過度な否定を避けつつ観察を続ける必要がある。
一見すると理解しがたいご本人の言動も、その背景にある病気の症状を知ることで、私たちの関わり方は大きく変わります。ご本人を否定するのではなく、その方が見ている世界に寄り添うことが、信頼関係の第一歩です。
【エビデンスで解説】なぜ「生活ペース」の尊重が重要なのか
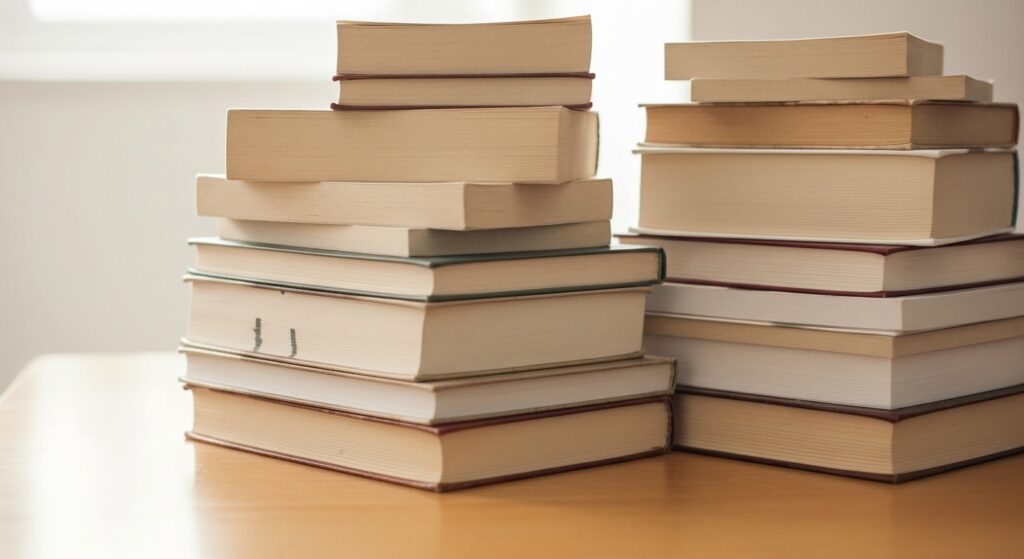
ご本人の言動に一つひとつ向き合う中で、「なぜ?」という疑問が生まれるのは自然なことです。その「なぜ?」を医学的な視点から理解することで、私たちのケアは「経験」から「根拠ある実践」へと変わります。ここでは、その科学的な背景を解説します。
パーキンソン病は心と身体の「パーキンソン複合病態」
私たちが向き合っているパーキンソン病は、手足の震えや動きにくさといった運動症状だけの病気ではありません。厚生労働省は、意欲の低下や幻覚といった精神症状も含めた「パーキンソン複合病態として認識すべき」という考え方を示しています。心と身体の症状が複雑に絡み合っているからこそ、私たちは生活全体を広く見渡す必要があるのです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
6 パーキンソン病
https://www.mhlw.go.jp/content/1090_5000/001173440.pdf
疾患概念として「パーキンソン複合病態」との認識が示され,治療は現時点で「全ての治療は対症療法」とされる。薬物の基本は「L-dopa とドパミンアゴニスト」で,ADLの変動や精神症状と合わせて総合的に評価し,多職種連携で支援することが前提となる。
3人に1人が経験する「うつ・不安」という現実
ご本人がふさぎ込んだり、「もう何もしたくない」と口にしたりする時、それは単なる気分の問題ではないかもしれません。ある研究報告では、パーキンソン病の方の「うつ症状・不安の点有症率は30~35%」と、非常に高い頻度で精神的な苦痛を抱えていることが示されています。この症状は病気のどの段階でも起こりうるため、私たちは常にその可能性を心に留めておく必要があります。
出典元の要点(要約)
日本精神神経学会誌
あいまい化する精神疾患と神経疾患の境界
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1270070473.pdf
「うつ症状・不安」の「点有症率は 30~35%」,「うつ」は「すべての病期」に出現する。さらに「サイコーシス」は「点有症率は 30%前後,累積有症率は 50~60%」と整理され,ADL変化時の精神症状評価の必要性が裏づけられる。
薬が見せる「幻覚・妄想」と副作用のリスク
ご本人の言動の変化には、治療薬が影響している可能性もあります。特に高齢の方や認知症を合併している場合、ドパミンアゴニストという種類の薬によって「幻覚・妄想が誘発されやすく」なることが知られています。介護士である私たちが日々の変化を注意深く観察し、その情報を医療チームに正確に伝えることが、ご本人にとって最適な治療環境を整える上で不可欠な役割となります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
6 パーキンソン病
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173440.pdf
高齢・認知症合併例はドパミンアゴニストで「幻覚・妄想」が誘発されやすいと明記される。治療全体は「病勢の進行…を止める治療法」は未確立であるため,薬剤の調整と副作用の観察を介護現場でも共有し,生活場面でのリスク低減を図る。
すべてのケアの目的は「QOL(生活の質)の向上」
リハビリテーションを含め、私たちが行う全てのケアは何を目指しているのでしょうか。日本神経学会のガイドラインでは、その目的を「症状のさらなる改善やQOLの向上が期待できる治療法」と定義しています。つまり、単に身体機能を維持・改善するだけでなく、その人らしい満足のいく生活を送れるように支援することこそが、私たちの共通のゴールなのです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
リハは「症状のさらなる改善や QOL の向上が期待できる治療法である」と定義され,「他の治療法と組み合わせて行うことが不可欠である」と明示。薬物・外科治療と併用する多面的介入が,機能と QOL の改善に寄与する立場を示す。
このように、医学的な背景を理解することは、ご本人の行動を正しく解釈し、ケアの本当の意味を見出すための羅針盤となります。私たちの関わりが、根拠に裏付けられた専門的な支援へと深まっていくのです。
明日からできる関わり方のヒント(Q&A形式)

理論や背景を理解した上で、次に知りたいのは「では、具体的にどうすればいいのか?」という実践的なヒントのはずです。ここでは、介護士の皆さんが現場で抱える具体的な疑問に、Q&A形式でお答えしていきます。
- Q声をかけても反応が薄い時、どうすればいいですか?
- A
ご本人の反応が薄い時、それはあなたを無視しているのではなく、「意欲の低下」という症状が出ているのかもしれません。厚生労働省の資料でも示されている通り、これはパーキンソン病の代表的な非運動症状の一つです。言葉でのコミュニケーションが難しい時は、無理に言葉を引き出そうとせず、そばに座って同じ時間を過ごしたり、優しく腕に触れたりするなど、言葉以外の方法で「あなたのそばにいますよ」というメッセージを伝えることが、ご本人の安心に繋がります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
6 パーキンソン病
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173440.pdf
概説は「非運動症状も注目されている」とし,具体例として「意欲の低下、認知機能障害、幻覚、妄想」を列挙。臨床像を運動・精神双方から把握する必要性を示す。
- Q拒否が強い時、無理強いしてでもやるべきですか?
- A
無理強いは避けましょう。日本神経学会のガイドラインでは、リハビリは本人の「意欲やモチベーションが影響する」とされています。これはケア全般にも通じる考え方です。強い拒否は、心や身体が「今は無理だ」と発しているサインかもしれません。まずは「お辛いんですね」「今日は乗り気じゃないんですね」とご本人の気持ちを一度受け止めることが大切です。その上で、なぜ拒否しているのかをチームで考え、関わりの時間や方法を見直すきっかけにしましょう。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173440.pdf
本章は「リハビリテーションは…症状のさらなる改善や QOL の向上が期待できる治療法」と定義し,「患者本人が参加する」という特性上「意欲やモチベーション」が結果に関与すると明記する。さらに「リハビリテーションはチームアプローチ」であり,多職種の協業が前提とされる。ADL が急低下した入居者に対しても,参加型の介入設計とチームでの評価・再調整が重要である。
- Q介護士として、医療とどう連携すればいいですか?
- A
あなたは「生活場面の専門家」です。医師や看護師が診察室では見ることのできない、日中の細かな変化を捉え、記録し、伝えることが非常に重要な役割となります。例えば、日中の眠気一つをとっても、その背景に「うつ」や「薬剤の影響」など様々な要因が考えられます。「いつ」「どのような状況で」「どのくらいの時間」眠気があるのか、といった具体的な情報を共有することで、医療チームはより的確な判断を下すことができます。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_28.pdf
Q&Aは「日中過眠」の背景要因として「うつ」「向精神薬」「レム睡眠行動障害」等を挙げ,問診・薬歴・睡眠習慣の評価を「確認しておく必要がある」と整理する。ADL低下と覚醒度低下が並行する場面でのチェックリスト化に有用である。
- Q「リズム」をケアに活かすって、具体的にどうやるのですか?
- A
パーキンソン病のリハビリでは、「聴覚によるリズム刺激」が脳内の歩行リズムを整えるのに効果的とされています。この原理は、歩行以外のケアにも応用できます。例えば、ベッドから起き上がる時に「いーち、にーの、さん」とリズミカルに声をかけたり、食事の際に静かな音楽を流して落ち着いたペースを作ったり。一定のリズムは、次の動きへ移行するための、脳にとっての“道しるべ”になるのです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
音楽療法は外部キュー戦略として位置づけられ,「外部からの音リズムが脳内の歩行リズムを喚起」する機序を説明。「聴覚によるリズム刺激が最も…効果的」とされ,歩行障害への実践的手段としての有用性が示される。
日々のケアに小さな工夫を取り入れることで、ご本人の反応が変わる瞬間があります。一つひとつの関わりが、ご本人の「できる」を引き出し、生活の質を高めることに直結しているのです。
まとめ:介護とは“その人の時間”を支える仕事
ここまで、ADLが低下した方の「喪失感」の背景と、その方の「生活ペース」に寄り添うことの重要性について、医学的な根拠を基に見てきました。最後に、私たちが明日から大切にしたい視点を改めて確認しましょう。
「できないこと」ではなく「今できること」に光を当てる
ケアの目的は、失われた機能を取り戻すことだけではありません。日本神経学会のガイドラインでは、リハビリは病気のどのステージにおいても有効性が高いと示されています。これは、どんな状態の方であっても、その人なりの「できること」や「穏やかな時間」を見つけ、支えることができるという希望の証です。私たちの役割は、ご本人が「今の自分」として輝ける瞬間を、一つでも多く作っていくことにあります。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
ガイドライン作成委員会の結論は「有効」「安全」と明記し,「早期から進行期までどのステージにおいても介入すると有効性が高いと思われる」。病期横断でリハ介入が推奨され,日常ケアへの継続的組込みの意義が裏づけられる。
あなたの観察が、最高のチームケアに繋がる
介護士は、ご本人の生活に最も長く寄り添う専門職です。だからこそ、あなたの細やかな観察は、最高の「チームアプローチ」を実現するための不可欠な要素となります。日々の様子の変化や、声にならないサインを捉え、チームに共有すること。それこそが、ご本人のQOL(生活の質)向上という共通のゴールを達成するための、最も価値ある貢献なのです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
多職種連携を前提に「リハビリテーションはチームアプローチ」とされる。本章は,OT による「ADL の訓練」を含む体系的介入が「症状のさらなる改善や QOL の向上」に寄与することを記す。現場では各職種の狙いを共有し,評価指標を揃えて進める意義が強調される。
明日から、まずは5分、相手のペースに耳を澄ませてみませんか
ご本人のペースを守るケアは、「誤嚥性肺炎」などの生命に関わる合併症を防ぐことにも繋がります。それは、日々の生活意欲を支え、臥床状態になるのを少しでも遅らせることに直結するからです。難しく考える必要はありません。まずは一日5分でもいい。隣に座り、ご本人の呼吸や身体の微細な動きに意識を向けてみる。その静かな時間が、ケアの質を大きく変えるはずです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
6 パーキンソン病
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001173440.pdf
予後では「臥床生活となってからの合併症」に注意し,「誤嚥性肺炎などの感染症が直接死因になることが多い」と記載。嚥下・感染予防の重要性が明確である。
支援が伝わらないと感じた時こそ、立ち止まるチャンスです。私たちの時計を少しだけ緩め、ご本人の時間に寄り添うこと。その温かい眼差しが、ご本人の心を支え、尊厳を守る最高のケアとなるでしょう。
更新履歴
- 2025年10月17日:新規公開




