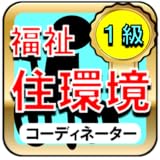介護現場で、特定の上司や先輩からの「威圧的な態度」や「理詰めの指導」に悩み、「今日も顔色をうかがわないと…」と心が疲弊していませんか?
「指導だから我慢しなくては」「自分ができないからだ」と自分を責めてしまうと、やがて心が燃え尽きてしまう(バーンアウト)危険性があります。
大切なのは、相手を変えようとすることではなく、相手の言動を「上手にかわし」、あなた自身の心を守る「技術」を身につけることです。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます。
この記事を知っていると
- 相手がなぜ「威圧的」になるのか、その心理的背景(自己愛憤怒など)を研究(日本教育心理学会など)に基づき理解できます。
- 我慢(服従)でも反撃(攻撃)でもない、第3の対処法「アサーション(自他尊重の主張)」という具体的なスキルを学べます。
- 相手の感情に巻き込まれず、自分自身の「情緒的消耗(バーンアウト)」を防ぐための心理的な防衛術がわかります。
この記事が、あなたが威圧的な言動に振り回されず、ご自身の心身の健康を守り、介護という専門職を長く続けていくための「技術」を身につける一助となれば幸いです。
結論:上手な「交わし方」とは、相手の土俵に乗らない技術(スキル)です

威圧的な上司に悩むあなたに、まず知っておいてほしい「結論」をお伝えします。最も上手な「交わし方」とは、相手の感情的な土俵に上がらず、あなた自身の心を守る「技術」を身につけることです。これは「我慢」や「無視」とは異なります。
「交わす」とは「相手の心理背景」を理解すること
なぜ相手は威圧的になるのでしょうか。日本教育心理学会の総説によれば、自己愛傾向が強い人は、誇大性や特権意識を持つ一方で、批判されると「自己愛憤怒」と呼ばれる激しい怒りで反応することが示されています。相手の威圧的な言動は、もしかすると批判や脅威から自分を守るための「防衛反応」かもしれません。この背景を理解することは、相手に同情するためではなく、あなたが冷静さを保ち、感情的に巻き込まれないための第一歩となります。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
誇大性・特権意識や「自己愛憤怒」が自己愛的特徴として示される。威圧・否定的な言動への対応では、反応の高ぶりを前提に事実の記述と境界の共有を軸に、対立のエスカレーションを避けるコミュニケーション設計が求められる。
「交わす」とは「我慢」でも「反撃」でもない「アサーション」である
「交わす」とは、我慢(受動的)でも、言い返す(攻撃的)でもない、第三の方法です。それが「アサーション」と呼ばれる心理教育の手法です。 アサーションとは、相手を尊重しつつ、自分の意見や要望を適切に主張することです。日本教育心理学会の研究でも、アサーション・トレーニングは「自己主張」と「他者尊重」を両立させ、怒り表現をコントロールする効果が示されています。これが「上手な交わし方」の具体的な技術(スキル)の核となります。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/67/4/67_317/_pdf/-char/ja
アサーションは相手尊重を前提とした自己主張の心理教育である。攻撃的にならずに境界や要望を伝える標準手順(事実→感情→要望→結果)の導入に適する。
日本教育心理学会
大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果(記事本文)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/67/4/67_317/_article/-char/ja/?utm_source=chatgpt.com
本文でも、自己主張と他者尊重の両立や視点取得・怒り表現への効果が明記される。話を聞かない/攻撃的な相手に対しても、相互尊重を保ちつつ目的を達成する対応スキルとして根拠づけられる。
なぜ「交わす」必要があるのか?(バーンアウト予防)
威圧的な言動を受け止め続けることは、あなたの心身を危険にさらします。日本老年社会科学会の介護職員を対象とした研究では、バーンアウト(燃え尽き症候群)は「情緒的消耗感」が中核となるとされています。 威圧的な上司との対人関係(仕事の要求度の高さ)は、この「情緒的消耗感」を強め、やがては利用者へのケアの質が低下する「脱人格化」や、離職につながる可能性があります。「交わす」技術は、この燃え尽きを防ぎ、あなた自身を守るために不可欠な防衛術なのです。
出典元の要点(要約)
日本老年社会科学会
介護職員におけるバーンアウトとワークエンゲイジメントの関係性—JD-Rモデルによる検討—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/42/3/42_188/_pdf/-char/ja
バーンアウトは三つの側面からなる症候群で、情緒的消耗が中核とされる。人間関係の不調や否定的態度は個人特性だけでなく症候群の表現であり、休息や支援導入の判断根拠となる。
このように、相手の心理を理解し、アサーションという技術で対応し、自分の情緒的消耗を防ぐこと。これが、威圧的な上司と対峙し、介護職として長く健康に働き続けるための「結論」です。
よくある事例:こんな「威圧的な場面」ありませんか?

介護現場でよく遭遇する「威圧的な場面」を振り返ってみましょう。あなたが「交わしにくい」と感じるこれらの言動には、特有の心理的な背景が隠れているかもしれません。
事例1:他の職員の前で理詰めで詰めてくる
「なぜできない?」「前も言ったよね?」「論理的におかしい」と、他の職員が見ている前で、逃げ場がないように理詰めで詰問してくるケースです。 これは、指導という目的以上に、自分の優位性を示したいという「誇大性」や「特権意識」の表れかもしれません。
日本教育心理学会の研究総説では、このような特徴を持つ人は、批判されると逆に怒るといった感情傾向(「自己愛憤怒」)を示すことが指摘されています。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
誇大性・特権意識や「自己愛憤怒」が自己愛的特徴として示される。威圧・否定的な言動への対応では、反応の高ぶりを前提に事実の記述と境界の共有を軸に、対立のエスカレーションを避けるコミュニケーション設計が求められる。
事例2:自分の非を認めず、責任転嫁してくる
上司自身の指示が曖昧だったり、確認不足が原因であったりしても、「あなたがちゃんと確認しないからだ」「報告がなかったせいだ」と、部下や他者のせいにして責任転嫁するケースです。 これは、自分の非を認めること、つまり批判されることを極端に恐れ、自分の立場を守ろうとする防衛反応である可能性が考えられます。
日本教育心理学会の総説では、こうした関わりの難しさに対し、周囲が拒否や批判の立場に偏らず、支援的な視点で理解する枠組みの必要性も示唆されています。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
自己愛的問題のある相手への関与は難易度が高いが、拒否・批判に偏らず支援志向の仮説で理解する姿勢が求められる。現場では、感情の承認と課題の具体化、役割・境界の明確化を並行させる介入が適合する。
事例3:機嫌によって態度が変わり、常に顔色をうかがう
朝の挨拶をしても無視されたり、些細なことで不機嫌になったり、日によって指示内容が変わったりするケースです。 このような予測不能な言動は、周囲の職員にとって深刻なストレス(仕事の要求度)となり、「常に顔色をうかがう」状態を生み出します。
日本老年社会科学会の介護職員を対象とした研究では、このような状態が「情緒的消耗感」を高め、やがてバーンアウト(燃え尽き症候群)につながる中心的な要因であることが示されています。
出典元の要点(要約)
日本老年社会科学会
介護職員におけるバーンアウトとワークエンゲイジメントの関係性—JD-Rモデルによる検討—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/42/3/42_188/_pdf/-char/ja
バーンアウトは三つの側面からなる症候群で、情緒的消耗が中核とされる。人間関係の不調や否定的態度は個人特性だけでなく症候群の表現であり、休息や支援導入の判断根拠となる。
これらの事例は、単なる「個人の性格」の問題として片付けるのではなく、専門的な知見からその背景を理解し、技術的に対処(交わす)すべき「現象」であることがわかります。
なぜ威圧的なのか? なぜ疲弊するのか?

なぜ上司は威圧的になり、私たちはそれに深く疲弊してしまうのでしょうか。その「理由」を、専門的な研究(エビデンス)に基づき解説します。相手と自分、両方のメカニズムを知ることが「交わし方」の第一歩です。
理由1:威圧の背景にある「自己愛憤怒」(相手の心理)
威圧的な言動は、単なる「性格が悪い」だけではなく、心理的な背景があるかもしれません。日本教育心理学会の総説によれば、自己愛傾向を持つ人は、自分を偉大だとみなす態度(誇大性)を持つ一方で、その自己像が脅かされる(例:批判される)と、「自己愛憤怒」と呼ばれる激しい怒りで防衛的に反応することがあります。
理詰めで詰問したり、他責的に振る舞ったりする態度は、自らの脆弱な部分を守るための「防衛反応」である可能性が考えられます。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
誇大性・特権意識や「自己愛憤怒」が自己愛的特徴として示される。威圧・否定的な言動への対応では、反応の高ぶりを前提に事実の記述と境界の共有を軸に、対立のエスカレーションを避けるコミュニケーション設計が求められる。
理由2:我慢が「情緒的消耗」に繋がる(自分の心理)
威圧的な上司の言動を我慢し続けると、なぜ私たちは深く疲弊するのでしょうか。日本老年社会科学会の介護職員を対象とした研究では、バーンアウト(燃え尽き症候群)は「情緒的消耗感」が中核となるとされています。
上司との対人関係といった「仕事の要求度」が過大になると、この「情緒的消耗感」が高まります。これが続くと、やがては心身が疲弊し、仕事への意欲を失うバーンアウトという深刻な状態につながる危険性があります。
出典元の要点(要約)
日本老年社会科学会
介護職員におけるバーンアウトとワークエンゲイジメントの関係性—JD-Rモデルによる検討—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/42/3/42_188/_pdf/-char/ja
バーンアウトは三つの側面からなる症候群で、情緒的消耗が中核とされる。人間関係の不調や否定的態度は個人特性だけでなく症候群の表現であり、休息や支援導入の判断根拠となる。
理由3:「共感疲労」が冷静な対応を奪う
特に介護職は、利用者に対して日々「共感」を求められる専門職です。しかし、日本看護科学学会の概念分析によれば、この「共感」は不可欠な要素であると同時に、「共感疲労」というリスクも伴います。
長期的・連続的に共感的な関わりを続けることで疲弊しきっている状態では、上司からの威圧的な言動を冷静に「交わす」心理的な余裕が奪われてしまいます。つまり、介護職特有の疲れが、威圧的な言動への耐性を下げている可能性も考えられます。
出典元の要点(要約)
日本看護科学学会
看護師における共感疲労の概念分析
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans/43/0/43_43919/_pdf/-char/ja
概念分析は、長期的・連続的な共感的関わりが「離職などにつながる状態」を生むリスクを明確化。過剰に抱え込むタイプや“優しすぎる”対応には、境界設定・負担の見える化・休息と役割分担の仕組みが必要である。
このように、相手には「防衛的な攻撃性」という理由があり、自分には「情緒的消耗」や「共感疲労」という理由があることを理解することが、冷静な対処(交わし方)のためのスタートラインとなります。

よくある質問(FAQ):「交わし方」の具体的な技術
威圧的な上司を「交わす」ための、より具体的な技術について、多くの方が抱く疑問にお答えします。これらは我慢ではなく、あなた自身を守るための専門的なスキルです。
- Q相手が激高している時は、どう対応すればいいですか?
- A
相手が感情的になっているときに、事実や正論で対抗するのは逆効果になることがあります。
日本教育心理学会の総説では、自己愛傾向が強い人は「批判」や「自我脅威」を感じると、防衛的に「攻撃性(自己愛憤怒)」を高める可能性が示されています。
まずは相手の土俵(感情)に乗らず、相手の言葉を冷静に要約して返す(例:「〇〇という点で、お怒りなのですね」)など、相手の「自我脅威」を下げ、冷静さを取り戻す時間を作ることが先決です。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
誇大性・特権意識や「自己愛憤怒」が自己愛的特徴として示される。威圧・否定的な言動への対応では、反応の高ぶりを前提に事実の記述と境界の共有を軸に、対立のエスカレーションを避けるコミュニケーション設計が求められる。
- Q理不尽な要求をされた時の「上手な断り方(アサーション)」は?
- A
「アサーション」とは、相手を尊重しつつ、自分の意見も適切に主張する心理教育の手法です。
日本教育心理学会の研究でも、アサーション・トレーニングは「自己主張」と「他者尊重」を両立させ、「怒り表現」を適切にコントロールする効果が示されています。
例えば、「(相手の事情を尊重しつつ)現在〇〇の業務を抱えており、すぐには対応できません。(代替案として)〇時以降であれば対応可能です」というように、「できない事実」と「できる(または、したい)提案」をセットで伝えることが、角を立てない上手な断り方(交わし方)の基本です。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果(記事本文)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/67/4/67_317/_article/-char/ja/?utm_source=chatgpt.com
本文でも、自己主張と他者尊重の両立や視点取得・怒り表現への効果が明記される。話を聞かない/攻撃的な相手に対しても、相互尊重を保ちつつ目的を達成する対応スキルとして根拠づけられる。
- Q相手の心理を理解しようとすると、かえって疲れませんか?
- A
非常に重要なご質問です。相手の心理的背景(例:自己愛傾向)を理解しようとすることは、相手に「共感」したり、相手の言動を「許したり」することではありません。
日本教育心理学会の総説でも、こうした関わりは「拒否や批判の立場に偏らず、支援につなげる視点」で理解する枠組みが求められるとされています。
これは、相手を変えるためではなく、あなたが冷静さを保ち、相手の感情に巻き込まれないための「技術」です。相手の言動を客観視することで、あなたの「情緒的消耗」を防ぐことが最大の目的です。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
自己愛的問題のある相手への関与は難易度が高いが、拒否・批判に偏らず支援志向の仮説で理解する姿勢が求められる。現場では、感情の承認と課題の具体化、役割・境界の明確化を並行させる介入が適合する。
日本老年社会科学会
介護職員におけるバーンアウトとワークエンゲイジメントの関係性—JD-Rモデルによる検討—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/42/3/42_188/_pdf/-char/ja
バーンアウトは三つの側面からなる症候群で、情緒的消耗が中核とされる。人間関係の不調や否定的態度は個人特性だけでなく症候群の表現であり、休息や支援導入の判断根拠となる。
これらの技術は、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、知識として「知っておく」だけでも、威圧的な場面に遭遇したときのあなたの心の持ちようは大きく変わるはずです。
まとめ:自分の「情緒的消耗」を防ぐ技術を身につける
最後に、威圧的な上司から自分の心を守り、介護職として健康に働き続けるための要点を振り返ります。大切なのは、相手を変えようとすることではなく、あなた自身の心を守る「技術」を身につけることです。
相手の「感情」と「事実」を切り分ける
威圧的な言動に直面したとき、相手の「怒り」や「イライラ」を真正面から受け止める必要はありません。
日本教育心理学会の総説で示されたように、その態度は相手の「自己愛憤怒」など、内的・防衛的な問題である可能性があります。相手の「感情」と、指摘された「業務上の事実」を冷静に切り分け、客観視することが、あなたの心を守る第一歩です。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
教育心理学と実践活動―自己愛をめぐる実践研究と実証研究の交差
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/58/0/58_167/_pdf/-char/ja
誇大性・特権意識や「自己愛憤怒」が自己愛的特徴として示される。威圧・否定的な言動への対応では、反応の高ぶりを前提に事実の記述と境界の共有を軸に、対立のエスカレーションを避けるコミュニケーション設計が求められる。
アサーション(自他尊重の主張)は自分を守るスキル
我慢し続ける(受動的)ことも、感情的に言い返す(攻撃的)ことも、あなたの「情緒的消耗」につながります。
日本教育心理学会の研究で示された「アサーション(自他尊重の主張)」は、相手を尊重しつつ、自分の意見も適切に伝える技術です。これは、威圧的な相手の土俵に乗らず、冷静に「交わす」ための、あなた自身を守る実践的なスキルとなります。
出典元の要点(要約)
日本教育心理学会
大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/67/4/67_317/_pdf/-char/ja
アサーションは相手尊重を前提とした自己主張の心理教育である。攻撃的にならずに境界や要望を伝える標準手順(事実→感情→要望→結果)の導入に適する。
自分の「情緒的消耗」を防ぐことを最優先する
なぜ「交わす」技術が必要なのか。それは、あなたのバーンアウト(燃え尽き症候群)を防ぐためです。
日本老年社会科学会の研究で示されたように、対人関係のストレスは「情緒的消耗感」の中核となり、心身の健康を害する危険があります。「上手く交わす」技術は、この消耗を防ぎ、介護という専門職を長く続けるために不可欠な自己防衛術です。
出典元の要点(要約)
日本老年社会科学会
介護職員におけるバーンアウトとワークエンゲイジメントの関係性—JD-Rモデルによる検討—
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/42/3/42_188/_pdf/-char/ja
バーンアウトは三つの側面からなる症候群で、情緒的消耗が中核とされる。人間関係の不調や否定的態度は個人特性だけでなく症候群の表現であり、休息や支援導入の判断根拠となる。
相手の言動に振り回され、あなたの心が疲弊してしまう前に、まずは「相手の心理を理解する」「アサーションで伝える」という技術があることを知っておいてください。
関連記事
更新履歴
- 2025年11月3日:新規投稿