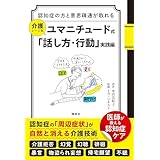「自分はリーダーとして頑張っているつもりなのに、なぜかスタッフが定着しない…」 「新人を指導しても、すぐに辞めてしまう…」
もし、あなたがそうした悩みを抱えているなら、それはあなたのリーダーとしての熱意や経験が足りないからではないかもしれません。この記事では、公的なデータや学術的なエビデンスに基づき、スタッフが離職する本当の理由と、それを防ぐための具体的な技術を解説します。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます
この記事を知っていると
- スタッフが離職する「本当の理由」が、エビデンス(根拠)に基づいてわかります。
- スタッフの「沈黙」や「ミスの隠蔽」がなぜ起こるのか、そのメカニズムを理解できます。
- 「慕われるリーダー」が実践している、離職を防ぐための具体的な「聞く姿勢」がわかります。
結論:スタッフの離職は、リーダーの「聞く技術」で止められる

スタッフが次々と辞めていく現実に、「リーダーとして何が足りないのだろう」と悩んでいませんか。その問題は、あなたの熱意や経験不足ではなく、具体的な「技術」で解決できるかもしれません。エビデンス(根拠)は、リーダーの「聞く技術」が職場の未来を大きく左右することを示しています。
「慕われるリーダー」とは「聞ける」リーダー
介護現場で「慕われるリーダー」とは、特別なカリスマ性を持つ人とは限りません。ある研究では、管理監督者(リーダー)が「積極的傾聴法」の研修を受けたところ、部下が感じる「上司の支援」の度合いが有意に上昇したことが示されました。リーダーが部下の相談に耳を傾ける姿勢こそが、スタッフの信頼を育みます。
出典元の要点(要約)
日本産業衛生学会(産業衛生学雑誌)
積極的傾聴法を取り入れた管理監督者研修による効果(2008)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/50/4/50_E7008/_article/-char/ja
電子機器製造業事業場の管理職を対象に「積極的傾聴法」を含む研修を実施し、従業員側の評価で「上司の支援」が研修後に有意上昇。本文は、管理職の相談対応充実を通じて「上司の支援」が強化された可能性を示す。上司の傾聴が客観指標(BJSQの上司支援因子)を改善しうることを示す一次データであり、「聞かない上司」の不利益(支援不足・相談停滞)と表裏の関係で説明可能。
「聞く姿勢」が職場にもたらす具体的な利益
リーダーが「聞く姿勢」を持つことは、単に職場の雰囲気を良くするだけではありません。世界保健機関(WHO)のガイドラインでは、「安全で健全かつ包摂的な職場環境は」、スタッフのパフォーマンスや生産性を向上させ、「同僚間の対立を最小限に抑える」と明記されています。リーダーが聞くことで職場環境が改善すれば、離職率の低下だけでなく、チーム全体の生産性向上という具体的な利益につながります。
出典元の要点(要約)
世界保健機関(WHO)日本語版(厚生労働省掲載)
職場のメンタルヘルス対策ガイドライン 日本語版(原著2022)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
序文は「安全で健全かつ包摂的な職場環境は」「アブセンティイーズムを減らし、仕事のパフォーマンス・生産性を向上」させ、「同僚間の対立を最小限に抑える」と記載する。上司の傾聴欠如で包摂性が欠けると、これらの利点が得られず、欠勤・生産性・対立面で不利益が生じうる。
スタッフのメンタルを守ることはリーダーの責務
スタッフが安心して働き続けるためには、心の健康が不可欠です。世界保健機関(WHO)は、労働者が「過度のストレスや心の健康問題のリスクにさらされないようにする」ことは雇用主や政府の責務であると示しています。さらに、そのための具体的な推奨事項として「管理監督者のトレーニングに関する推奨事項」を挙げています。スタッフの話に耳を傾け、メンタルヘルスを守ることは、現代の介護リーダーに求められる重要な責務の一つです。
出典元の要点(要約)
世界保健機関(WHO)日本語版(厚生労働省掲載)
職場のメンタルヘルス対策ガイドライン 日本語版(原著2022)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
目次に「管理監督者のトレーニングに関する推奨事項」「労働者のトレーニングに関する推奨事項」「組織介入に関する推奨事項」が並び、管理監督者の関与が制度的に位置づけられている。上司が聞かない環境は、これら推奨の実施を妨げ、メンタルヘルス上の不利益を招く可能性がある。
世界保健機関(WHO)日本語版(厚生労働省掲載)
職場のメンタルヘルス対策ガイドライン 日本語版(原著2022)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
序文は、労働者の権利として「職場で達成可能な最高水準のメンタルヘルス」を掲げ、政府と雇用主に「過度のストレスや心の健康問題のリスクにさらされないようにする」責務を示す。上司の傾聴欠如がストレスやリスクを増す場合、権利と責務に反し不利益が生じる。
スタッフの離職を防ぐ鍵は、リーダーであるあなたの「聞く技術」にあります。それは組織の生産性を上げ、スタッフのメンタルヘルスを守る具体的なスキルなのです。続くセクションでは、もしリーダーが「聞かない」場合に、現場でどのような危機が起こるのかを具体的に見ていきます。
あなたの職場は大丈夫?「話を聞かないリーダー」が引き起こす3つの危機

「忙しいから」とスタッフの声を後回しにしていませんか。リーダーが「聞かない」姿勢は、現場のスタッフに「沈黙」を選ばせ、やがて深刻な事態につながります。あなたの職場にも、以下のような兆候はないでしょうか。
事例1:「どうせ言っても無駄」— スタッフの「沈黙」と学習の停止
スタッフが改善提案や懸念事項を口にしなくなるのは、意欲の問題ではないかもしれません。産業医学振興財団の総説では、「心理的安全性が低いと、組織としての学習行動が減少し」、「ミスの報告を含めた労働者の発言が減り、沈黙が増える。」と説明されています。リーダーが支持的でない、あるいは意見を表明しにくい職場では、スタッフは「沈黙」を選びます。この「発言行動」の欠如は、組織が改善の機会を失うという重大な不利益につながります。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
本総説は、心理的安全性が低い職場では「組織としての学習行動が減少し」「ミスの報告を含めた労働者の発言が減り、沈黙が増える。」と説明し、産業保健の観点から「心理的安全性の高い職場風土づくり」を支える重要性を述べる。上司が話を聞かず発言を抑える状況は、学習と報告を阻害し、沈黙を増やす不利益につながる。
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
資源保存理論の整理で、発言は「資源…を獲得するための潜在的な手段」と位置づけられ、「職場内の発言や知識の共有が資源となり」「新たな資源獲得のための学びにつながる」。上司が聞かず発言を抑えると、資源獲得と学びの機会が失われる不利益が生じる。
事例2:「報告したら怒られる」— ミスの隠蔽と介護事故リスク
介護・医療現場において「コミュニケーション不全はエラーの主な原因となる」と指摘されています。リーダーが聞く姿勢を持たず、ミスを報告しにくい環境では、スタッフは「上司に報告する」ことに安全を感じられません。厚生労働省は介護施設に対し、事故発生時は「速やかに市町村、入所者の家族等に連絡」し、分析・活用することを求めています。報告が遅れる職場は、利用者の安全を直接脅かすリスクを抱えています。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
介入研究の整理では「コミュニケーション不全はエラーの主な原因」とされ、懸念を「上司と共有することにより、…学びにつなげる」。またアウトカムに「心理的安全性や発言行動(voice/speaking up behavior)」が用いられる。上司が聞かず共有が滞ると、エラー原因が温存され、安全と学びに不利益が生じる。
厚生労働省 老健局
介護保険最新情報 Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/1202092706494/ksvol.1332.pdf?from=rss
通知は事故時の連絡義務「速やかに市町村、入所者の家族等に連絡」、事故情報の「収集・分析・公表」、第1報の「事故発生後速やかに、遅くとも5日以内」を定める。上司が現場の声を聞かず共有が遅れると、報告と分析の枠組みに適合せず、安全対策に不利益が生じる。
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
尺度項目として「If I saw a colleague making a mistake, I would feel safe speaking up to my team leader.」が示され、「上司に報告する」ことが「患者の安全を守ることが可能」と説明される。上司が聞かない状態は、報告の安全感を損ない、患者安全の不利益につながる。
事例3:「誰も助けてくれない」— 孤立感と離職の決意
スタッフの離職は、突然決まるわけではありません。理学療法科学学会の研究では、「心理的安全性と働く意欲およびストレスに相関関係」が認められました。また、産業医学振興財団の総説では、「職場での信頼を基盤とした高い心理的安全性」が「離職率を低下させるとの指摘がある」と整理されています。リーダーが話を聞かず、スタッフが孤立感を深める職場は、離職の決断を後押ししてしまいます。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
社会的アイデンティティ理論の視点から「高い心理的安全性は…離職率を低下させるとの指摘がある」。また「職場のインクルーシブネス」が「心理的安全性を促進」する。上司が話を聞かず包摂性が損なわれると、心理的安全性が下がり、離職抑制の効果が得られないという組織の不利益が生じうる。
理学療法科学学会(理学療法科学 / J-STAGE)
若手理学療法士の心理的安全性と働く意欲に関する基礎研究(2025, 混合研究)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/52/3/52_25-12599/_html/-char/ja
若手理学療法士116名の量的+29名の質的調査で、「心理的安全性と働く意欲およびストレスに相関関係」を認め、インタビューでは「他者との関わり」「共感」などが心理的安全性に影響と抽出。上司の傾聴不足は「他者との関わり」「共感」を損ない、心理的安全性の低下→意欲低下・ストレス増加という不利益ルートを日本語一次資料で裏づける。
これらの事例は、決して特別なことではありません。スタッフの「沈黙」や「ミス報告の遅れ」は、リーダーであるあなたの「聞く姿勢」によって防げる可能性があります。次のセクションでは、なぜ「聞かない」ことが離職に直結するのかを、さらに詳しく見ていきます。
なぜリーダーが「聞かない」だけで、スタッフは辞めてしまうのか?

「聞く」という行為が、なぜこれほどまでにスタッフの定着と深く結びついているのでしょうか。その背景には、「安心感」「信頼関係」「安全」という、介護現場で働く上で欠かせない3つの要素があります。エビデンスに基づき、その構造を解説します。
理由1:「心理的安全性」が担保されないから
スタッフが辞めてしまう職場は、「心理的安全性」が低いという共通点があります。産業医学振興財団の総説では、「心理的安全性」を「職場で自分の立場に悪影響が及ぶおそれなく対人リスク行動に出られる心の状態」と定義しています。リーダーが話を聞かず、意見を表明しにくい環境は、まさにこの心理的安全性が損なわれている状態です。その結果、「ミスの報告を含めた労働者の発言が減り、沈黙が増える」ことにつながります。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
本文は「心理的安全性は『職場で自分の立場に悪影響が及ぶおそれなく対人リスク行動に出られる心の状態』」と定義し、「仕事に関する自分の意見を表明する」前提を明確化。高い心理的安全性は「労働者の自由な言動を可能にする」点を強調する。
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
抄録は「心理的安全性が低いと、組織としての学習行動が減少し」「ミスの報告を含めた労働者の発言が減り、沈黙が増える。」と明記。産業保健スタッフが「心理的安全性の高い職場風土づくりを支援」する役割を示し、発言促進とヒヤリ・ミス共有の重要性を示す。
理由2:「知覚された上司の支援(PSS)」が得られないから
スタッフは、リーダーの行動を敏感に見ています。経営行動科学学会の研究ノートでは、「知覚された上司の支援(PSS)」という概念が紹介されています。これは、スタッフが「上司は自分を支援してくれている」と感じる度合いのことです。この「PSS が POS の経時的な変化に正の有意な相関」(POS=組織全体への信頼感)があることが示されています。リーダーの傾聴は、この「上司の支援」を強化する有効な手段であり、これが欠如すると、スタッフの組織への信頼が失われていきます。
出典元の要点(要約)
日本産業衛生学会(産業衛生学雑誌)
積極的傾聴法を取り入れた管理監督者研修による効果(2008)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/50/4/50_E7008/_article/-char/ja
電子機器製造業事業場の管理職を対象に「積極的傾聴法」を含む研修を実施し、従業員側の評価で「上司の支援」が研修後に有意上昇。本文は、管理職の相談対応充実を通じて「上司の支援」が強化された可能性を示す。上司の傾聴が客観指標(BJSQの上司支援因子)を改善しうることを示す一次データであり、「聞かない上司」の不利益(支援不足・相談停滞)と表裏の関係で説明可能。
理由3:利用者の「安全」が守れない職場だと感じるから
介護スタッフは、利用者の安全を守ることに強い責任感を持っています。公益財団法人 日本医療機能評価機構の年報では、医療安全文化が醸成されると「コミュニケーションエラーが減り、医療の質が高まる」と明記されています。また、厚生労働省は介護施設に対し、事故情報の「収集・分析・活用」を求めています。リーダーが聞く耳を持たず、報告や情報共有が滞る職場は「安全でない職場」です。スタッフは、利用者の安全を守れないことへのストレスから、離職を選択することがあります。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構
医療安全文化調査 2022年度 年報(抜粋版)
本年報は「医療安全文化」を「…患者さんの安全を最優先に考え…それを可能にする組織のあり方」と定義し、醸成により「医療チームの能力が高まり、コミュニケーションエラーが減り、医療の質が高まる」と明記する。調査は「医療安全文化調査票 (HSOPS)」を用い、日本語化し定量測定する枠組みを提示。上司が現場の声を受け止めない状況は、コミュニケーションエラーの増大や安全文化の低下という具体的不利益に直結するエビデンスを示す。
厚生労働省 老健局
介護保険最新情報 Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/1202092706494/ksvol.1332.pdf?from=rss
報告方法は「原則、電子メール等の電磁的方法」とし、「様式の統一化」により「事故情報の収集・分析・活用」を進める。現場の報告を上司が受け止めないと、この標準化の意図に反し、分析・活用が滞る不利益が生じ、安全と再発防止に影響する。
このように、「聞かない」という姿勢は、スタッフの安心感、信頼感、そして安全への責任感までも損なってしまいます。次のセクションでは、リーダーが抱きがちな疑問について、エビデンスを基に回答します。
よくあるご質問(FAQ)
リーダーとして現場に立っていると、様々な疑問やジレンマに直面します。「忙しくて聞けない」「厳しさも必要だ」といった現実的な悩みについて、エビデンス(根拠)を基に回答します。
- Q忙しくて、スタッフの話をゆっくり聞く「時間」がありません。
- A
多くのリーダーが直面する課題です。しかし、世界保健機関(WHO)のガイドラインでは、メンタルヘルス対策として「管理監督者のトレーニング」や「組織介入」が推奨事項として挙げられています。話を聞く時間を確保することは、リーダー個人の努力目標であると同時に、組織として取り組むべき重要な責務です。
出典元の要点(要約)
世界保健機関(WHO)日本語版(厚生労働省掲載)
職場のメンタルヘルス対策ガイドライン 日本語版(原著2022)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
目次に「管理監督者のトレーニングに関する推奨事項」「労働者のトレーニングに関する推奨事項」「組織介入に関する推奨事項」が並び、管理監督者の関与が制度的に位置づけられている。上司が聞かない環境は、これら推奨の実施を妨げ、メンタルヘルス上の不利益を招く可能性がある。
世界保健機関(WHO)日本語版(厚生労働省掲載)
職場のメンタルヘルス対策ガイドライン 日本語版(原著2022)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001258077.pdf
構成上「推奨事項」および「組織介入に関する推奨事項」が示され、さらに「本ガイドラインの普及と更新」が記される。上司の傾聴と対話促進は推奨実装の一部であり、実施しない場合、普及と更新の意図に反し、メンタルヘルスの改善機会を逃す不利益が生じる。
- Q「聞く」だけで、本当に離職率が下がるのですか?
- A
はい、エビデンスによって強く示唆されます。産業医学振興財団の総説では、「職場での信頼を基盤とした高い心理的安全性は…離職率を低下させるとの指摘がある」と整理されています。また、理学療法科学学会の研究でも、若手理学療法士を対象に「心理的安全性と働く意欲およびストレスに相関関係」が認められました。リーダーの傾聴は、これらの基盤となります。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
社会的アイデンティティ理論の視点から「高い心理的安全性は…離職率を低下させるとの指摘がある」。また「職場のインクルーシブネス」が「心理的安全性を促進」する。上司が話を聞かず包摂性が損なわれると、心理的安全性が下がり、離職抑制の効果が得られないという組織の不利益が生じうる。
理学療法科学学会(理学療法科学 / J-STAGE)
若手理学療法士の心理的安全性と働く意欲に関する基礎研究(2025, 混合研究)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/52/3/52_25-12599/_html/-char/ja
若手理学療法士116名の量的+29名の質的調査で、「心理的安全性と働く意欲およびストレスに相関関係」を認め、インタビューでは「他者との関わり」「共感」などが心理的安全性に影響と抽出。上司の傾聴不足は「他者との関わり」「共感」を損ない、心理的安全性の低下→意欲低下・ストレス増加という不利益ルートを日本語一次資料で裏づける。
- Qスタッフを指導するために、厳しく叱ることも必要ではないですか?
- A
指導は必要ですが、その方法が重要です。産業医学振興財団の総説では、「上司が支持的」であることや、リーダーと共に振り返る「デブリーフィング」、「発言しやすい雰囲気づくり」が心理的安全性を向上させると整理されています。威圧的な態度は「ミスの報告」を減少させ、安全なケアを妨げる不利益につながる可能性があります。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
介入研究レビューでは、リーダーと行う「デブリーフィング」や「発言しやすい雰囲気づくり」が「心理的安全性を向上」させると整理される。これらは上司の関わりが前提であり、上司が聞かない状態はこうした有効介入を阻害し、心理的安全性の改善を妨げる不利益につながる。
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
文化的背景に関する記述では、「上司が支持的で労働者の心理的安全性が高いと、忖度のない発言ができる」。さらに「階層的構造を有する職場」では「発言行動(voice behavior, speaking up behavior)」に影響が及ぶとされる。支持的でない上司の下では、発言が抑制され、改善機会を逃す不利益が生じる。
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
本総説は、心理的安全性が低い職場では「組織としての学習行動が減少し」「ミスの報告を含めた労働者の発言が減り、沈黙が増える。」と説明し、産業保健の観点から「心理的安全性の高い職場風土づくり」を支える重要性を述べる。上司が話を聞かず発言を抑える状況は、学習と報告を阻害し、沈黙を増やす不利益につながる。
リーダーの疑問は、職場改善の第一歩です。「聞く」という技術は、忙しい現場の課題を解決し、スタッフと組織を守る力になります。次のまとめでは、改めてこの記事の要点を振り返ります。
まとめ:「聞くリーダー」こそが、介護現場の離職を止める
スタッフが辞めていく背景には、給与や待遇だけでなく、「リーダーが話を聞いてくれない」というコミュニケーションの問題が深く関わっています。この記事で見てきたように、「聞く」という行為は単なる精神論ではなく、職場の離職を防ぎ、安全性を高めるための具体的な「技術」です。
「心理的安全性」が離職を防ぐ土台となる
スタッフが安心して働き続けるためには、「何を言っても罰せられない」という安心感が不可欠です。産業医学振興財団の総説では、「職場での信頼を基盤とした高い心理的安全性」が「離職率を低下させるとの指摘がある」と整理されています。リーダーが「聞く」ことを通じてこの安全な土壌を作ることが、離職防止の第一歩となります。
出典元の要点(要約)
産業医学振興財団(産業医学レビュー)
心理的安全性と産業保健における意義(Vol.38 No.1, 2025)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/38/1/38_53/_pdf/-char/en
社会的アイデンティティ理論の視点から「高い心理的安全性は…離職率を低下させるとの指摘がある」。また「職場のインクルーシブネス」が「心理的安全性を促進」する。上司が話を聞かず包摂性が損なわれると、心理的安全性が下がり、離職抑制の効果が得られないという組織の不利益が生じうる。
リーダーの「聞く姿勢」が信頼を生む
スタッフは、リーダーが自分たちを支援してくれているかを敏感に感じ取っています。ある研究では、管理監督者が「積極的傾聴法」の研修を受けることで、部下が感じる「上司の支援」の度合いが有意に上昇したことが示されました。この「知覚された上司の支援」こそが、スタッフの組織への信頼感を育み、定着につながります。
出典元の要点(要約)
日本産業衛生学会(産業衛生学雑誌)
積極的傾聴法を取り入れた管理監督者研修による効果(2008)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/50/4/50_E7008/_article/-char/ja
電子機器製造業事業場の管理職を対象に「積極的傾聴法」を含む研修を実施し、従業員側の評価で「上司の支援」が研修後に有意上昇。本文は、管理職の相談対応充実を通じて「上司の支援」が強化された可能性を示す。上司の傾聴が客観指標(BJSQの上司支援因子)を改善しうることを示す一次データであり、「聞かない上司」の不利益(支援不足・相談停滞)と表裏の関係で説明可能。
「聞くこと」は利用者の安全とケアの質に直結する
リーダーがスタッフの声を聞くことは、人間関係のためだけではありません。公益財団法人 日本医療機能評価機構の年報では、安全文化が醸成されると「コミュニケーションエラーが減り、医療の質が高まる」と明記されています。スタッフからのヒヤリハットや懸念事項を傾聴することは、介護事故を未然に防ぎ、利用者の安全を守るというリーダーの重大な責務の遂行に直結します。
出典元の要点(要約)
公益財団法人 日本医療機能評価機構
医療安全文化調査 2022年度 年報(抜粋版)
本年報は「医療安全文化」を「…患者さんの安全を最優先に考え…それを可能にする組織のあり方」と定義し、醸成により「医療チームの能力が高まり、コミュニケーションエラーが減り、医療の質が高まる」と明記する。調査は「医療安全文化調査票 (HSOPS)」を用い、日本語化し定量測定する枠組みを提示。上司が現場の声を受け止めない状況は、コミュニケーションエラーの増大や安全文化の低下という具体的不利益に直結するエビデンスを示す。
「慕われるリーダー」になるための第一歩は、特別なカリスマ性ではありません。まずはスタッフの話を遮らず、最後まで耳を傾けることから始めてみてください。その小さな変化が、職場の空気と未来を変えるはずです。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月20日:新規投稿