夜勤中、特に深夜の時間帯に襲ってくる強烈な眠気。「休憩中に少しでも寝たいけど、かえってだるくなりそう」「仮眠はサボっているようで気が引ける…」と感じたことはありませんか? しかし、夜勤中の仮眠は「サボり」ではなく、安全な介護を提供するためのプロフェッショナルな技術(テクニック)です。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます。
この記事の信頼性と目的
この記事は、個人の感想や憶測ではなく、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」や日本看護協会のガイドラインなど、権威ある公的な資料のみを根拠としています。睡眠不足は「事故等の重大な結果を招く場合もある」と警告されており、この記事は科学的根拠に基づき、夜勤中の仮眠がなぜ重要なのか、そしてどうすれば上手に仮眠がとれるのかを解説します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
本ガイドは「睡眠は…健康増進・維持に不可欠な休養活動である。」とし、「睡眠不足は…事故等の重大な結果を招く場合もある。」と警告する。さらに、睡眠の問題が慢性化すると生活習慣病に関連し「死亡率の上昇…に関与することが明らかとなっている。」と示す。介護職の交代勤務における睡眠課題の理解と、日々の健康管理の基盤として重要な位置づけである。
この記事を知っていると
夜勤中の仮眠が「仕事の効率」と「安全」のために不可欠であることが分かり、限られた休憩時間で質高く仮眠するための具体的なテクニックを知ることができます。
「仮眠」を正しく理解することは、あなた自身と利用者の安全を守る第一歩です。まずは、なぜ夜勤中の仮眠が「サボり」ではなく、業務上「必要」なのか、その明確な理由から詳しく見ていきましょう。
結論:「夜勤中の休憩」を最大活用する4つのコツ
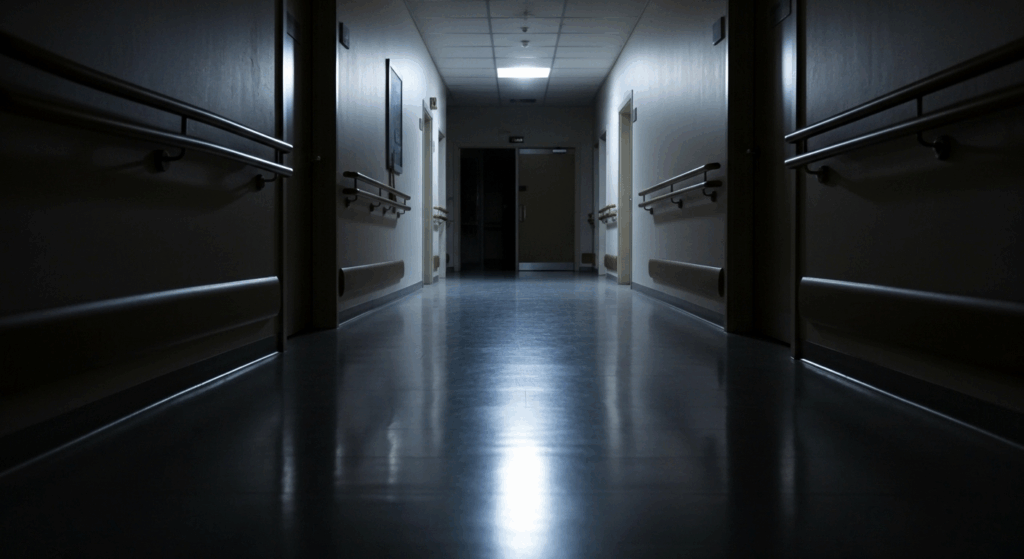
夜勤中の仮眠は「サボり」ではなく、安全と効率のための「専門技術」です。公的な資料で推奨されている、限られた休憩時間を最大活用するための「上手な仮眠のコツ」を4つ紹介します。
コツ1:【最重要】仮眠の「時間帯」と「長さ」を守る
仮眠の効果は、そのタイミングと長さで決まります。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、夜勤中の眠気対策として、「0~4時…20~50分間の仮眠」が仕事の効率を改善する場合があると具体的に示されています。この時間帯は、体内時計のリズムで最も眠気が強くなる時間であり、このタイミングで短く仮眠をとることが最も効果的です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(仮眠・カフェイン)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
業務中の眠気対策として「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し「仕事の効率が向上する場合があります。」とする。特に夜勤帯では「0~4時…20~50分間の仮眠…改善」と具体的に示され、短時間仮眠の有効活用が推奨される。
コツ2:「長すぎる仮眠(睡眠慣性)」を避ける
「どうせ寝るなら休憩時間いっぱいまで寝たい」と思うかもしれませんが、長すぎる仮眠は逆効果になることがあります。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」は、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じる可能性を示しています。「睡眠慣性(すいみんかんせい)」とは、深い睡眠から無理やり起きた直後に生じる、強い眠気や疲労感、頭がボーッとする状態のことです。これを避けるためにも、仮眠は50分以内(長くとも深い睡眠に入る前)に留めるのが賢明です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(睡眠慣性への注意)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
仮眠の取り方には留意点があり、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、「覚醒感の強いねむけや疲」に繋がる可能性がある。光環境との組み合わせでは「体内時計を調整する作用」を踏まえ、仮眠後の照明や帰路の光曝露を適切化することが重要となる。
コツ3:「質」を高める環境を確保する
たとえ20分でも、仮眠の質を高めるためには環境が重要です。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、仮眠のための環境整備として、「遮光、防音、温度・湿度、換気などに配慮」し、「ベッドやリクライニングチェアなどを設置」することが推奨されています。職場で完璧な環境を求めるのは難しくても、アイマスクや耳栓を持参するなど、できるだけ「暗く・静か」な環境を作る工夫が質を高めます。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策(作業環境・作業管理)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
夜勤時の作業環境では「勤務場所の照明を高照度」とし、作業管理では「適切な休養時間や静かで快適な休養場所」の確保を推奨。「勤務間隔の短時間化…は避ける。」と設計原則を示す。
コツ4:「カフェイン」と組み合わせる(カフェインナップ)
仮眠の効果をさらに高める方法として、カフェインの活用があります。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、眠気対策として「仮眠やカフェイン摂取等」が仕事の効率を改善する場合があると示されています。これは「カフェインナップ」と呼ばれるテクニックで、仮眠をとる「直前」にコーヒーなどのカフェインを摂取します。カフェインが効き始める(約20~30分後)と仮眠から目覚めるタイミングが重なり、スッキリと覚醒しやすくなります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(仮眠・カフェイン)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
業務中の眠気対策として「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し「仕事の効率が向上する場合があります。」とする。特に夜勤帯では「0~4時…20~50分間の仮眠…改善」と具体的に示され、短時間仮眠の有効活用が推奨される。
夜勤中の仮眠は、あなた自身と利用者の安全を守るための重要な業務スキルです。まずは「20分アラームをセットする」「アイマスクを持参する」など、一つでもできることから試してみてください。
よくある事例:夜勤仮眠の「よくある失敗」

夜勤中の仮眠が重要だと分かっていても、現実にはうまくいかないことも多いものです。ここでは、多くの介護士さんが経験する「よくある失敗」の事例を紹介します。
事例1:「長すぎた仮眠」で起きた後がもっと辛い
休憩時間いっぱいに寝ようと、1時間半や2時間の仮眠をとった結果、起きた後に強烈な眠気や疲労感、頭がボーッとする状態に襲われるケースです。これは「睡眠慣性(すいみんかんせい)」と呼ばれる現象で、深い睡眠に入りすぎたために起こります。厚生労働省の資料でも、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、かえって「覚醒感の強いねむけや疲」に繋がる可能性があると指摘されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(睡眠慣性への注意)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
仮眠の取り方には留意点があり、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、「覚醒感の強いねむけや疲」に繋がる可能性がある。光環境との組み合わせでは「体内時計を調整する作用」を踏まえ、仮眠後の照明や帰路の光曝露を適切化することが重要となる。
事例2:「眠れない」まま休憩時間が終わる
「寝なければ」と焦るばかりでリラックスできず、緊張で目が冴えてしまうケースです。また、仮眠室がなかったり、休憩室が明るく騒がしかったりして、眠れる環境にない場合も同様です。労働者健康安全機構の資料では、「適切な休養時間や静かで快適な休養場所」の確保が推奨されています。環境が整っていないと、貴重な休憩時間を「眠ろうと努力しただけ」で終えてしまい、余計に疲労が溜まってしまいます。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策(作業環境・作業管理)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
夜勤時の作業環境では「勤務場所の照明を高照度」とし、作業管理では「適切な休養時間や静かで快適な休養場所」の確保を推奨。「勤務間隔の短時間化…は避ける。」と設計原則を示す。
事例3:「睡魔」が原因でヒヤリ・ハット
仮眠をとらずに頑張り続けた結果、明け方の最も集中力が必要な時間帯に、利用者の安全に関わる重大なミスを起こしそうになった(ヒヤリ・ハット)ケースです。厚生労働省の資料では、睡眠不足が「事故等の重大な結果を招く場合もある」と警告されています。また、労働者健康安全機構の資料でも「不眠や不十分な疲労回復は、事故やミス…安全面への影響」があると指摘されており、仮眠を怠ることは介護の質と安全に直結するリスクとなります。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策 ~健康と生活への影響と管理のポイント~(産業保健21 第98号)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
交替勤務は「昼夜逆転のある不規則な就労形態」により「睡眠の質の問題と疲労回復の困難さ」が相乗し、影響が広範となる。「不眠や不十分な疲労回復は、事故やミス…安全面への影響」とされ、安全配慮の観点からも睡眠対策が不可欠である。
これらの失敗は、個人の能力の問題ではなく、「仮眠の正しい方法」を知らないことが原因で起こります。では次に、なぜ仮眠が「サボり」ではなく「業務上必要」なのか、その明確な理由を見ていきましょう。
なぜ夜勤中の仮眠は「サボり」ではなく「必要」なのか
夜勤中の仮眠に対して、「忙しいのに休んでいられない」「サボっているようで罪悪感がある」と感じる介護士さんは少なくありません。しかし、公的な資料では、仮眠は「任意」ではなく、安全な介護業務を遂行するための「必要な対策」として明確に位置づけられています。
理由1:仮眠は「仕事の効率と安全性」を高めるため
最も重要な理由は、仮眠が業務パフォーマンスに直結するからです。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し、「仕事の効率が向上する場合があります。」と明記されています。つまり、短時間の仮眠は、脳の疲労を回復させ、その後の業務(記録、巡視、介助)の効率と正確性を高めるための合理的な手段です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(仮眠・カフェイン)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
業務中の眠気対策として「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し「仕事の効率が向上する場合があります。」とする。特に夜勤帯では「0~4時…20~50分間の仮眠…改善」と具体的に示され、短時間仮眠の有効活用が推奨される。
理由2:睡眠不足による「事故・ミス」を防ぐため
介護現場での事故やミスは、利用者の生命と安全に直結します。労働者健康安全機構の資料では、「不眠や不十分な疲労回復は、事故やミス…安全面への影響」があると明確に指摘されています。特に夜勤帯は、心身の疲労が蓄積し、注意力が散漫になりがちです。仮眠をとることは、この最も危険な時間帯のヒヤリ・ハットや介護事故を未然に防ぐための、重要なリスクマネジメントです。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策 ~健康と生活への影響と管理のポイント~(産業保健21 第98号)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
交替勤務は「昼夜逆転のある不規則な就労形態」により「睡眠の質の問題と疲労回復の困難さ」が相乗し、影響が広範となる。「不眠や不十分な疲労回復は、事故やミス…安全面への影響」とされ、安全配慮の観点からも睡眠対策が不可欠である。
理由3:自身の健康を守る「責務」のため
利用者に質の高いケアを提供するためには、まず介護士さん自身が健康でなければなりません。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、看護者(介護職にも通じる)の基本理念として、「看護者自身の心身の健康の保持増進に努める」ことが責務として掲げられています。夜勤という過酷な勤務の中で、仮眠をとって自身の健康を維持することは、プロフェッショナルとしての責任を果たすことにもつながります。
出典元の要点(要約)
日本看護協会
看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(基本理念)
https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
本ガイドラインは、倫理綱領に基づき「看護者自身の心身の健康の保持増進に努める」とし、組織として「労働時間管理…安全衛生マネジメントに取り組むことが必要」と示す。負担軽減に向け「夜勤・交代制勤務の負担を軽減…対策が欠かせない」と明確化。
よくある質問(FAQ)

夜勤中の仮眠に関して、現場でよく聞かれる疑問に答えます。
- Q仮眠室がなく、休憩室がうるさくて眠れません
- A
本来、事業者は安全配慮の観点から「適切な休養時間や静かで快適な休養場所」を確保することが望ましいとされています。労働者健康安全機構の資料でも、作業管理の一環としてこの点が推奨されています。とはいえ、すぐに環境が整わない場合は、アイマスク(光を遮断するため)や耳栓(音を遮断するため)を持参するなど、個人でできる対策を講じて、少しでも仮眠の質を高める工夫をすることが現実的な第一歩となります。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策(作業環境・作業管理)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
夜勤時の作業環境では「勤務場所の照明を高照度」とし、作業管理では「適切な休養時間や静かで快適な休養場所」の確保を推奨。「勤務間隔の短時間化…は避ける。」と設計原則を示す。
- Q「20分」では寝た気がしません
- A
夜勤中の短時間仮眠の目的は、熟睡することではなく、深い睡眠に入る「前」に脳を休ませ、疲労感をリセットすることにあります。厚生労働省の資料では、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、起きた後に「覚醒感の強いねむけや疲」に繋がる可能性があると指摘されています。推奨される「20~50分」という時間は、この睡眠慣性を防ぎ、スッキリと業務に戻るために最も効率的な長さとして示されているのです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(睡眠慣性への注意)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
仮眠の取り方には留意点があり、「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、「覚醒感の強いねむけや疲」に繋がる可能性がある。光環境との組み合わせでは「体内時計を調整する作用」を踏まえ、仮眠後の照明や帰路の光曝露を適切化することが重要となる。
- Q忙しくて仮眠(休憩)自体が取れません
- A
「忙しくて休めない」という状況は、安全面から見て非常に危険な状態です。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、組織が講じるべき施策として「休憩と仮眠のための時間の確保」が明示されています。これは、仮眠が個人の任意で行うものではなく、組織として安全衛生マネジメントの一環として取り組むべき課題であることを示しています。
出典元の要点(要約)
日本看護協会
看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(組織的取り組み)
https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
組織施策として「休憩と仮眠のための時間の確保」を明示し、導入時は「現状分析…拘束時間、仮眠時間、休憩・仮眠の確保状況」を把握。「PDCAサイクル」により勤務編成を継続改善する枠組みを提示する。
まとめ
夜勤中の仮眠は、「サボり」や「怠慢」ではなく、あなた自身と利用者の安全を守り、介護の質を維持するために不可欠なプロフェッショナルな業務スキルです。
本記事のまとめ
この記事では、厚生労働省などの公的な資料に基づき、夜勤中の仮眠が「仕事の効率」と「安全」のために必要であることを解説しました。睡眠不足は「作業効率の低下…事故等の重大な結果」に繋がる可能性があり、放置すべきではありません。結論で紹介した「4つのコツ」(時間帯、長さ、環境、カフェイン)は、休憩時間を最大活用し、安全に業務を遂行するための科学的なテクニックです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(事故・安全)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
ガイドは睡眠不足が「作業効率の低下…事故等の重大な結果」に繋がるとし、予防の目的は「生活の質を高めていくことは極めて重要」とする。実装に向け「本ガイド…ツールとしての活用性」を打ち出す。
今日からできる第一歩
夜勤中の仮眠を実践するために、まずは「仮眠は安全のための仕事のうち」と意識を変えることから始めてみてください。そして次の夜勤では、休憩時間に「20分後」のアラームをセットし、アイマスクや耳栓を使って、短時間でも脳を休ませることを試してみましょう。
慢性的な眠気が続く場合は
もし、これらのセルフケアを試しても日中や勤務中の眠気が改善しない場合は、一人で抱え込まないでください。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」は、「眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。」と強く呼びかけています。交代勤務睡眠障害(SWSD)などの可能性もあるため、「早めに専門家に相談することが重要」です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(受診・相談)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第12条は支援活用を促し、「早めに専門家に相談することが重要」と明示。薬物療法の安全面では「薬とお酒とを一緒に飲まないことは特に重要」と具体的に注意喚起する。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月22日:新規投稿









