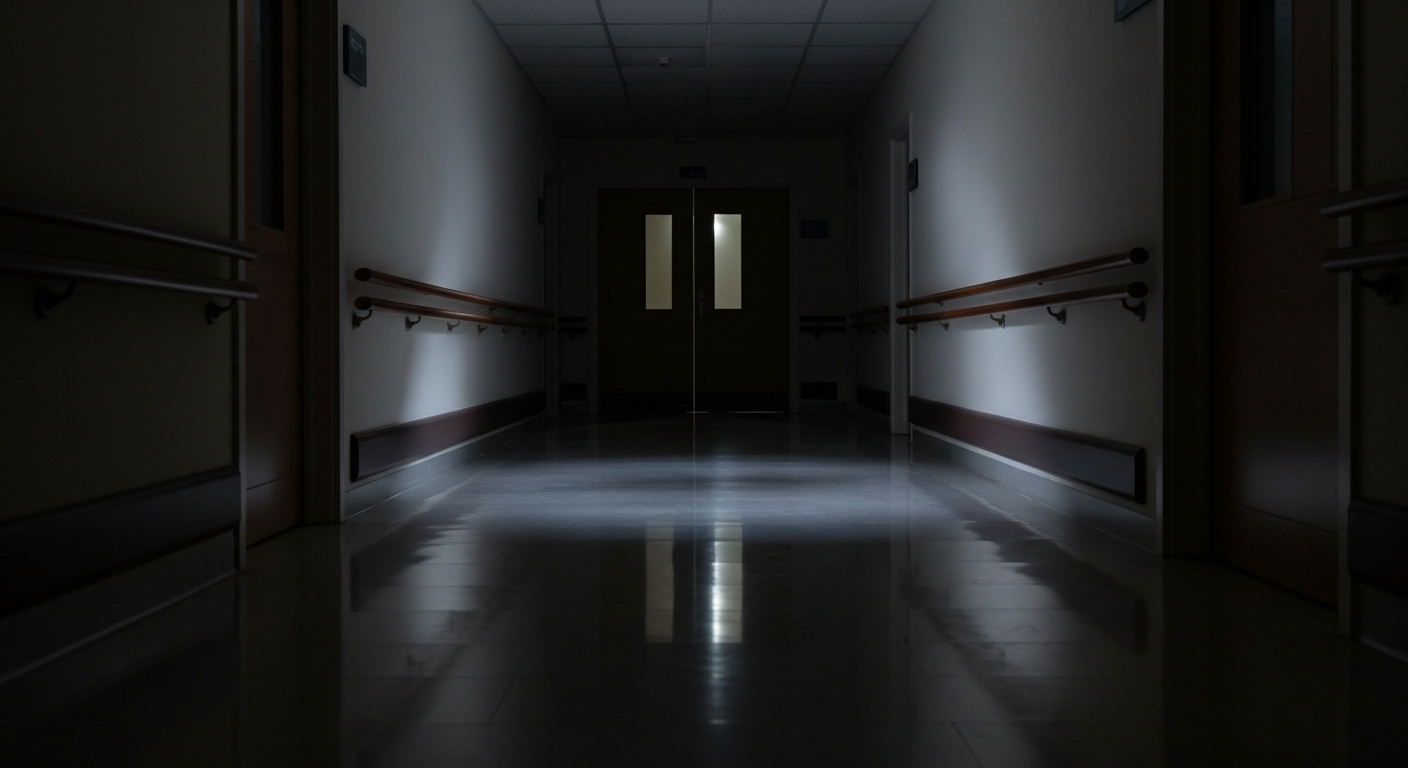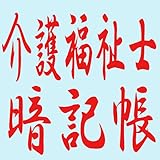「夜勤明け、疲れているはずなのに目が冴えて眠れない。」 「『明日は早番』と焦るほど、かえって寝付けない夜。」 「勤務中、ふとした瞬間に襲ってくる、ヒヤリとするほどの強烈な眠気。」
シフト勤務(交代勤務)で働く介護士さんなら、こうした悩みを一度は経験したことがあるかもしれません。
その「うまく眠れない」「日中の疲れが取れない」という感覚は、決してあなたの努力不足や、「気合が足りない」せいではありません。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます。
この記事は、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」や、日本看護協会のガイドラインなど、権威ある公的な資料に基づき、交代勤務の介護士さんが直面する睡眠の課題と、その具体的な対策(テクニック)を解説します。
【この記事を知っていると】
なぜ眠れないのかという「本当の理由」と、不規則なリズムの中でも睡眠の質を高めるための「具体的なテクニック」を知ることができ、日々の体調管理に役立てることができます。
結論:生活リズムを整える「7つの睡眠テクニック」

交代勤務による睡眠の問題は、個人の努力不足ではなく、体の仕組み(体内時計)の問題です。ここでは公的資料に基づき、不規則なリズムの中でも睡眠の質を高める「何をすべきか」を、7つの具体的なテクニックとして解説します。
テクニック1:「光」を管理する(体内時計の調整)
私たちの体は、光によって体内時計を調整しています。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、「光には体内時計を調整する作用」があると示されています。この作用を利用し、浴びるタイミングを意図的に管理することが、不規則な勤務下での睡眠改善の鍵となります。
- 早番・日勤の朝:起床後は光を浴び、からだを目覚めさせます。
- 夜勤明けの朝:ガイドラインでは「夜勤明けの朝はなるべく明るい光を避ける」ことが具体的な対策として提示されています。帰宅時にサングラスを着用するなど、強い光が目に入らないよう工夫します。
- 夜勤明けの寝室:昼間に睡眠をとる際は、遮光カーテンなどで寝室を暗くし、脳が「夜だ」と認識できる環境を作ることが重要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(参考情報:環境)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
参考情報では環境の重要性を扱い、「良質な睡眠のための環境づくりについて」を掲げる。体内時計調整では「光には体内時計を調整する作用」とし、交代勤務者向けに「夜勤明けの朝はなるべく明るい光を避ける」と具体的な光曝露のコントロールを提示する。
テクニック2:「仮眠」を戦略的に活用する(眠気の改善)
業務中の眠気対策や、疲労回復のために仮眠は有効です。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」は、「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し「仕事の効率が向上する場合があります。」と明記しています。ただし、タイミングと長さに注意が必要です。
- 夜勤中の仮眠:特に夜勤帯では「0~4時…20~50分間の仮眠…改善」と具体的に示されており、職場環境が許せば、この時間帯の短時間仮眠の活用が推奨されます。
- 長すぎる仮眠への注意:一方で、同ガイドでは「仮眠が長すぎると…睡眠慣性」が生じ、覚醒後も強い眠気や疲労感が続く可能性があるため注意が必要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(仮眠・カフェイン)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
業務中の眠気対策として「仮眠やカフェイン摂取等…眠気が改善」し「仕事の効率が向上する場合があります。」とする。特に夜勤帯では「0~4時…20~50分間の仮眠…改善」と具体的に示され、短時間仮眠の有効活用が推奨される。
テクニック3:「食事・運動」のタイミングを意識する
食事や運動も体内時計や睡眠の質に影響します。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、生活リズムのメリハリをつける工夫が示されています。
- 朝食:「しっかり朝食」を摂ることは、生活リズムにメリハリをつけます。
- 運動:「適度な運動」は良い睡眠をもたらします。
- 運動のタイミング:ただし、「激しい運動は…睡眠を妨げる可能性」があるため、就寝直前の激しい運動は避けるなど、タイミングに配慮が必要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(運動・朝食)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第2条では「適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリ」を推奨し、「定期的な運動…良い睡眠をもたらす」とする一方、「激しい運動は…睡眠を妨げる可能性」に注意を促す。勤務前後の運動強度の調整が鍵となる。
テクニック4:「嗜好品(カフェイン・アルコール)」と正しく付き合う
眠気覚ましやリラックスのために使う嗜好品には、明確なルールを持つことが重要です。
- カフェイン:厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、「就寝前 3~4 時間以内のカフェイン摂取は…控えた方が良い」とされています。
- アルコール(寝酒):アルコールは寝つきを良くするように感じますが、同指針で「睡眠薬代わりの寝酒は睡眠を悪くする」と明記されています。睡眠の質を低下させ、夜中に目が覚める原因となるため、睡眠目的の飲酒は避けるべきです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(運動・食事・嗜好品)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
行動面では「定期的な運動や規則正しい食生活は良い睡眠をもたらす」とし、刺激物について「就寝前の喫煙やカフェイン摂取を避ける」、さらに「睡眠薬代わりの寝酒は睡眠を悪くする」と具体的に注意喚起している。
テクニック5:快適な睡眠環境を整える
良質な睡眠のためには環境づくりも重要です。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、「光・温度・音等の環境因子…生活習慣…嗜好品…留意」すべき点が明示されています。特に日中に睡眠をとる必要がある夜勤明けは、環境整備が鍵となります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
本ガイドは「『健康づくりのための睡眠指針 2014』を見直し…『睡眠ガイド 2023』を策定」とし、目標を「適正な睡眠時間と睡眠休養感…年代別にとりまとめた」。加えて、実践で配慮すべき点として「光・温度・音等の環境因子…生活習慣…嗜好品…留意」を明示し、環境・行動・嗜好の包括的な睡眠衛生を示した。
テクニック6:勤務編成の「望ましい基準」を知っておく
個人の工夫だけでなく、勤務シフト自体が睡眠に大きく影響します。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」や労働者健康安全機構の資料には、負担軽減のための望ましい基準が示されています。
- 勤務間隔:疲労回復と安全のため「11時間以上の勤務間隔(基準1)」をあけることが推奨されます。
- シフトの順番:体内時計の特性上、「交替勤務の循環方式は正循環方式(日勤⇒夕勤⇒夜勤…)が望ましい。」とされています。
- 夜勤回数:負担軽減のため、「夜勤回数はなるべく少なくし」などが望ましい基準です。
出典元の要点(要約)
日本看護協会
看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(勤務編成の基準)
https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
勤務設計では「勤務の拘束時間は13時間以内とする。」と上限を掲げ、「11時間以上の勤務間隔(基準1)」を基準化。運用面では「休憩と仮眠のための時間の確保」を管理ポイントに据える。
テクニック7:セルフケアで困難なら専門家に相談する
これらのテクニックを試しても睡眠の問題が改善しない場合、一人で抱え込む必要はありません。
- 厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、「眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。」と呼びかけています。
- 同指針では「早めに専門家に相談することが重要」と明示されており、特に服薬中は「薬とお酒とを一緒に飲まないことは特に重要」と注意喚起されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(受診・相談)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第12条は支援活用を促し、「早めに専門家に相談することが重要」と明示。薬物療法の安全面では「薬とお酒とを一緒に飲まないことは特に重要」と具体的に注意喚起する。
これらのテクニックは、どれも「完璧にやろう」と気負う必要はありません。まずは「夜勤明けはサングラスをかける」「寝る前のカフェインを控える」など、今日から一つでも試せることから始めてみてください。あなたの体を守るための、大切な第一歩です。
よくある事例:シフト勤務介護士の睡眠の悩み

あなただけではありません。多くの交代勤務の介護士さんが、日々の業務の中で特有の睡眠の悩みを抱えています。ここでは、代表的な3つの事例を紹介します。
事例1:夜勤明け(疲労困憊なのに眠れない)
夜勤を終え、体はクタクタ。すぐにでも眠りたいのに、外の明るい光を浴びると目が冴えてしまい、なかなか寝付けない。やっと寝ても、数時間で目が覚めてしまう。これは、強い光によって体内時計が「朝だ」と誤解し、睡眠を妨げている典型的な例です。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」でも、夜勤明けの光の管理は重要視されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(参考情報:環境)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
参考情報では環境の重要性を扱い、「良質な睡眠のための環境づくりについて」を掲げる。体内時計調整では「光には体内時計を調整する作用」とし、交代勤務者向けに「夜勤明けの朝はなるべく明るい光を避ける」と具体的な光曝露のコントロールを提示する。
事例2:「遅番→早番」の切り替え(睡眠時間が足りない)
遅番で夜遅くに帰宅し、数時間後には早番のために起床しなければならない。このような極端に短い勤務間隔では、必要な睡眠時間を確保すること自体が困難です。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、疲労回復と安全のために「11時間以上の勤務間隔(基準1)」をあけることが推奨されており、短い休息時間は心身に大きな負担をかけます。
出典元の要点(要約)
日本看護協会
看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(勤務編成の基準)
https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
勤務設計では「勤務の拘束時間は13時間以内とする。」と上限を掲げ、「11時間以上の勤務間隔(基準1)」を基準化。運用面では「休憩と仮 préliminairesのための時間の確保」を管理ポイントに据える。
事例3:日中の眠気とヒヤリ・ハット(安全への不安)
慢性的な睡眠不足が続くと、勤務中に強い眠気に襲われ、集中力が低下します。移乗介助や服薬確認など、一瞬の気の緩みが許されない業務中にヒヤリ・ハットを経験し、「いつか事故を起こすのでは」と不安を感じるケースです。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、睡眠不足が注意力低下を招き、「居眠り運転の頻度が高い」ことなどが示されています。これは業務中の安全にも直結する問題です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(事故防止)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
指針は事故リスクに触れ、「睡眠時間が 6 時間未満の者…居眠り運転の頻度が高い」ことや、睡眠不足で「注意力が低下することが示されている」と明記。夜勤明け・通勤時の安全配慮に直結する知見を提供する。
介護士が眠れない「本当の理由」
なぜ交代勤務の介護士は、あれほどまでに眠れなくなってしまうのでしょうか。それは「気合」や「体質」の問題ではなく、勤務形態そのものが引き起こす「体内時計(概日リズム)」の乱れが最大の原因です。
交代勤務が体内時計を乱す仕組み
私たちの体は、本来「昼に活動し、夜に眠る」というリズムを持っています。しかし、交代勤務、特に夜勤は、この自然なリズムに逆らうことになります。労働者健康安全機構の資料では、交代勤務を「昼夜逆転のある不規則な就労形態」と指摘しています。この「昼夜逆転」こそが、睡眠の質を低下させ、疲労回復を困難にする根本的な理由です。
出典元の要点(要約)
労働者健康安全機構(JOHAS)
交替勤務とその対策 ~健康と生活への影響と管理のポイント~(産業保健21 第98号)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/98_14-17.pdf
交替勤務は「昼夜逆転のある不規則な就労形態」により「睡眠の質の問題と疲労回復の困難さ」が相乗し、影響が広範となる。「不眠や不十分な疲労回復は、事故やミス…安全面への影響」とされ、安全配慮の観点からも睡眠対策が不可欠である。
睡眠不足が引き起こす心身への健康リスク
睡眠の問題は、単なる寝不足では済みません。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」は、睡眠の問題が心身の健康に深刻な影響を及ぼすことを示しています。
- 精神面への影響:ガイドでは「うつ病などの精神疾患…発症初期から睡眠の問題が出現」し、さらに「睡眠の問題自体が精神障害の発症リスクを高める」と記載されています。慢性的な不眠が、意欲の低下や抑うつにつながる危険性があります。
- 身体面への影響:同ガイドは、睡眠不足が「死亡率の上昇…に関与することが明らかとなっている。」とも警告しています。厚生労働省の資料では、交代勤務者はメタボリックシンドロームや心血管系疾患の発症リスクが高まる可能性も指摘されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
本ガイドは「睡眠は…健康増進・維持に不可欠な休養活動である。」とし、「睡眠不足は…事故等の重大な結果を招く場合もある。」と警告する。さらに、睡眠の問題が慢性化すると生活習慣病に関連し「死亡率の上昇…に関与することが明らかとなっている。」と示す。介護職の交代勤務における睡眠課題の理解と、日々の健康管理の基盤として重要な位置づけである。
安全面への影響(事故・ヒューマンエラー)
睡眠不足は、ご自身の健康だけでなく、介護現場の安全にも直結します。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」は、「睡眠不足は…事故等の重大な結果を招く場合もある。」と明確に示しています。集中力や判断力が低下した状態での業務は、重大な介護事故のリスクを高めます。これは介護職自身の通勤時の安全にも関わる問題です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
本ガイドは「睡眠は…健康増進・維持に不可欠な休養活動である。」とし、「睡眠不足は…事故等の重大な結果を招く場合もある。」と警告する。さらに、睡眠の問題が慢性化すると生活習慣病に関連し「死亡率の上昇…に関与することが明らかとなっている。」と示す。介護職の交代勤務における睡眠課題の理解と、日々の健康管理の基盤として重要な位置づけである。
このように、介護士の睡眠問題は「個人の資質」ではなく、「勤務形態」に起因する構造的な問題です。だからこそ、正しい知識に基づいたセルフケアと、負担を軽減するための対策が不可欠なのです。
よくある質問(FAQ)

交代勤務の睡眠に関する、よくある疑問に答えます。
- Q休日に「寝だめ」をしても良いですか?
- A
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、「睡眠時間は人それぞれ」であり、「日中の眠気で困らない程度の睡眠時間を」確保することが一つの目安とされています。休日の寝だめが生活リズムを大きく乱す場合、かえって次の勤務に影響する可能性もあります。時間数にこだわりすぎず、睡眠による休養感(「睡眠休養感の向上」は国の重要課題とされています)が得られているかを大切にしましょう。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(睡眠時間の個人差)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第 6 条は「睡眠時間は人それぞれ」とし、「日中の眠気で困らない程度の睡眠時間を」確保することが重要だと説く。また「必要な睡眠時間は、季節や年齢によっても変化」するとし、柔軟な自己管理を促す。交替勤務下で睡眠時間が不規則になる中でも、日中のパフォーマンスを基準に自身の睡眠充足度を判断する視点を提供する。
- Qどうしても眠れない時はどうすればよいですか?
- A
焦りは禁物です。「寝床で考えごとはやめましょう」と厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」でも示されています。同指針では「眠くなってから寝床に就く」ことが推奨されています。もし寝床に入っても眠れない場合は、一度寝床を離れてリラックスできること(例:静かな音楽を聴く、難しくない本を読む)をし、再び眠気を感じてから寝床に戻る方法を試してみてください。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(入眠儀式)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第 7 条は「快適な睡眠は、環境づくりから」とし、騒音や光の調整に加え、「自分なりのリラックス法を」見つける(例:音楽、読書、香り)ことを推奨する。これは入眠儀式(スリープ・ルーティン)の重要性を示す。また、「眠くなってから寝床に就く」ことで、寝床と不眠を結びつけない(刺激制御法)考え方を提示。夜勤明けでもスムーズに入眠するための具体的な工夫点である。
- Q睡眠導入剤やサプリメントに頼っても良いですか?
- A
睡眠の問題がセルフケアで改善せず、日常生活に支障が出ている場合は、自己判断で市販薬やサプリメントに頼る前に、専門家へ相談することが重要です。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」は、「眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。」と呼びかけ、「早めに専門家に相談することが重要」と明示しています。特に服薬中は「薬とお酒とを一緒に飲まないことは特に重要」であり、安全な対策のためにも専門家の診断を仰ぎましょう。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(受診・相談)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第12条は支援活用を促し、「早めに専門家に相談することが重要」と明示。薬物療法の安全面では「薬とお酒とを一緒に飲まないことは特に重要」と具体的に注意喚起する。
まとめ
交代勤務(シフト勤務)における睡眠の問題は、個人の「気合」や「体質」のせいではなく、「体内時計の乱れ」という構造的な原因によって引き起こされます。しかし、それは「仕方ない」と諦めるしかない問題ではありません。
本記事のまとめ
この記事では、厚生労働省や日本看護協会などの公的な資料に基づき、交代勤務の介護士が直面する睡眠の課題を解説しました。睡眠不足は「作業効率の低下…事故等の重大な結果」につながるため、放置すべきではありません。結論で紹介した「7つの睡眠テクニック」(光・仮眠・食事・運動・嗜好品・環境・習慣)は、不規則なリズムの中でも睡眠の質を高め、心身の健康を守るための具体的な方法です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠ガイド 2023(事故・安全)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
ガイドは睡眠不足が「作業効率の低下…事故等の重大な結果」に繋がるとし、予防の目的は「生活の質を高めていくことは極めて重要」とする。実装に向け「本ガイド…ツールとしての活用性」を打ち出す。
今日からできる第一歩
7つのテクニックを一度にすべて実践する必要はありません。まずは「夜勤明けの帰宅時にサングラスをかける」「寝る1時間前からはスマートフォンを見ない」「寝酒をやめてみる」など、ご自身が「これならできそう」と思うことを一つでも始めてみてください。それが、ご自身の体を守るための大切な第一歩となります。
睡眠の不調が続く場合は専門家へ
もし、これらのセルフケアを試しても「日中の眠気がどうしても取れない」「やる気が起きない」「気分が落ち込む」といった状態が続く場合は、一人で抱え込まないでください。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」でも、「眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。」と呼びかけています。睡眠の問題が続く場合は、早めに専門家や医療機関に相談しましょう。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
健康づくりのための睡眠指針 2014(受診・相談)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
第12条は支援活用を促し、「早めに専門家に相談することが重要」と明示。薬物療法の安全面では「薬とお酒とを一緒に飲Tirira…まないことは特に重要」と具体的に注意喚起する。
あなたの心身の健康は、質の高い介護を提供する上での大切な基盤です。この記事が、少しでもあなたの快適な睡眠と健康の維持に役立つことを願っています。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月25日:新規投稿