「何を伝えても通じない」と感じている方はいらっしゃいますよね?夕方に不穏がみられることがあり、帰宅願望や歩行が増える。否定するとこじれ、場が緊張してしまう。そんな戸惑いに対して、根拠に沿った手順を一緒にそろえます。
結論として、非薬物を第一選択し、否定しない声掛けと環境調整を先に行う流れを定着させます。日本精神神経学会のガイドラインでは非薬物を第一選択と示し、厚生労働省の教材では「短く一度に一つ」「受容」「非言語併用」を明記しています。日本神経学会のガイドラインでは病型差の臨床像が整理され、病型差に基づく観察が実践の前提になります。
この記事を読んで分かる事
見当識障害の理解と評価の着眼点、不穏時の 否定しない声掛け の実装、夕方の 予防的環境調整 、ABC記録の 標準化 ――これらを根拠資料に沿って整え、業務の安定と効率化につなげます。
結論:非薬物を第一選択に――否定しない声掛けと環境調整を先に行う

「何を伝えても通じない」と感じる場面、夕方に不穏が高まる場面でも、手順を一本化すれば対応は整います。まず非薬物を第一選択とし、否定しない声掛けと環境調整を先に実施します。
非薬物を第一選択にする
不穏や帰宅願望への初期対応は非薬物を第一選択とし、環境調整と声掛けを優先します。薬物は必要時に最小限で開始し、効果と副作用を短周期で評価します。介入の順番を固定し、モニタリングで見直す流れを習慣化します。
※エビデンス
日本精神神経学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版・2025)
非薬物介入を第一選択とし、背景評価→非薬物→必要最小限の薬物→モニタリング・減量の手順を提示。多職種連携と継続的評価を求め、場面に応じた最小介入で安全性を高める枠組みを示しています。
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/BPSD_guideline.v.3.2025.pdf
否定しない声掛けと一度に一つ伝える
理解が揺らぐ場面では、否定しない声掛けで不安を受け止め、一度に一つの短い指示を穏やかな声で伝えます。視線・うなずき・指差しなどの非言語を併用し、相手の世界に合わせて安心の手がかりを増やします。
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
名前を呼ぶ、短文で一つずつ伝える、否定を避け受容する、非言語(表情・視線・身振り)を併用する等の原則を具体例とともに整理。環境の見やすさ調整と合わせ、混乱時のコミュニケーションを実践的に示しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
病型差を前提に観察点をそろえる
見立てを病型差に合わせます。アルツハイマー型は時間→場所→人物の順で見当識が崩れやすく、DLBは認知の変動と視空間の揺らぎ、FTDは行動変化が前景です。観察の焦点を合わせ、介入の的を外さないようにします。
※エビデンス
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第6章:Alzheimer型認知症/第7章:Lewy小体型認知症/第8章:前頭側頭葉変性症)
病型別臨床像を整理。ADでは見当識が時間→場所→人物の順で乱れやすいこと、DLBでは認知の変動や視空間障害、FTDでは行動・社会的認知の障害が目立つことを記載し、観察の重点化に資する情報を提供。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_06.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_07.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_08.pdf
同じ手順で非薬物を第一選択、否定しない声掛け、環境調整、病型差に基づく観察を積み上げれば、現場は着実に整います。次章から、具体の実装と記録の型を提示します。
事例:よくあるケース3選――受容と環境で“こじれ”を防ぐ

夕方の不穏や「通じない」場面でも、手順を一本化すれば落ち着きは戻ります。ここでは否定しない声掛けと環境調整、そして病型差を踏まえた観察を軸に、現場で再現しやすいケースを示します。
夕方に帰宅願望が高まるケース
夕方のフロアで「家に帰る」が反復。否定せず受容し、短い一事指示で「こちらで座りましょう」と同行。照度を上げ、時計・予定表を見やすく配置し、今いる場所と次の行動を視覚化。環境調整を先に置く順番で歩行往復が減ることがあり、会話が成立しやすくなります。※時間や反応には個人差があります。
- 実装の型:①受容フレーズ→②座位へ誘導→③照度・掲示→④温かい飲み物→⑤反応を記録
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
短文で一つずつ伝える、否定を避けて受容する、表情や身振りなど非言語を併用する、時計・カレンダー等の環境調整を行う実践原則を提示。混乱場面でのコミュニケーションと環境介入の基本を具体的に整理しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
自室が分からず歩行が続くケース
自室前を行き来し「ここはどこ」。職員は名乗りとアイコンタクトで安心づけ、一度に一つの短い指示で同行。ドアに名前と大きなピクトを掲示し、廊下の導線を簡素化。視空間の手掛かりを増やすことで迷いが減少し、居場所の再確認が容易になります。
- 実装の型:①名乗り→②一事指示→③誘導→④掲示・導線調整→⑤反応を記録
※エビデンス
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第2章:症候,評価尺度,検査,診断)
認知領域(注意・記憶・言語・視空間認知・遂行機能)を整理し、地誌的失見当識など迷いやすさの背景を説明。評価尺度の活用と併せ、環境手掛かりの重要性を理解する基盤を提供しています。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_02.pdf
入浴前に人物混同と拒否が出るケース
浴室前で職員を家族と取り違え、拒否が出現。否定しない声掛けで受容し、名札の提示と自己紹介、視線を合わせ「今は順番を一つずつ行います」と短く説明。浴室前の騒音を下げ、手順を指差しで視覚化。落ち着きが戻り、拒否が軽減します。
- 実装の型:①受容→②名乗り・名札→③一事指示→④静音・手順掲示→⑤反応を記録
※エビデンス
日本精神神経学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版・2025)
非薬物を第一選択とし、背景要因のアセスメント→非薬物介入→必要最小限の薬物→モニタリングという流れを提示。行動分析と環境調整、コミュニケーションの標準化で再現性を高める方針を明確にしています。
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/BPSD_guideline.v.3.2025.pdf
小さな手順の積み重ねで、非薬物を第一選択、否定しない声掛け、環境調整、記録の標準化が形になります。次のセクションでは、これらの効果を支える理由と根拠を、病型差と中核症状の視点から整理します。
理由:なぜ「声掛けと環境」で落ち着きが戻るのか
「正しさを説明しても落ち着かない」場面の背景には、中核症状と病型差があります。根拠に沿って仕組みを押さえ、非薬物を第一選択で整えると、再現性のある安定につながります。
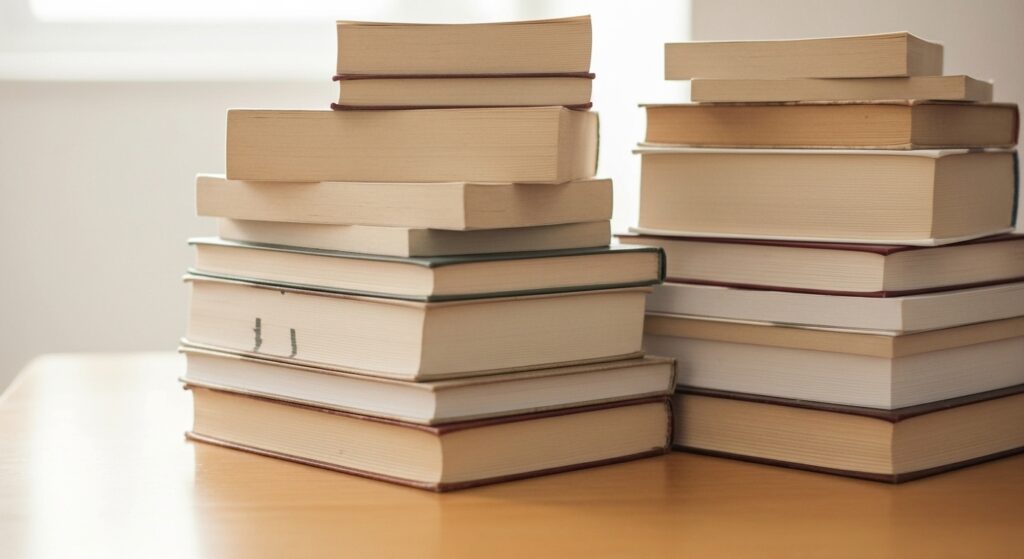
見当識障害は中核症状であり“訂正”では整いにくい
見当識障害は中核症状として位置づき、アルツハイマー型では時間→場所→人物の順で乱れが進みます。情報の訂正を重ねても不安は減りにくいため、否定しない声掛けで安心の手掛かりを先に作る設計が適合します。
※エビデンス
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第6章:Alzheimer型認知症/第2章:症候,評価尺度,検査,診断)
臨床像として見当識障害を整理し、ADで時間→場所→人物の順に崩れやすい経過を提示。症候の理解と評価(MMSE等)を通じ、介入の前提を整える枠組みを示しています。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_06.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_02.pdf
病型差が“通じる介入”の焦点を左右する
DLBは認知の変動や視空間の揺らぎ、FTDは行動変化が前面に出やすく、VaDは病変部位で症状が異なります。病型差を踏まえ、時間手掛かり・視空間の手掛かり・手順の視覚化など、介入の的を合わせる必要があります。
※エビデンス
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第7章:Lewy小体型認知症/第8章:前頭側頭葉変性症/第14章:血管性認知症)
DLBの認知の変動・視空間障害、FTDの行動・社会的認知の障害、VaDの多様な臨床像を章別に記述。病型ごとの観察点と対応の焦点化に資する情報を提供しています。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_07.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_08.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_14.pdf
BPSDは非薬物を第一選択で段階的に整える
不穏や帰宅願望はBPSDの文脈で捉え、非薬物を第一選択として原因のアセスメント→非薬物介入→必要最小限の薬物→モニタリングの段階で運用します。介入の順番を固定し、効果・副作用を継続評価します。
※エビデンス
日本精神神経学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版・2025)
非薬物優先の原則を明示し、行動分析と環境・コミュニケーション介入を起点に、薬物は最小限で導入しモニタリング・減量を組み込む段階的手順を示しています。
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/BPSD_guideline.v.3.2025.pdf
コミュニケーション原則と環境調整が安心の手掛かりを増やす
否定しない声掛け、一度に一つの短い指示、名前を呼ぶ、視線・うなずきなどの非言語を組み合わせると理解が進みます。時計・カレンダー・予定表の掲示や照度・静音の環境調整で「今・ここ」の手掛かりを増やします。
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
短文・一事指示、受容的対応、非言語の併用、時計やカレンダーの見やすい配置など、実践的なコミュニケーションと環境調整の原則を提示。現場で再現しやすい運用の土台を与えます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
根拠に沿って中核症状と病型差を押さえ、非薬物を第一選択で環境調整と否定しない声掛けを重ねれば、介入はぶれません。次章では、よくある質問を整理し、運用を安定させます。
FAQ:見当識障害への声掛けと環境調整を現場で安定運用するために
- Q認知症の見当識障害に対する声掛けの基本は?
- A
否定しない声掛けを起点に、一度に一つの短い指示を非言語の併用(視線・うなずき・指差し)で伝えます。名前を呼び、ゆっくり落ち着いた調子で話し、環境調整(時計・カレンダーの視認性)を合わせて行うと理解が進みます。
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
短文・一事指示、否定を避け受容する姿勢、表情や視線・身振りなど非言語の併用、時計・カレンダー等の配置といったコミュニケーションと環境調整の原則を具体的に整理。現場で再現しやすい手順を提示する教材です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
- Q夕方に不穏や帰宅願望が強まるときの対策は?
- A
予防的な環境調整を先に行います。照度を上げ、予定表・時計の視認性を確保し、騒音を抑え、落ち着ける座位へ受容的に誘導します。介入の順番(環境→声掛け→行動誘導)を固定し、反応を記録して次回に反映させます。
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
日常場面における環境調整(照明・掲示・音環境)と受容的コミュニケーションの組み合わせを明示。見当識の手掛かりを増やすことで不安を下げ、行動の落ち着きを促す実践的ポイントを示しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
- Q病型別に声掛けや環境の焦点は変えたほうがよいですか?
- A
病型差に応じて焦点を調整します。ADは時間→場所→人物の順で見当識が崩れやすく時間手掛かりを重視。DLBは認知の変動・視空間の揺らぎに配慮。FTDは行動変化が前景のため手順の視覚化が有効。VaDは個別性が大きく、評価所見に合わせます。
※エビデンス
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第6章:Alzheimer型認知症/第7章:Lewy小体型認知症/第8章:前頭側頭葉変性症/第14章:血管性認知症)
病型別臨床像を章別に整理。ADでは見当識が時間→場所→人物の順に乱れやすいこと、DLBでは認知の変動・視空間障害、FTDでは行動・社会的認知の障害、VaDの多様性を記載し、観察点と対応の焦点化に資する根拠を提供。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_06.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_07.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_08.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_14.pdf
- Q声掛けが通じない(日本語が理解されにくい)ときはどうすればよいですか?
- A
非言語コミュニケーションを主手段にします。穏やかな表情とゆっくりした声、視線・うなずき・指差し、同行して行動で示すなどで安心の手掛かりを増やします。否定しない声掛けと組み合わせ、短く一事で伝える流れを維持します。
※エビデンス
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
言語理解が難しい状況において、非言語の併用(表情・視線・身振り)と短文・一事指示、受容的対応を基本とすることを明確化。環境側の見やすさ調整と合わせ、伝達の成功率を高める指針を提示。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
- Q対応を安定させる記録方法はありますか?
- A
ABC記録(Antecedent-Behavior-Consequence)で介入の再現性を高めます。起こる前の状況・行動・結果を短く統一様式で記録し、介入の順番(環境→声掛け→誘導)と反応を次の交代者に引き継ぎます。
※エビデンス
日本精神神経学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版・2025)
非薬物を第一選択とし、背景評価とモニタリングを重視。行動分析の枠組みを用いて介入→評価→見直しの循環を回し、標準化された記録でチーム内の再現性を高める運用を示します。
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/BPSD_guideline.v.3.2025.pdf
まとめ:今日から始める標準化――受容フレーズ・照度チェック・ABC記録
見当識障害への対応は非薬物を第一選択とし、否定しない声掛け、一度に一つの短い指示、環境調整を先に置くことで再現性が高まります。病型差に基づく観察で焦点を合わせ、ABC記録の標準化でチーム全体の運用を揃えましょう。根拠は学会ガイドラインと厚生労働省の教材に基づきます。
要点の再確認と“今日から”の実装
非薬物を第一選択、否定しない声掛け、予防的な環境調整、病型差の観察、ABC記録を共通手順として定着させます。具体的には、受容フレーズの掲示、夕方前の照度・掲示・静音チェック、記録様式の統一を始めます。次に、家族と情報を共有し、効果のあった介入を施設全体で標準化します。
出典:
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第2章:症候,評価尺度,検査,診断)
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_02.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第6章:Alzheimer型認知症)
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_06.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第7章:Lewy小体型認知症)
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_07.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第8章:前頭側頭葉変性症)
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_08.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017(第14章:血管性認知症)
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_14.pdf
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
日本精神神経学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版・2025)
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/BPSD_guideline.v.3.2025.pdf
日本老年医学会
認知機能評価ツール(MMSE等)
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/tool_02.html
厚生労働省
認知症を理解する(症状2 見当識障害)
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/19.html
更新履歴
- 2025年9月21日:新規公開
- 2025年10月21日:一部レイアウト修正





