待っている余裕がなくて、つい質問を重ねてしまう――そんな状況に心当たりがある方、いらっしゃいますよね?「返事が遅い=拒否」と感じてしまい、現場がざわつき、自分も疲れてしまう。この悩みは珍しくありません。
本記事の結論はシンプルです。認知症ケアでは、時間的配慮と情報量の調整が要です。厚生労働省のガイドラインでは、意思形成・表明を支えるために「わかりやすい提示」と「時間をかける支援」が重要と言われています。日本認知症学会のガイドラインでも、非薬物的介入を優先し、過剰な刺激を避ける関わりが推奨されています。つまり、待つ・一問一意・環境調整が、拒否と混乱の低減に直結します。
この記事を読んで分かる事
認知症ケアで返答が遅い理由と、その背景にある認知科学的プロセスを整理できます。厚生労働省や学会のガイドラインが示す「時間的配慮」「一問一意」「過剰刺激の回避」「選択肢の絞り込み」を取り入れることで、拒否や混乱を減らし、介助を安定させる実践手順が分かります。
待てない声かけが認知症ケアに拒否と混乱を生む実態

忙しさのなかで質問を重ねてしまい、返答が遅い相手を「拒否」と受け取ってしまうことはありませんか。まずは時間的配慮と情報量の調整という基本に立ち返り、現場を静かに整えます。
結論と基本方針
認知症ケアでは、わかりやすい提示・一問一意・時間的配慮・環境調整を徹底します。厚生労働省のガイドラインでは、意思形成・表明を支えるために「理解しやすい情報提供」と「少し時間を置く支援」を重視しています。結論として、待つことを標準化し、再質問の連発を避け、静かな場面設計を行います。
出典
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の意思形成・表明を支えるため、分かりやすい情報提示と時間的配慮、環境調整を重視する枠組みを示す。場面設計や支援プロセスの要点が整理され、現場での標準化に活用できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
現場でまず実行すること
呼名→視線の確認→短い文で一問一意→少し時間を置く→必要時に少数回の言い換えで再提示(状況に応じて)→少し時間を置く→選択肢は絞って視覚提示、の順で進めます。過剰刺激の回避(早口・同時発話・騒音)を徹底し、記録には「待機の有無」を残して標準化を促します。
- 一問一意:同時に複数の用件を重ねない
- 選択肢は絞る:2案+指差し・カードで視覚補助
- 環境調整:テレビ音や雑音を下げ、静けさを確保
出典
日本精神神経学会
重度認知症患者のコミュニケーション能力への対応(精神神経学雑誌 123巻5号)
認知症では言語・注意・遂行機能の低下が重なり、情報量と提示様式が応答に影響することを概説。短い文、非言語的手掛かり、環境調整が理解と表明を助けると整理されている。
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1230050270.pdf
得られる効果とリスク管理
時間的配慮と情報量の調整により、再質問の減少、場面の安定、拒否の低減が期待できます。日本認知症学会のガイドラインでは、非薬物的介入を優先し、過剰刺激の回避を前提とした対応を推奨しています。嚥下や転倒など安全が最優先の場面は例外として即時介入します。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSD対応は非薬物的介入を第一選択とし、環境調整やコミュニケーションの工夫を優先する立場を整理。過剰な刺激を避け、穏やかな関わりを基盤にする重要性が述べられている。
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
静かな場面設計と標準化は、今日から実行できる改善です。基本の徹底が、利用者の意思表明を守り、現場の負担を和らげる一歩になります。
現場で起きやすいケースと基本対応

忙しさのなかで質問を重ね、相手の沈黙を「拒否」と受け取ってしまう場面は少なくありません。まずは時間的配慮と情報量の調整をそろえ、静かな場面設計に整えます。
朝の更衣ラインが滞るときの整え方
呼名→視線の確認→短い文で一問一意→少し時間を置く→必要時に少数回の言い換えで再提示(状況に応じて)→少し時間を置く。選択肢は絞り、指差しやカードで視覚補助を添えます。過剰刺激の回避(早口・同時発話・雑音低減)を同時に行い、記録には「待機の有無」を明記して標準化します。
出典
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の意思形成・表明を支えるため、理解しやすい情報提供、時間的配慮、環境調整を重視する枠組みが示されている。場面設計と支援プロセスを明確化し、現場での手順化に役立つ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
食事の選択で固まりやすいときの整え方
「主食はこれ」「飲み物はこれ」のように一問一意で順番に提示し、少し時間を置きます。選択肢は少数に絞り(例:2案など)、視覚提示を併用、実物・写真・指差しで視覚補助を行います。早口や重ね質問を避けることで、拒否の低減と場面の安定が期待できます。
出典
日本精神神経学会
重度認知症患者のコミュニケーション能力への対応(精神神経学雑誌 123巻5号)
言語・注意・遂行機能の低下により、情報量と提示様式が応答に影響することを概説。短い文、非言語的手掛かり、環境調整が理解と表明を助ける方策として整理されている。
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1230050270.pdf
入浴前説明で拒否が強まるときの整え方
説明は短く要点のみとし、少し時間を置いた上で確認します。人・物・音を絞って過剰刺激の回避を徹底し、必要に応じて言い換えは1回まで。安全が最優先となる場面は例外として速やかに介入します。標準化の観点から、手順と振り返りをチームで共有します。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSD対応では非薬物的介入を第一選択とし、環境調整とコミュニケーションの工夫を優先する立場を示す。刺激の過多を避け、穏やかな関わりを基盤とする重要性が整理されている。
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
小さな整え方の積み重ねが、時間的配慮と情報量の調整を軸とした安定した認知症ケアにつながります。次の場面から、静かな場面設計と手順の標準化を始めましょう。
なぜ返答が遅くなるのか――背景と根拠を整理する
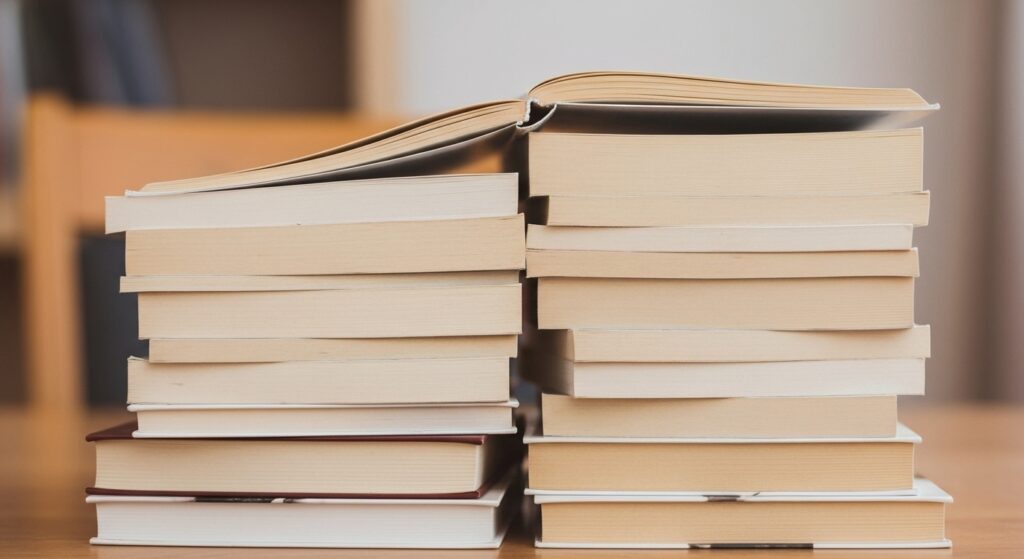
返答までの「間」は偶然ではありません。情報処理の段階や環境の刺激、時間的配慮の不足が重なり、応答が遅く見える背景があります。ここで根拠を踏まえて整理します。
情報処理の段階を分けて考える
聴取→意味理解→記憶からの想起→選択→発話という連続工程のどこでも遅延は起こります。高齢では反応時間が延びやすく、問いが長い・選択肢が多いほど負荷が増します。一問一意と選択肢の絞り込みは、この工程を軽くするための基本です。
出典
理学療法関連誌
二重課題条件下での反応時間と認知機能・脳萎縮の関連
地域高齢者で反応時間が延長し、注意分配の負荷や課題の複雑化で遅延が増す傾向を報告。情報処理の段階に負荷がかかると応答潜時が延びることを示唆する。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2010/0/2010_0_EbPI1413/_article/-char/ja/
時間的配慮は意思決定支援の中核
時間的配慮とわかりやすい情報提供は、意思形成・表明を支えるための中核です。環境調整と併せて支援プロセスを整えることで、応答の機会が守られます。独自の秒数は設定せず、原典の表現に従い少し時間を置く姿勢を共有します。
出典
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の意思形成・表明を支える枠組みとして、理解しやすい情報提示、時間的配慮、環境調整を体系化。場面設計から記録までの実務上の配慮点を明確化している。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
過剰刺激の回避と非言語の活用
早口・同時発話・騒音・多すぎる選択肢は過剰刺激となり、応答潜時をさらに延ばします。短い文・指差し・カードなど非言語的手掛かりを組み合わせ、過剰刺激の回避と情報量の調整を同時に進めます。
出典
日本精神神経学会
重度認知症患者のコミュニケーション能力への対応(精神神経学雑誌 123巻5号)
言語・注意・遂行機能の低下により、提示様式と情報量が応答に影響することを概説。短い文、非言語支援、環境調整が理解と表明を助ける方策として整理されている。
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1230050270.pdf
静かな場面設計と時間的配慮、そして情報量の調整が揃うと、返答までの「間」は意思表明のために必要な時間として機能します。次のセクションでは、実装の手順をさらに具体化します。
よくある質問(FAQ)

返答が遅い場面に焦りが生まれやすいからこそ、時間的配慮と情報量の調整を基本に据えて対応を整えます。検索意図の高い疑問に要点で答えます。
- Q認知症ケアで返答が遅いとき、まず何をすればいいですか?
- A
わかりやすい提示、一問一意、時間的配慮、環境調整をそろえます。呼名→視線の確認→短い文→少し時間を置く→必要時に少数回の言い換えで再提示(状況に応じて)→少し時間を置く、の順で進め、記録に「待機の有無」を残して標準化します。
出典
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
本人の意思形成・表明を支えるため、理解しやすい情報提供、時間的配慮、環境調整を重視する枠組みを示す。支援プロセスを整理し、場面設計と手順の標準化に活用できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
- Qどのくらい待てばよいですか?独自の秒数は必要ですか?
- A
原典では「少し時間を置く」と表現されています。独自の秒数を追加せず、状況に応じて時間的配慮を行います。提示は一問一意で、選択肢は絞り、静かな環境を整えます。
出典
厚生労働省
意思決定支援ガイドラインをより理解するための事例集(第2版)
ガイドラインの考え方を場面に落とし込み、時間配慮や情報提示の工夫、環境調整の具体例を示す。独自の時間数値を設けず、「少し時間を置く」などの表現で配慮を示す。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484892.pdf
- Q質問はどのように短くすべきですか?選択肢は何個が適切ですか?
- A
一問一意を原則に、短い文で順番に提示します。選択肢は絞り、指差しやカードなどの非言語的手掛かりを併用します。早口・同時発話・騒音などの過剰刺激の回避を徹底します。
出典
日本精神神経学会
重度認知症患者のコミュニケーション能力への対応(精神神経学雑誌 123巻5号)
言語・注意・遂行機能の低下を踏まえ、提示様式と情報量が応答に影響することを概説。短い文、非言語支援、環境調整を組み合わせる実践が整理されている。
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1230050270.pdf
- Q急かさない対応はBPSDの予防に役立ちますか?
- A
非薬物的介入を優先し、過剰刺激の回避と環境調整、コミュニケーションの工夫を基盤にします。時間的配慮と情報量の調整を整えることで、拒否や混乱の低減が期待できます。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSD対応は非薬物的介入を第一選択とし、環境調整やコミュニケーションの整備を前提にする立場を示す。刺激過多を避け、穏やかな関わりを基盤に据える重要性が整理されている。
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
- Q返答が遅く見える科学的な背景はありますか?
- A
高齢では反応時間が延びやすく、課題の複雑化や注意分配の負荷で遅延が増す傾向が報告されています。情報量の調整と一問一意が応答潜時を軽くする基本になります。
出典
理学療法科学
地域在住高齢者における認知機能と反応時間の関連
地域高齢者を対象に、反応時間の延長と認知負荷の影響を検討。注意分配や課題複雑性の増加で応答潜時が延びる傾向を示し、場面設計の必要性を示唆する。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/34/4/34_393/_pdf
まとめ――時間的配慮と情報量の調整を標準化する
急かす声かけが拒否と混乱を招きやすい背景を確認しました。ここからは、時間的配慮と情報量の調整を日々のケアに組み込み、現場の安定と意思表明の機会を守ります。
今日から実行する最小ステップ
呼名→視線の確認→短い文で一問一意→少し時間を置く→必要時に少数回の言い換えで再提示(状況に応じて)→少し時間を置く→選択肢は絞って視覚提示。静かな場面を整え、記録に「待機の有無」を残して標準化へつなげます。
出典
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
理解しやすい情報提供、時間的配慮、環境調整を体系化。意思形成・表明を支える支援プロセスを示し、現場手順の明確化に資する。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf
チームで定着させる運用
用語と手順を統一し、標準化を進めます。短時間の振り返りで「再質問の回数」「待機の有無」を確認し、過剰刺激の回避(早口・同時発話・騒音低減)を共通ルールにします。
出典
日本精神神経学会
重度認知症患者のコミュニケーション能力への対応(精神神経学雑誌 123巻5号)
言語・注意・遂行機能の低下を踏まえ、短い文、非言語支援、環境調整を組み合わせる実践の重要性を整理。提示様式と情報量が応答に影響する点を解説。
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1230050270.pdf
安全場面の例外と判断
嚥下や転倒など安全が最優先となる状況は、時間的配慮よりも迅速な介入を優先します。平時は情報量の調整と時間的配慮を基本に、例外時は即時対応という方針を共有します。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
非薬物的介入の優先と環境調整を基盤にしつつ、状況に応じた柔軟な対応を求める立場を整理。刺激過多の回避と穏やかな関わりを重視。
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
継続学習のポイント
時間的配慮・一問一意・情報量の調整を軸に、反応時間や注意分配に関する学術知見を定期的に確認します。現場の事例を蓄積し、手順と記録を更新します。
出典
理学療法科学
地域在住高齢者における認知機能と反応時間の関連
高齢者で反応時間が延びやすく、課題の複雑化や注意分配の負荷が遅延を増す傾向を報告。場面設計における情報量調整の必要性を示唆。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/34/4/34_393/_pdf
静かな場面設計を整え、時間的配慮と情報量の調整をチームで標準化する。それが、拒否と混乱を減らし、介助の安定につながる出発点です。
関連記事
更新履歴
- 2025年9月29日:新規投稿










