夜勤明けの静かな詰め所。 PCの画面と向き合いながら、「あの時、もっと早く訪室していれば…」と、一人で自分を責めてしまう。
巡視を重ねても、防ぎきれない事故。 その悔しさは、あなたの頑張りが足りないからではありません。もし、利用者の「起き上がりそうな予兆」を、あなたのスマホがそっと教えてくれるとしたら。そんな「先回りの見受け」が、実はもう夢物語ではないのです。
「気合」や「根性」といった個人の力に頼る介護は、もう限界かもしれません。だからこそ今、国(厚生労働省)もテクノロジーの活用を公式に後押しし始めています。
この記事では、夜勤の精神的な負担を軽くし、利用者の安全とあなたの心を守るための、新しい見守りの形を具体的に解説します。
この記事を読んで分かる事
結論:「先回りで守る——介護×ICTで必要時訪室を標準化する」

巡視だけでは守り切れない不安を、介護×ICTで「通知→確認→対応」の型に変えましょう。小さく始め、KPIとPDCAで確かめながら標準化するのが近道です。
必要時訪室の最短ループを固定化する
通知(センサー)→確認(映像)→声かけ→必要時のみ訪室の順で運用を一本化します。厚生労働省の資料では、見守りセンサーやインカム等の活用が職員負担の軽減とケアの質の向上に資すると示しています。現場では「アラートの優先度」「誰が動くか」「記録の残し方」を明文化し、リアルタイム共有で属人化を防ぎます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「見守りセンサーやインカム等…ツール等を活用することによる業務改善は、職員の身体的・精神的負担の軽減や、ケアの質の向上に資する。」
- リアルタイムで記録・共有・確認できる仕組みの構築を推奨
- 重複記録の解消・標準化が急務
ユニット単位のPoCから開始し、KPIで効果を確認する
導入は1ユニットの小規模PoCから。初期設定のままにせず、訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断・事故(重篤度別)を同一条件で前後比較します。厚生労働省の資料では、データで成果を示し、継続的に確認・見直しする枠組みを提示しています。KPIとPDCAを回し、鳴りすぎ・見落としを週次で調整しましょう。
PoC(ピーオーシー)とは?
「Proof of Concept(概念実証)」の略で、新しい機器や仕組みを本格導入する前に、まず1つのユニットなど小規模な範囲で「お試し」してみることです。
PoCの主な目的
低リスクでの検証: 全施設で一斉に導入するリスクと費用を避け、最小限の負担でその仕組みが自分たちの現場に合うかどうかを安全に検証します。
効果の確認:「本当に転倒は減るか?」「夜勤の負担は軽くなるか?」といった効果を、客観的なデータで確かめます。
課題の洗い出し:「アラートが鳴りすぎる」「この操作が分かりにくい」など、現場で実際に使ってみて初めてわかる問題点を見つけ、本格導入の前に改善します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 「機器の導入により…業務効率化(訪室回数の変化、駆け付け時間等)に繋がったことをデータ等で説明すること」
- 「成果が確認されていること/継続的に確認し、見直しを行っていること」
- 委員会でデータ(睡眠・心拍・呼吸等)を活用しケアに反映
BPSDは非薬物療法を起点に、薬物は例外的に最小有効量・単剤で
日本老年医学会のガイドラインでは、BPSDへの対応は非薬物療法が原則と示されます。薬物療法が必要な場合も、包括的アセスメント→目標設定→最小有効量・単剤→定期評価・漸減を徹底します。せん妄の鑑別や評価尺度による定期評価を運用に組み込み、漫然投与を避けます。
出典元の要点(要約)
日本老年医学会
介護施設内での転倒に関するステートメント
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20210611_01_01.pdf
- 「BPSDへの対応は,まず非薬物療法を試みることが原則」
- 「治療目標(標的症状)を明確に設定し,家族にも説明」
- 「定期的に有効性を評価し,漫然と長期投与しない」
制度の後押しを活用し、同意・体制・連携を整える
厚生労働省の資料では、見守り機器の活用を前提に夜間の人員配置基準を1.0→0.9へ緩和する項目が示されています。要件に沿って全員同意・情報共有体制・データ提出・緊急対応連携を整えましょう。介護×ICTは制度面でも推進されており、現場の標準化に追い風です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 「夜間における人員配置基準を1.0から0.9に緩和する」
- 「利用者全員の同意を得た上で、見守り機器を導入」「職員全員がインカム等を使用」
- 急変時に迅速対応できる体制の構築
最後に――必要時訪室を核に介護×ICTを小さく始め、KPIとPDCAで確かめながら現場標準に育てていきましょう。明日の夜勤から変化を実感できます。
事例:よくある夜勤の“つまづき”を必要時訪室でほどく3ケース

巡視中心の動き方を、通知→確認→対応へ。ここでは現場で頻度の高い3パターンを、必要時訪室の視点で整理します。
ケースA|起き上がり予兆→遠隔声かけ→必要時のみ訪室
離床センサーの通知を起点に、映像で安全確認し、スピーカーで待機を依頼。不要訪室を抑えつつ、必要場面には即応します。運用は「誰が一次対応」「何分以内に再確認」「記録はどこに残す」を手順として固定化。効果は訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断回数で前後比較し、週次でアラート感度を調整します。
- 運用の型:通知(センサー)→確認(映像)→声かけ→訪室
- 評価の型:KPIとPDCAで前後比較(同一条件で測定)
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 「見守りセンサーやインカム等…による業務改善は、職員の負担軽減とケアの質の向上に資する。」
- リアルタイムで記録・共有・確認できる仕組みの構築
- 重複記録の解消・標準化の必要性
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 導入効果(訪室回数・駆け付け時間等)をデータで説明
- 成果の継続確認と見直し
- 委員会でデータを活用しケアへ反映
ケースB|夜間の徘徊が集中する帯を“ゾーン×時間”で最適化
覚醒パターンを記録し、通知は重点帯と重点ゾーンに限定。出口・曲がり角などの危険箇所に視野を合わせ、アラート疲労を抑えながら即応性を維持します。優先度付き通知と担当の割り振りを明文化して、属人化を防ぎます。
- 設計の型:重点帯(時刻)×重点ゾーン(位置)×優先度
- 検証の型:駆け付け時間・誤報率の推移を月次レビュー
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- リアルタイム共有体制の整備
- 業務の標準化でムリ・ムダ・ムラを削減
- PDCAの継続実施
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 逐語引用:職員全員がインカム等を使用し迅速に共有
- 急変時に迅速対応できる体制構築
- データで成果を説明
ケースC|排泄予測×睡眠保護で“起こさないケア”を実装
膀胱センサー等の傾向から誘導に適したタイミングを把握し、睡眠保護と失禁対応の軽減を両立。定時交換一律から、個別パターンに合わせた必要時対応へ切り替えます。通知幅は週次のPDCAで最適化し、洗濯・清掃の周辺負担も含めて評価します。
- 設計の型:個別の貯尿傾向×誘導タイミング×必要時訪室
- 評価の型:排泄失敗率・睡眠中断回数・周辺作業時間の推移
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- ICT活用で情報共有と記録の効率化
- PDCAで継続改善
- 24時間の暮らし全体を捉える視点
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 導入効果のデータ説明
- 生産性向上の評価と加算要件
- 同意・体制・連携の整備
3つのケースはいずれも、必要時訪室を核にKPIとPDCAで運用を磨くことが鍵です。小さく始め、確かめてから広げる——その積み重ねが標準になります。
理由:制度・科学・運用の3本柱で“気合では守れない”を超える
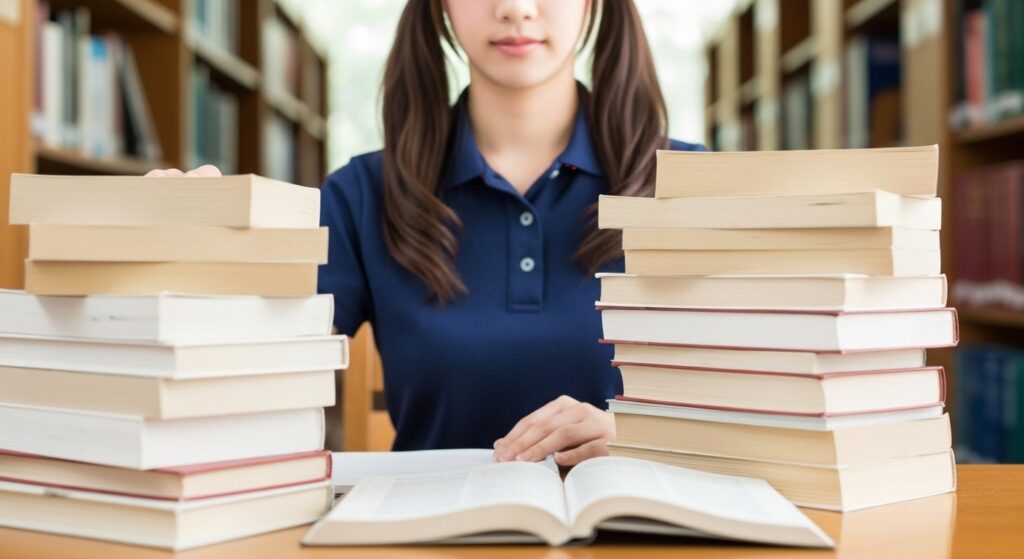
夜勤の不安は、制度の後押し・エビデンス・運用設計の3点で小さくできます。ここでは土台となる根拠を要点でまとめます。
制度的後押し:要件を満たせば現場は軽くなる
報酬改定では、見守り機器の活用を前提に夜勤体制や加算で評価する枠組みが整っています。全員同意・情報共有・データで成果説明といった明確な要件を満たすことで、必要時訪室の実装が組織の標準になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 見守り機器の導入と体制整備を評価
- 利用者全員の同意、職員全員の機器使用体制
- 導入効果をデータで説明し、継続的に確認・見直し
業務の可視化:通知→確認→対応で判断負担を減らす
厚生労働省の論点整理では、見守りセンサーやインカム、リアルタイム記録・共有の整備が職員負担の軽減とケアの質向上に資すると示されています。重複記録をやめ、役割と優先度を明文化することで、迷いとムダを減らせます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf
- 見守り機器・インカム等の活用で負担軽減と質向上
- リアルタイムで記録・共有・確認できる仕組み
- 標準化でムリ・ムダ・ムラを削減
BPSD対応の原則:非薬物療法を起点に、薬は最小有効量・単剤
日本老年医学会のガイドラインでは、BPSDは非薬物療法が原則とされています。やむを得ず薬物を使う場合も、包括的アセスメント→目標設定→最小有効量・単剤→定期評価・漸減を徹底し、漫然投与を避けることが求められます。
出典元の要点(要約)
日本老年医学会
介護施設内での転倒に関するステートメント
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20210611_01_01.pdf
- BPSDはまず非薬物療法を試みる
- 目標(標的症状)を明確化し説明
- 有効性を定期評価し、漫然と長期投与しない
KPIとPDCA:効果を数値で示し続ける仕組み
訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断・事故の重篤度などをKPIとして設定し、導入前後を同条件で比較します。委員会で睡眠・心拍・呼吸などのデータを活用し、月次で見直す体制を固定化しましょう。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 導入効果をデータで説明
- 提出データに基づき成果を確認
- 委員会でデータを活用しケアへ反映
同意・連携の徹底:信頼が運用を支える
全員同意、保存期間と権限管理、看護との連携と緊急対応までを運用規程に明記します。休憩の確保や複数人協働の体制も求められ、テクノロジーと人的支援の両輪が安全の前提になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf
- 利用者全員の同意と情報共有体制
- 急変時に迅速対応できる連携体制
- 夜勤時間帯の協働と休憩確保
小さく始め、必要時訪室を核に仕組みを磨く——制度の要件とガイドラインに沿って進めれば、現場の安心は着実に積み上がります。
よくある質問:介護×ICTの導入と運用
- Q介護 ICT を導入すると、夜勤の負担は本当に軽くなりますか?
- A
通知→確認→対応の流れを標準化し、見守りセンサーとインカムで不要訪室を抑制すると、事後対応が減り判断も平準化します。厚生労働省の整理では、こうした取組が職員負担の軽減とケアの質の向上に資すると示されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業(報告書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001148548.pdf- 見守りセンサーやインカム等の活用で、負担軽減と質向上に資する
- リアルタイムで記録・共有・確認できる仕組みの整備を推奨
- 重複記録の解消や業務の標準化を課題として提示
- Q必要時訪室は、どんな最小構成から始めればよいですか?
- A
離床などの見守りセンサー+映像確認(カメラ)+音声連絡(インカム)+記録・共有から小規模に開始します。ユニット単位のPoCで、訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断を同条件で前後比較し、週次で調整します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf- 導入効果をデータで説明(訪室回数、駆け付け時間 等)
- 成果の継続確認と見直し(PDCA)を求める
- 委員会で睡眠・心拍・呼吸等のデータを活用しケアへ反映
- Q見守りカメラの導入時、同意やプライバシーはどう扱えばよいですか?
- A
利用者全員の同意取得、目的の明確化、保存期間・権限管理・持ち出し禁止・閲覧ログを運用規程に明記し、職員全員が機器を使用して情報共有できる体制を整えます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf- 全員同意の取得と機器活用体制の整備を要件化
- 急変時に迅速対応できる連携体制の構築
- 夜勤体制の見直しを見守り機器の活用とセットで評価
- QBPSDには薬を使えますか?
- A
日本老年医学会のガイドラインでは、BPSDは非薬物療法が原則です。やむを得ず薬物を使う場合も、包括的アセスメント→目標設定→最小有効量・単剤→定期評価・漸減を徹底し、漫然投与を避けます。
出典元の要点(要約)
日本老年医学会
介護施設内での転倒に関するステートメント
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20210611_01_01.pdf- BPSDはまず非薬物療法を試みることを原則化
- 治療目標(標的症状)の明確化と家族への説明を求める
- 定期的に有効性を評価し、漫然と長期投与しない
- Q効果測定は何を指標にすればよいですか?
- A
訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断回数・事故件数(重篤度別)・アラート誤報率などをKPIに設定します。委員会でデータを共有し、月次で見直しを行います。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き ver.2
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001276275.pdf- 成果をデータで説明することを要件化
- 提出データに基づき業務改善の成果を確認
- 委員会でのデータ活用と継続的見直しを位置づけ
まとめ:小さく始め、必要時訪室を標準に——明日からの一歩
今日の要点は、介護×ICTで「通知→確認→対応」を型にし、必要時訪室へ移行すること、そしてKPIとPDCAで効果を可視化することです。まずはユニット単位のPoCで、訪室回数・駆け付け時間・睡眠中断を同条件で前後比較し、週次で設定を整えましょう。BPSDは非薬物療法を起点に、薬物は最小有効量・単剤・定期評価を徹底。制度面の要件(同意・体制・データ活用)も合わせて整備すれば、夜勤の不安は確実に小さくできます。
本情報は2025年10月4日までの内容です。導入や申請の直前には、一次資料の最新版をご確認ください。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月5日:新規公開
- 2025年10月6日:引用部分の一部修正









