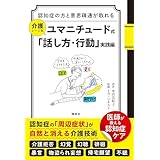「口を開けてくれない」焦りと、業務に追われる中での無理強いへの葛藤。現場では板挟みになることがあります。
全部を完璧にするのは難しくても、「とろみの不快感」と「関わり方」を知るだけで、拒否は減らせるかもしれません。
この記事を読むと分かること
- 拒否に隠れた身体的理由
- とろみが招く摂取量減少
- 自尊心を守る関わり方
一つでも当てはまったら、この記事が役に立ちます
結論:「食べない」はわがままとは限らず、身体と心からの「サイン」かもしれません

「栄養を摂らせなきゃ」という責任感と、「無理やり口に入れるのは虐待じゃないか」という罪悪感。 現場では、その板挟みで苦しい思いをすることがありますよね。
その拒否が「認知症だから」ではなく、別の理由だとしたらどうでしょうか。
拒否には「とろみによる不快感」が隠れている可能性があります
良かれと思って付けている「とろみ」が、実はご本人の摂取量を減らしているかもしれません。
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の資料では、とろみを付けることで腹部膨満感(お腹の張り)を誘発したり、さっぱり感が減って摂取量が減ったりする場合が多いと報告されています。
また、時間が経つと味や香りが劣化することも指摘されており、これが「食べたくない」要因になっている可能性があります。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
とろみを付けることは安全に液体を摂取してもらうための対応であるが,腹部膨満感を誘発したりさっぱり感が少ないため摂取量が少なくなったりする場合が多いとの報告があり,脱水予防のためには摂取量の把握が必要としている.とろみ調整食品は数十秒を要する場合が多く,所定の量を十分混ぜ,時間がたってからとろみの程度を評価して判断する必要がある.また味や香りが劣化すること,糖尿病の患者に大量に使用する場合はエネルギー計算が必要であること,付着性などが異なるため試飲を心がけたいことを示している.
無意識の「幼児語」が自尊心を傷つけている可能性があります
親しみを込めたつもりの言葉遣いが、逆効果になる場合もあります。
厚生労働省の資料では、心理的な配慮として「幼児語を使わず自尊心を尊重する」ことが挙げられています。
また、相手のペースに合わせず一方的に話しかけたり、目の前で職員同士だけで話して「置き去り」にしたりすることも、心理的な拒絶と受け取られる可能性があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法ー認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
心理的特徴に応じたかかわり方として、価値観や考え方、習慣を受容する、幼児語を使わず自尊心を尊重する、不快でない距離や目線の高さに留意する、相手の表情を確認しながら話しかける、相手のペースに合わせ気持ちを汲み取る、家族とだけ話したりせず相手を置き去りにしないといったポイントがある。
拒否行動は、単なるわがままではなく「お腹が苦しい」「扱いが嫌だ」というサインかもしれません。無理に食べさせる前に、まずはとろみの量や関わり方が原因になっていないか、振り返ってみることが糸口になるかもしれません。
よくある事例:現場で起きている「食べない」の典型パターン

「本人のペースに合わせましょう」と教わっても、次々に業務が押し寄せる現場では、待つ余裕がないこともあるのではないでしょうか。
また、良かれと思って行った工夫が、結果的に「拒否」につながっているケースも少なくありません。現場でよくある3つの場面を見てみましょう。
【事例1】とろみ食を「数口で残してしまう」
- 状況
- 誤嚥が怖いので、お茶や汁物にしっかりとろみを付けて提供している。
- 困りごと
- 最初は口を開けるが、すぐにスプーンが進まなくなり、食事全体を残してしまう。
- よくある誤解
- 「認知症で食欲が落ちている」「わがままで残している」と思い込んでしまう。
- 押さえるべき視点
- とろみは腹部膨満感(お腹の張り)を誘発したり、さっぱり感が損なわれたりすることがあります。お腹が苦しくて食べられない可能性があります。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
とろみを付けることは安全に液体を摂取してもらうための対応であるが,腹部膨満感を誘発したりさっぱり感が少ないため摂取量が少なくなったりする場合が多いとの報告があり,脱水予防のためには摂取量の把握が必要としている.
【事例2】親しく接したら「顔を背けられた」
- 状況
- 親しみやすさを込め、「〇〇ちゃん、ごはんですよー」「あーんして」と幼児語で話しかけている。
- 困りごと
- 笑顔で接しているつもりなのに、利用者が不機嫌になり、口を固く閉ざしてしまう。
- よくある誤解
- 「認知症だから機嫌が悪い」「私のことが嫌いなのかな」と落ち込んでしまう。
- 押さえるべき視点
- 幼児語は避けたほうがよいとされています。子供扱いされたと受け取られる可能性があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法ー認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
心理的特徴に応じたかかわり方として、価値観や考え方、習慣を受容する、幼児語を使わず自尊心を尊重する
【事例3】急いで食べさせたら「むせてしまった」
- 状況
- 次の業務が控えており、「早く終わらせたい」という焦りからペースを速めて介助している。
- 困りごと
- 次々とスプーンを運ぶと、口から出したりむせ込んだりして、かえって時間がかかる。
- よくある誤解
- 「飲み込みが悪くなった」「もっと協力してほしい」と感じてイライラしてしまう。
- 押さえるべき視点
- 相手のペースに合わせ、表情を確認しながら進めることが基本とされています。急かされる不安や不快感につながっているかもしれません。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法ー認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
不快でない距離や目線の高さに留意する、相手の表情を確認しながら話しかける、相手のペースに合わせ気持ちを汲み取る
「食べない」背景には、とろみによる身体的な苦しさや、関わり方による心理的な拒絶が隠れている可能性があります。「認知症だから」と決めつけず、「苦しくないか?」「嫌な思いをさせていないか?」という視点を持つことが望ましいです。
なぜ「食べない」のか? 認知症のせいだけではない身体と心の「3つの理由」

「理想のケア」として、美味しく調理し、ゆっくり待つべきだとは誰もが分かっています。 しかし現場では、人員不足や時間の制約から「安全のためにとろみを濃くする」「急いで介助する」という対応を取らざるを得ないこともあるでしょう。
ただ、皮肉なことに、その「安全対策」や「業務効率化」が、利用者様の「食べたくない理由」を作り出してしまっている可能性があるのです。
【身体的要因】とろみによる「お腹の張り」と「脱水」の悪循環
- 建前(理想):とろみは誤嚥を防ぎ、安全に水分を摂るためのもの。
- 現実(現場):安全を優先して濃くしがちだが、それが満腹感を招いている。
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の分類によると、とろみ調整食品の使用は腹部膨満感(お腹の張り)を誘発しやすいとされています。 お腹が張って苦しければ、食事が入りにくいことがあります。
さらに、とろみ特有の「さっぱり感のなさ」から摂取量が減る場合があり、脱水予防のためには摂取量の把握が必要とされています。 「飲ませなきゃ」と濃いとろみを勧めることが、逆効果になっているかもしれません。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
とろみを付けることは安全に液体を摂取してもらうための対応であるが,腹部膨満感を誘発したりさっぱり感が少ないため摂取量が少なくなったりする場合が多いとの報告があり,脱水予防のためには摂取量の把握が必要としている.
【感覚的要因】時間が経つことによる「味や香りの劣化」
- 建前(理想):適温で、美味しい状態で食事を提供する。
- 現実(現場):配膳や他の方の介助に時間がかかり、口に入る頃には状態が変わっている。
とろみ調整食品は、混ぜてから時間が経つと状態が変化するだけでなく、味や香りが劣化するとされています。
私たちも、不味いものや香りの悪いものは箸が進みにくいことがあります。 「食事拒否」と記録される行動の裏には、認知機能の問題ではなく、味や香りの変化が影響している可能性を見落とさないようにしましょう。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
とろみ調整食品は数十秒を要する場合が多く,所定の量を十分混ぜ,時間がたってからとろみの程度を評価して判断する必要がある.また味や香りが劣化すること,糖尿病の患者に大量に使用する場合はエネルギー計算が必要であること,付着性などが異なるため試飲を心がけたいことを示している.
【心理的要因】「子供扱い」による自尊心の傷つき
- 建前(理想):人生の先輩として敬い、丁寧に関わる。
- 現実(現場):親しみを込めたつもりの「ちゃん付け」や、忙しさからくる「置き去り」が発生している。
厚生労働省の資料では、「幼児語を使わず自尊心を尊重する」ことが挙げられています。 また、目の前で家族や職員同士だけで話し、ご本人を「置き去り」にすることも避けることが望ましいとされています。
「自分を尊重してくれない人」から食事を介助されることは、屈辱的と感じる場合があります。 口を閉ざすのは、その不快感に対する精一杯の「No」の意思表示かもしれません。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法ー認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
心理的特徴に応じたかかわり方として、価値観や考え方、習慣を受容する、幼児語を使わず自尊心を尊重する、不快でない距離や目線の高さに留意する、相手の表情を確認しながら話しかける、相手のペースに合わせ気持ちを汲み取る、家族とだけ話したりせず相手を置き去りにしないといったポイントがある。
食べない理由は「認知症」だけとは限りません。良かれと思った「とろみ」がお腹を苦しくさせ、親愛のつもりの「言葉」が自尊心を傷つけている可能性があります。そのミスマッチに気づくことが、第一歩になるかもしれません。
現場の小さな迷いを解決! 食事拒否ととろみに関するFAQ
「食べない」理由が分かっても、実際の対応では迷うことがたくさんありますよね。 現場でよく聞かれる悩みについて、専門機関の資料を基に整理します。
- Qとろみは「濃いめ」につけたほうが安心ですか?
- Aいいえ、濃すぎると腹部膨満感(お腹の張り)につながったり、付着性が変わったりすることがあります。 時間が経つと状態が変わるため、混ぜてから少し置いて評価することが望ましいです。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
とろみを付けることは安全に液体を摂取してもらうための対応であるが,腹部膨満感を誘発したりさっぱり感が少ないため摂取量が少なくなったりする場合が多いとの報告があり,脱水予防のためには摂取量の把握が必要としている.とろみ調整食品は数十秒を要する場合が多く,所定の量を十分混ぜ,時間がたってからとろみの程度を評価して判断する必要がある.
- Q拒否されたときの「接し方のコツ」はありますか?
- A目線の高さを合わせ、威圧感を与えない距離で表情を確認しながら話しかけましょう。 ご本人のペースを尊重し、幼児語を使わず大人として接することが挙げられています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法ー認知症の理解
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
心理的特徴に応じたかかわり方として、価値観や考え方、習慣を受容する、幼児語を使わず自尊心を尊重する、不快でない距離や目線の高さに留意する、相手の表情を確認しながら話しかける、相手のペースに合わせ気持ちを汲み取る、家族とだけ話したりせず相手を置き去りにしないといったポイントがある。
- Q一度決まった「とろみ」は、ずっと続けるべきですか?
- A原則はとろみを付けますが、個別に水分の嚥下評価を行い、不要と判断されれば解除できる場合があります。 一律の対応にせず、ご本人の状態に合わせて見直すことが挙げられています。
出典元の要点(要約)
一般社団法人 日本老年歯科医学会(共同:一般社団法人 日本在宅栄養管理学会)
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン 2017
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
本表に該当する食事において,汁物を含む水分には原則とろみを付ける。【Ⅰ-9項】ただし,個別に水分の嚥下評価を行ってとろみ付けが不要と判断された場合には,その原則は解除できる。
食事の拒否には、とろみによる身体の苦しさや、関わり方の心理的違和感が隠れていることがあります。「いつも通り」で済ませず、ご本人の表情や反応を評価し、適切な濃度や接し方を再検討してみましょう。
まとめ:拒否は「サイン」。まずは一口、味見から始めよう
ここまで、「食べない」という行動の裏にある理由を見てきました。
現場ではどうしても「どうやって食べさせるか」に必死になってしまいますが、ふと立ち止まってみてください。
全部を明日から変える必要はありません。 まずは、ご本人に出しているそのとろみ食を、一口だけ自分で味見(試飲)してみてください。
「意外とベタベタするな」「味が薄まっているな」と気づくだけで十分です。
その「気づき」があれば、「なんで食べないの」という 苛立ちが和らぎ、「食べにくいのかもしれない」という寄り添うケアに変わっていく可能性があります。
最後までご覧いただきありがとうございます。この記事が参考になれば幸いです。
関連コンテンツ
更新履歴
- 2025年10月28日:新規投稿
- 2026年2月15日:より詳細なエビデンス(根拠)に基づき解説を充実させるとともに、最新のサイト基準に合わせて構成・レイアウトを見やすく刷新。