「むせる」「食事が長い」「オン・オフでペースが合わない」—現場でよくありますよね。声かけも介助も正しいはずなのに結果が揺れる…そんな“やりづらさ”に心がすり減っていませんか?
食事介助は、姿勢×一口量×ペース×食形態(とろみ再現)×タイミング(オン時間)を整えることで、安全性と安定化に大きく寄与します。ここが整えば、誤嚥リスクと“延び延び食事”はぐっと減らせます。
PDは日内変動(オン・オフ)が大きく、嚥下や注意も揺れます。だからこそ「待つ介助」と多職種の統一手順、そして再現性あるとろみと食前準備(姿勢・口腔)が効きます
- はじめに:現場で「むせ」と「延びる食事」を減らすために
- 食前準備:安全な一口のための仕込み
- 食事中の介助:手の運びと声かけを“同じ型”にそろえる
- とろみ再現の壁を越える:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2013」で“同じ濃度”を作る
- オン・オフ現象への実務対応:否定せず、安全を添えて“チャンス”を活かす
- 口腔・栄養・歯科連携:経口維持と誤嚥性肺炎予防の“下半身”を固める
- よくある“つまずき”とNG対応:誤解をほどき、再現性を高める
- 事例で学ぶ:現場ショート3例で“型”を固める
- 明日から使えるチェックリスト:5×7×6×4で“同じ介助”をつくる
- FAQ:現場で迷いやすい5つの疑問を先に解いておく
- まとめ:標準化(型)×時間設計×共有で、明日の一口を安全に
- 関連記事
- 更新履歴
はじめに:現場で「むせ」と「延びる食事」を減らすために

忙しいフロアで、同じ手順でも日によって食事が進んだり止まったり。そんな揺れに翻弄されていませんか。まずは姿勢・一口量・ペース・食形態・タイミングの土台をそろえましょう。
食事介助の土台は5点で決まる
食事介助は、姿勢(骨盤を立て軽い前傾と顎引き、足底接地)、一口量(最小量から開始)、ペース(嚥下確認まで待つ)、食形態(学会分類2013で再現性を担保)、タイミング(オン時間を活用して配膳・服薬・離床を同期)の5点を組み合わせると安定します。とくにとろみの再現は安全性の鍵です。施設内で作り方・確認手順・申し送り様式まで統一するとブレが減ります。
学会分類2013とは?
「学会分類2013」とは、日本摂食嚥下リハビリテーション学会が策定した嚥下調整食の全国共通基準で、食形態やとろみの段階を統一する指標です。
公式ページ:https://www.jsdr.or.jp/doc/classification2013.html
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章) 引用章
食事・嚥下は姿勢調整やSTの訓練と併用し、日内変動を踏まえた時間設計が要点と記載。教育・食事指導の有用性、L-ドパ吸収に食事や併用物が影響すること、オンの活用と“待つ介助”の重要性を示している。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
パーキンソン病の“揺れ”を前提にする
パーキンソン病はオン・オフで「動ける/動けない」が日内で変動します。急なオンは本人の貴重な持ち時間。否定せず、安全を添えて活かしましょう。一方、オフで固まる時は、無理に進めず姿勢保持→中断→再セットへ。配膳・服薬・離床の順序を見直し、オンの時間帯に食事工程を寄せると、むせと延長を抑えやすくなります。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第1章/第11章) 引用章
L-ドパの半減期が短く日内変動の原因となる点、運動療法や安全確保の位置づけ、進行期でも介入有効であることを整理。オン時間の活用と安全重視が実務上の要点として示されている。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_09.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
多職種で“同じやり方”にそろえる
介護は個人技ではなくチーム戦。医師が薬のタイミングを整え、STが姿勢・一口量・食形態を設計し、介護士が同じ手順で回す。口腔清掃と食後ケアは歯科・栄養と連携してルーチン化。むせ回数、残留、使用したとろみ手順、配膳と服薬の関係を記録と申し送りで見える化すると、翌日の介助精度が上がります。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章) 引用章
リハビリテーションは医師・PT・OT・ST・看護・介護の連携で行うべきと明記。病期に応じて目標を変え、安全確保と合併症予防、家族教育を含めた継続が重要と整理している。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017(本文・暫定版) 引用本文
口腔管理と栄養管理を同時に実施し、経口維持と誤嚥性肺炎予防を図る枠組みを示す。家族を含むユーザーにわかりやすく、多職種が使える実務的指針として位置づけている。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
https://www.gerodontology.jp/committee/file/job_link_20170626.pdf
日々の揺れに惑わされず、まずは土台の5点をチームで統一。明日の一口が安全に進む準備を、今日の一皿から整えていきましょう。
食前準備:安全な一口のための仕込み

パーキンソン病の入居者にとって、食事は生命を守るだけでなく、楽しみの時間でもあります。食前のちょっとした準備を整えるだけで、むせや誤嚥を減らし、安心して介助を進められます。
オンの時間に合わせる
服薬後に体が動きやすい時間(オンの時間)を狙って食事をセットすると、嚥下がスムーズになります。逆にオフの時間に無理に食べ始めると、むせや停滞が増えてしまいます。配膳のタイミングや離床時間を、薬効のピークとリンクさせる工夫が大切です。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第1章/第11章) 引用章
L-ドパの効果は時間依存的で、日内変動(オン・オフ)を生じる。服薬と生活行為を調整することがADL維持に直結する、と明記されている。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_09.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
姿勢づくりを徹底する
食事中のむせを減らす基本は、骨盤を立てる・軽く前傾する・顎を引く・足底を床につけるの4点です。ベッド上でもギャッジアップ+足台で代替できます。姿勢が崩れると、どんなにとろみを工夫しても誤嚥リスクは下がりません。
出典
厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
嚥下を助ける基本体位は、背筋を伸ばし軽度前傾、顎引きを推奨。体位・環境調整が摂食嚥下障害予防の最初の一歩とされる。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
嚥下ウォームアップを取り入れる
食前に口唇・舌・頸部の軽い運動をするだけで、嚥下機能は安定しやすくなります。特にパーキンソン病では筋の硬さが影響するため、ウォームアップは大きな効果を持ちます。歌唱や発声も準備運動の一部になります。
出典
日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
反復唾液嚥下テストや口腔体操などを食事前に取り入れることで、嚥下リスクを軽減し、誤嚥性肺炎の予防に寄与すると整理されている。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
環境を整える
テレビ音や複数人からの声かけが重なると、注意が分散し嚥下が止まりやすくなります。静かな環境・照明調整・一対一の声かけを徹底することで、本人の集中が高まり、安全性が増します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章 非薬物療法Q&A)
注意分散は症状を不安定にしうるため、嚥下時は静かな環境・一対一の声かけなど単一課題化を推奨。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
食前準備は「ただの段取り」ではなく、命を守るケアです。オンの時間に合わせ、姿勢と環境を整え、嚥下ウォームアップを取り入れることで、次の一口が格段に安全になります。
食事中の介助:手の運びと声かけを“同じ型”にそろえる

同じ人でも日によって進み方が違う――だからこそ、介助の“型”をそろえると安定します。一口量・角度・ペース・確認を決め、誰が介助しても揺れにくい流れを作りましょう。
一口量とスプーン角度を小さく正確に
最初の数口は最小の一口量で開始し、水平〜やや上向きの角度で口唇からそっと置くことを徹底。口腔内の残留やポケットを観察し、頬部軽いタッピングや舌の誘導で取り込みを促します。顎引き・軽い前傾・足底接地が崩れていないかも同時に確認。量と角度の標準化は、むせと延長を減らすもっとも再現性の高い一手です。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
嚥下障害には姿勢調整と食形態の工夫、言語聴覚士の訓練が有用と整理。安全な摂食を支える基本として、姿勢づくりと食事操作の標準化が重要とされる。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
口腔・嚥下の観察、残留の評価、口腔機能の支援を組み合わせて安全な経口摂取を進める枠組みを提示。基本手技の標準化が事故予防に直結する。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
ペーシング:“飲み込み→呼吸復帰”まで必ず待つ
介助の核心は待つことです。投入→嚥下確認(喉頭挙上・呼吸の整い)→次の一口の三拍子を崩さない。急がせるとむせ・拒否・固縮を誘発します。オン・オフの日内変動も考慮し、オフなら中断→姿勢維持→再セットへ切り替える判断をスタッフ全員で共有します。同じペース配分は、食事の延長と誤嚥を大きく減らします。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
進行期でもリハ介入は有効。教育・食事指導は有用で、L-ドパの吸収と日内変動を踏まえたタイミング設計、焦らせない支援が実務の要点として記載。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
むせ・停滞時のリカバリー手順を決めておく
むせが続く、口腔内で停滞する――そんな時は中断→姿勢再セット→口腔内の確認→水分で洗い流し(指示濃度のとろみ)→再開可否の判断をルール化。必要時はST・歯科・看護へ共有し、食形態や一口量を見直します。“濃ければ安全”ではないため、とろみの再現(計量・攪拌・時間・温度)を手順書で担保します。
- 中断の合図と言い回しを統一
- 再開は“最小量”から
- 同日の再挑戦は疲労にも配慮
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
学会分類2013は形態と言語の標準化を示し、再現性ある提供を求める。物性の数値固定より、運用上の手順と解説の熟読による再現確保を重視。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf厚生労働省
口腔機能向上マニュアル
体位調整、口腔準備、食事中の留意点、効果測定まで具体的に示し、誤嚥・窒息予防に寄与。中断と再セットの手順化が安全性を高める。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
とろみは“再現手順”で安全を設計する
計量→攪拌→所要時間→温度→最終確認を決め、誰が作っても同じ濃度を目指します。配膳票や申し送りにとろみ手順・粉量・水温・攪拌秒数を記録し、変更時は必ず共有。コード0t/0j〜各コードを共通言語に、形態と一口量・ペースをセットで設計すると事故が減ります。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
段階は形態で統一し、栄養量は原則規定しない。物性の数値化が難しい現場特性を踏まえ、運用における再現手順と解説の理解を重視する方針を提示。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf農林水産省(参照掲載)
嚥下調整食分類2013(同一本文参照版)
行政資料としての参照版。施設・委託・メーカー間での段階整合や周知に役立ち、提供の標準化と再現性向上に資する。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/pdf/07aka1_sankou3_gakkai_bunrui.pdf
“手の運び”と“声かけ”を型に落とすことで、誰が介助しても安全水準が揃います。明日からは、最小一口・待つ・再現する――この三つをチームで徹底しましょう。
とろみ再現の壁を越える:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2013」で“同じ濃度”を作る

同じ粉でも作る人・温度・攪拌で濃さが変わる——その“ブレ”こそ誤嚥リスクの盲点です。まずは正式な共通言語と再現手順で、施設内外のやり方をそろえましょう。
正式名称を明記し、共通言語として運用する
初出は日本摂食・嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2013」(以下、学会分類2013)と正式表記に。学会分類2013は形態を中心に段階を定義し、コード(0j/0t〜)で誰が見ても同じ意味を共有できます。配膳票・記録・申し送りにコードを明記し、一口量・ペース・姿勢もセットで記述すると、提供の再現性が高まります。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会のガイドラインでは、こうした標準化が現場の混乱を減らすと整理されています。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
学会分類2013は、医療・介護・在宅をつなぐ共通言語として食事形態ととろみ段階を定義。栄養量の画一規定は避け、形態の統一と解説に基づく運用で再現性を確保する枠組みを示す。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
“計量→攪拌→時間→温度→最終確認”を固定する
とろみは粉量の精密計量、一定の攪拌方法と時間、待ち時間(粘度安定)、飲料の温度で粘度が変化します。手順書に水温・粉量・攪拌秒数・最終確認方法(スプーンからの落ち方等)を明文化し、誰が作っても同じ濃度を目指します。学会分類2013では、物性を単純な数値固定にせず実務的な再現運用を重視しており、施設の標準手順化が推奨されます。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
物性値の一律規定ではなく、現場での手順統一と解説の理解により再現性を担保する設計方針を提示。段階コードの運用を通じて提供のばらつきを抑える。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
“濃ければ安全”の誤解を捨て、残留リスクを抑える
過濃のとろみは咽頭残留を増やすことがあり、窒息・誤嚥の引き金になります。コードだけでなく、一口量・ペース・姿勢を同時に調整し、停滞やむせが続けば中断→姿勢再セット→最小量で再開を基本にします。厚生労働省のマニュアルは、体位・操作の標準化とPDCAで安全性を高める枠組みを示しており、“濃度だけで解決しない”視点が重要です。
出典
厚生労働省
口腔機能向上マニュアル
体位・環境・食事操作・効果測定までの手順を示し、誤嚥・窒息予防に資する運用を整理。中断と再セット、観察・記録のプロセス化が実践の要点として示されている。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
外部委託・メーカーと段階整合を取る(行政参照版の活用)
給食委託や市販介護食を用いる場合は、製品仕様の段階と学会分類2013のコード整合を発注・受入時に確認します。農林水産省の参照掲載版を共有すると、委託・調理・介護の間で同じ基準を持ちやすく、納入切替時の取り違えも予防できます。発注書・配膳票にコードと作り方の要点を併記し、変更時は申し送りで全員に周知します。
出典
農林水産省(参照掲載)
嚥下調整食分類2013(同一本文の参照版)
学会分類2013の本文を行政サイトに掲載し、施設・委託・メーカー間での段階整合と周知を後押し。標準化と再現性の向上に役立つ。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/pdf/07aka1_sankou3_gakkai_bunrui.pdf
正式名称の明記、手順の固定、段階整合の共有——この三点をそろえれば、濃度の“ブレ”は着実に小さくなります。今日の一杯を、明日も同じ濃さで提供できる体制を整えましょう。
オン・オフ現象への実務対応:否定せず、安全を添えて“チャンス”を活かす

同じ人でも、ある日は動けて、別の日は固まる——その揺れこそパーキンソン病の前提です。オンの時間を活かし、オフでは待つ介助に切り替える“運用設計”が食事介助の安定に直結します。
オフでは急がせない:中断・姿勢保持・再セット
オフ時は無理に進めないことが基本です。嚥下がまとまらない・反応が遅い・固縮が強いときは、いったん中断→姿勢を整える→再セットへ。顎引き・軽い前傾・足底接地の基本姿勢を保ち、安全>継続で判断します。再開は最小一口量から。チームで中断の合図と言い回しを統一し、動揺を減らします。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
進行期でもリハ介入は有効と示し、教育・食事指導の有用性、日内変動(オン・オフ)への配慮、焦らせない支援の重要性を整理している。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
突然オンは“本人の持ち時間”:否定せず、安全を添える
オフだと思っていたのに、急に座位が保てる/立ち上がれる——こうしたオンの立ち上がりは、食事・トイレ・更衣を進める好機です。「さっきはできなかったのに」ではなく、事実の承認+安全な伴走へ言い換えます。手を添えて転倒予防、歩行や移乗は二重課題を避ける。オンが短い人ほど、この切り替えがQOLに影響します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第1章/第11章)
L-ドパの半減期の短さと日内変動、オン時の機能活用、転倒予防・安全確保の位置づけを整理。施設ではオン時間を活かす計画が合理的と読み取れる。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_09.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
タイミング設計:服薬・配膳・離床を同期させる
食事工程は服薬後のオンに寄せて配置します。日本神経学会のガイドラインでは、L-ドパ吸収に影響する要因(食後服薬、牛乳・制酸薬、胃排出遅延など)が挙げられ、食事指導が必要と示されています。必要に応じて蛋白再配分(PRD)を検討しますが、体重減・ジスキネジアの懸念があるため、医師・栄養士と綿密に運用します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章 非薬物療法Q&A)
教育・食事指導の有用性、L-ドパ吸収に影響する要因、PRDの有効性と留意点を明示。時間設計と多職種連携の必要性が示される。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
記録と申し送り:オン・オフの“見える化”で再現性を高める
ケアの質を安定させる鍵は可視化です。①オン出現時刻と持続、②むせ回数・残留、③使用したとろみ手順(粉量・水温・攪拌秒数)、④配膳と服薬の関係を記録し、同じ書式で申し送り。“誰が担当でも同じ進め方”を担保します。歯科・ST・栄養への情報フィードバックが介入の精度を上げます。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
リハビリは医師・PT・OT・ST・看護・介護の連携で実施し、病期ごとに目標を変え継続する重要性を記載。チーム内での標準化・共有が前提になる。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
“否定せず、安全を添える”が合言葉です。オンを活かし、オフでは待つ——この切り替えを時間設計と記録で支えれば、明日の食事介助はもっと安定します。
口腔・栄養・歯科連携:経口維持と誤嚥性肺炎予防の“下半身”を固める
食事介助を安定させるには、口腔と栄養の土台が欠かせません。食前・食中の工夫だけでなく、食後ケアと多職種連携を“同じ型”にして、毎食のばらつきを減らします。
口腔ケア×栄養×嚥下評価を同時に回す
経口維持と誤嚥性肺炎予防は、口腔清掃・嚥下評価・栄養評価を同時に回すと効果が出やすくなります。歯科(往診可)と栄養(管理栄養士)、STの導線を予め決め、食形態・一口量・ペースの見直しに直結させます。家族にも同じ説明資料で共有すると、ケアの再現性が上がります。
出典
日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
口腔評価・嚥下スクリーニング・栄養評価を統合し、経口維持と誤嚥性肺炎予防を目指す実務枠組みを示す。家族を含むユーザーに分かりやすい運用を重視。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
食後ケアを“型”にする:残留・ポケット対策
食後の口腔残留・頬ポケットは誤嚥の火種です。うがい/吸引の手順・義歯の管理・保湿を定型化し、残留が多い日は次回の一口量・ペース・食形態に反映します。ケア実施の有無でなく、残留量・部位・再発頻度を記録して次の判断材料にします。
出典
厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
体位・環境・口腔体操・食後の口腔管理までPDCAで標準化し、誤嚥・窒息予防とQOL向上に資する手順を提示。観察と記録が次の介入精度を高める。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
チームで“同じ説明”をする:家族合意と再現性
薬のタイミングやオン・オフの揺れ、とろみの再現手順、口腔管理の目的は、家族にも同じ言葉で伝えます。配膳票・口腔ケア記録・とろみ手順を見える化し、面会時に確認できるようにすると合意形成が早く、現場負担も減ります。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
リハビリは医師・PT・OT・ST・看護・介護の連携で実施し、患者・家族への教育・指導を重要要素として位置づける。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017(本文・暫定版)
家族を含むユーザーに理解しやすい説明と多職種活用を重視。口腔と栄養の同時介入を現場で使える形に整理。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
https://www.gerodontology.jp/committee/file/job_link_20170626.pdf
“測って残す”で質を担保:モニタと申し送り
毎食のモニタリング指標を少数精鋭で固定します。下の例を施設標準にして、同じ用語・同じ書式で回してください。
| 指標 | 例示 | 次の一手 |
|---|---|---|
| むせ回数 | 0/1/2回以上 | 中断→姿勢再セット→最小量へ |
| 口腔残留 | 無/少/多(部位) | 一口量縮小・ペース延長 |
| とろみ手順 | 粉量・水温・攪拌秒数 | 手順の再確認・共有 |
| オン時間 | 服薬後の開始時刻 | 配膳・離床の同期 |
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章/第I編 第11章)
教育・食事指導の有用性、L-ドパ吸収と生活時間設計、進行期でも介入有効である点を整理。標準化と共有が実践効果を高める。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
口腔・栄養・嚥下を同時に回し、食後ケアの型化と同じ説明、少数精鋭の指標で“測って残す”。この三本柱が、経口維持と誤嚥予防の再現性を高めます。
よくある“つまずき”とNG対応:誤解をほどき、再現性を高める
「濃ければ安全」「オフでも進められる」――現場で繰り返し起きる誤解を解くと、食事介助は一気に安定します。ここでは仕組みから修正できるNGを整理します。
NG1:「濃ければ安全」ではない――過濃は残留と窒息を招く
過度のとろみは咽頭残留を増やし窒息リスクを高めます。まずは学会分類2013(正式名)のコードで形態をそろえ、計量→攪拌→時間→温度→最終確認を固定。さらに一口量・ペース・姿勢を同時に調整します。厚生労働省のマニュアルでも体位・操作の標準化とPDCAを重視しています。ここを外すと、濃度だけをいじっても事故リスクは下がりません。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
段階を形態で統一し、現場では手順の標準化と解説の理解で再現性を担保する方針を提示。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
厚生労働省
口腔機能向上マニュアル
体位・環境・食事操作・評価を一体化し、誤嚥・窒息予防に資する運用を示す。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
NG2:オフでも“とにかく続ける”――安全より継続を優先しない
オフでは嚥下や反応が鈍くなり、急かすほどリスクが上がるのがパーキンソン病の特性です。中断→姿勢保持→再セットを基本に、再開は最小一口量から。オンの時間に寄せて工程を配置する設計が要です。日本神経学会のガイドラインは、日内変動(オン・オフ)を踏まえた時間設計と教育の有用性を明確にしています。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
進行期でも介入は有効で、焦らせない支援・時間設計・教育の有用性を整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
NG3:自己判断のサプリ追加――薬効と安全性の“ブレ”を増やす
カフェインやハーブ、ムクナ豆などを自己判断で追加すると、L-ドパ含有量や相互作用の不確実性で日内変動が悪化しかねません。日本神経学会は有効性の高いエビデンスは乏しく、ムクナ豆は勧めないと明言。食事指導と服薬タイミングの見直しを先に行い、サプリは医師と相談が原則です。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章)
サプリメントは有効性の高い根拠が乏しく、ムクナ豆は安全とは言い切れず推奨できないと整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
NG4:賑やかな環境・二重課題での介助――注意分散が“止まり”を生む
テレビ音や複数同時の声かけ、作業と会話の二重課題は、すくみや停止を誘発しやすく、嚥下の流れも乱れます。単一課題化して、一対一の声かけに絞るのが安全。日本神経学会の非薬物療法のQ&Aは、外的刺激の調整を基本に据えています。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章)
環境・課題設定の調整が症状安定と安全な動作に寄与することを整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
NG5:PRD(蛋白再配分)を安易に導入――体重減・ジスキネジアに要注意
PRDは有効例がある一方、体重減少・ジスキネジア増悪の懸念も示され、導入・維持は医師・栄養士と綿密に行う必要があります。まずは食後服薬や牛乳・制酸薬の同時服用回避など、L-ドパ吸収の阻害因子を外すことが先決です。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章 非薬物療法Q&A)
PRDの有効性と留意点、L-ドパ吸収に影響する因子、食事指導の必要性を明示。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
誤解を正す近道は、標準化(型)×時間設計×情報共有です。NGを減らし、同じやり方を積み上げるほど、明日の一口は安全で短く、本人の満足度も高まります。
事例で学ぶ:現場ショート3例で“型”を固める

どの事例も「姿勢・一口量・ペース・食形態・タイミング」の5点で整理すると、迷いが減ります。共通の型に落とし込み、チーム全員で同じやり方にそろえましょう。
ケース1:朝食が延びる——オンが来ない朝の設計
状況整理:起床後、服薬直前に配膳してしまい、オフのまま食事が始まり延びている。
対応の型:①服薬→②離床→③配膳の順に再設計する。L-ドパ吸収を妨げる要因(食直後、牛乳・制酸薬併用など)を避け、オン時間に合わせて一口量は最小から開始。むせや停滞が続けば中断→姿勢再セット→再開判断へ。
強調点:タイミング再設計、“待つ”ペース、最小一口量の三点で安定化。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章/第I編 第11章)
L-ドパ吸収に影響する要因(食後服薬、牛乳・制酸薬、胃排出遅延)を整理し、教育・食事指導の有用性、日内変動(オン・オフ)への配慮と“焦らせない支援”を示す。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
ケース2:主食で止まりデザートだけ進む——形態とペースの再設計
状況整理:ご飯やパンで停滞し、プリンやゼリーは進む。残留が多く、むせが時折出る。
対応の型:学会分類2013のコードで食形態を統一し、一口量の縮小とペーシング(飲み込み→呼吸復帰まで待つ)を徹底。顎引き・軽い前傾・足底接地の姿勢を維持し、必要に応じてコード段階を見直す。過濃は残留を増やすため、とろみは“計量→攪拌→時間→温度→最終確認”で再現。
強調点:食形態の標準化、最小一口量、再現手順の三点を固定。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
食事形態・とろみ段階の共通言語(コード)を提示し、数値固定より運用手順の標準化で再現性を担保する枠組みを示す。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
嚥下障害には姿勢調整・食形態工夫・ST訓練が有用と整理。食事操作は標準化が重要。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
ケース3:食後トイレ誘導中に「ご飯食べたい」——急なオンの活かし方
状況整理:食後にオフが続いていたが、誘導中に突然オンとなり、自発的に動き始め「ご飯食べたい」と発言。
対応の型:否定せず事実を承認し、安全を添えて行動を整理する(例:「今は動けています。トイレを済ませてから次にしましょう」)。急なオンは本人の貴重な持ち時間であり、転倒予防に配慮しながら必要な工程(排泄・更衣・水分補給)を優先して進める。二重課題は避け、声かけは一対一で簡潔に。
強調点:否定しない受け止め、安全の添え方、二重課題の回避。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第1章/第11章/第III編 第4章)
L-ドパの半減期の短さによる日内変動、オン時の機能活用、環境・課題設定の調整(単一課題化)と安全確保の重要性を示す。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_09.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
事例を“型”に落として振り返ると、次の現場での判断が速くなります。チームで同じ言葉・同じ手順を共有し、再現性のある食事介助を積み重ねましょう。
明日から使えるチェックリスト:5×7×6×4で“同じ介助”をつくる
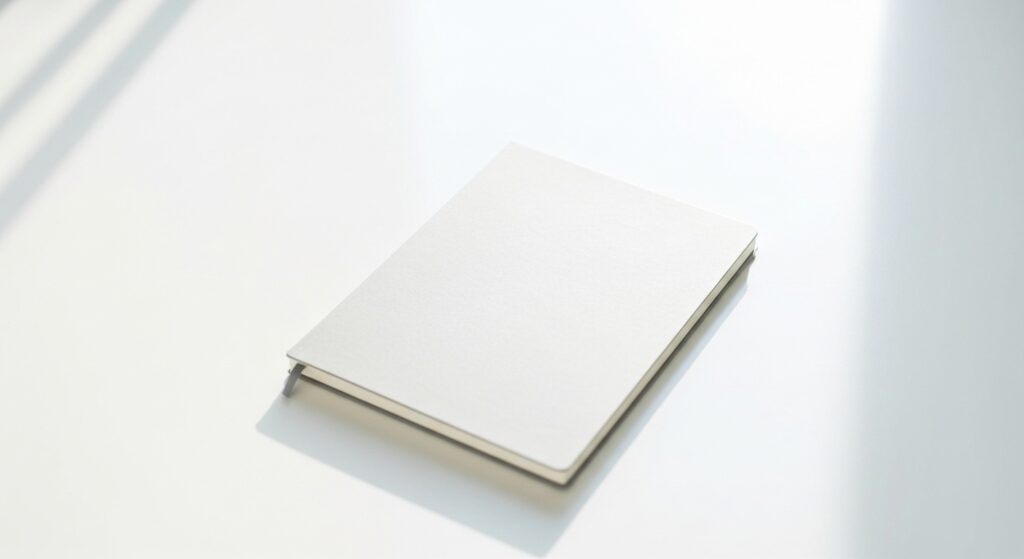
その日の調子に左右されないために、誰が担当しても同じ結果に近づく型を用意します。食前5・食中7・とろみ6・連携4の計22項目を、同じ用語・同じ書式で回しましょう。
食前5項目(オン時間/姿勢/口腔/環境/配膳同期)
- オン時間の見極め:服薬後の開始時刻を決める
- 姿勢:骨盤立て・軽前傾・顎引き・足底接地
- 口腔準備:清掃+軽い口腔体操
- 環境:テレビや同時声かけを避け単一課題化
- 配膳同期:服薬→離床→配膳の順序で固定
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
オン・オフを踏まえた時間設計、教育・食事指導の有用性、焦らせない支援を整理。食事工程をオンに寄せる発想が妥当で、標準化が実務の核になる。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
体位・環境・口腔準備と評価を含むPDCAを提示。基本体位と事前準備が誤嚥・窒息予防とQOL向上に寄与する枠組みを提供。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
食中7項目(量/角度/待つ/嚥下確認/水分/中断/記録)
- 量:最小一口量から開始
- 角度:スプーンは水平〜やや上向きで置く
- 待つ:嚥下→呼吸復帰まで必ず待つ
- 確認:喉頭挙上・残留を観察
- 水分:指示濃度のとろみ水で調整
- 中断:停滞時は中断→姿勢再セット→再開判断
- 記録:むせ回数・残留・使用した手順を残す
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
嚥下障害への姿勢・食形態工夫、ST訓練の位置づけを整理。介助操作の標準化が安全性を高める。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
口腔・嚥下評価と介入、残留への対応、経口維持のための多職種連携を提示。記録とフィードバックが介助精度を上げる。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
中断と再セット、観察・効果測定まで一連の手順を標準化する重要性を示す。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
とろみ6項目(計量/攪拌/時間/温度/最終確認/共有)
- 計量:粉量を計量スプーン・デジタル秤で統一
- 攪拌:方法・秒数を固定
- 時間:安定待ち時間を設定
- 温度:水温・飲料温を条件表で管理
- 最終確認:スプーンからの落ち方等で合意基準
- 共有:配膳票・申し送りに手順と変更点を明記
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
段階は形態で統一し、数値固定より運用の再現手順を重視。コード運用と解説理解で施設間のばらつきを抑える。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf農林水産省(参照掲載)
嚥下調整食分類2013(同一本文の参照版)
委託・メーカーとの段階整合・周知に役立ち、標準化と再現性向上を後押しする。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/pdf/07aka1_sankou3_gakkai_bunrui.pdf
連携4項目(申し送り/家族共有/歯科・ST・栄養/教育)
- 申し送り:オン時刻・むせ回数・残留・手順を定型フォームで
- 家族共有:同じ説明資料で合意形成
- 歯科・ST・栄養:評価→介入→再評価の導線を固定
- 教育:新任者向けに手順動画・早見表を用意
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
多職種連携・教育の有用性、オン・オフを踏まえた生活時間設計の重要性を整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
家族を含むユーザーにわかりやすい説明、多職種の同時介入を重視する実務枠組み。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
この22項目を一枚のチェックシートにして回すだけで、ばらつきは確実に縮みます。まずは明日の配膳から、同じ言葉・同じ順序で始めましょう。
FAQ:現場で迷いやすい5つの疑問を先に解いておく
同じ人でも日ごとに揺れるからこそ、よくある疑問を“型”で解けば判断が速くなります。ここでは安全と再現性を高める5問に絞って回答します。
- Qとろみの「正解濃度」はありますか?
- A
“数値だけの正解”より、学会分類2013の段階(0j/0t〜)を共通言語にし、計量→攪拌→時間→温度→最終確認の手順で同じ濃度を再現することが重要です。過濃は咽頭残留を増やす可能性があるため、一口量・ペース・姿勢とセットで調整してください。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
食事形態・とろみ段階を共通言語として定義。物性の一律数値化よりも、解説に基づく運用と手順標準化で再現性を担保する方針を示す。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
- Qオフのまま食事が進みません。続けるべきですか?
- A
安全>継続です。オフでは中断→姿勢保持→再セットへ。服薬・配膳・離床をオンに寄せる時間設計に見直してください。急かすほどリスクが上がります。再開は最小一口量から、チームで合図と言い回しを統一します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章/第III編 第4章)
日内変動(オン・オフ)への配慮、教育・食事指導の有用性、焦らせない支援の重要性を整理。進行期でも介入は有効と明記。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
- QPRD(蛋白再配分療法)は試すべきですか?
- A
症例により有効例はありますが、体重減少・ジスキネジア増悪に注意が必要です。まずは食後服薬や牛乳・制酸薬の同時服用回避など吸収阻害因子を外し、PRDは医師・栄養士と綿密に設計・評価してください。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章 非薬物療法Q&A)
L-ドパ吸収に影響する要因、PRDの有効性と留意点、食事指導の必要性を具体的に提示。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
- Qむせが続く時、最初の一手は?
- A
中断して姿勢を再セットし、残留の確認→指示濃度のとろみ水で洗い流し→再開可否を判断します。所見はむせ回数・残留量/部位まで記録し、ST・歯科・看護に共有して形態・一口量・ペースを見直します。
出典
厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
体位・口腔準備から食事操作、食後の口腔管理、評価までを一連のPDCAで標準化。誤嚥・窒息予防の具体的手順として中断と再セットを位置づける。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017
口腔・嚥下評価と介入、残留対応、経口維持のための多職種連携を整理。記録とフィードバックが介助精度を高める。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
- Q突然オンで立ち上がろうとします。止めるべきですか?
- A
否定せず、安全を添えるが原則です。手を添えて転倒予防、指示は一対一で簡潔に。オンは本人の貴重な持ち時間なので、食事・排泄・更衣など優先課題を進めます。二重課題は避け、状況と対応を申し送りに残してください。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第1章/第11章/第III編 第4章)
L-ドパの半減期の短さによる日内変動、オン時の機能活用、環境・課題設定(単一課題化)と安全確保の重要性を整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_09.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
迷いを型に置き換えると、誰が介助しても同じ水準に近づきます。施設標準のFAQとして配布し、毎日の申し送りとセットで運用してください。
まとめ:標準化(型)×時間設計×共有で、明日の一口を安全に
日によって揺れる食事介助を安定させるには、ばらつく工程を“型”に落とし、オン時間に寄せ、同じ情報で回すことが近道です。ここまでの要点を3本柱で締めくくります。
柱① 標準化(型)で再現性をつくる
姿勢・一口量・ペース・食形態(とろみ)・記録の5点を施設標準に。学会分類2013によるコード運用、とろみの計量→攪拌→時間→温度→最終確認の固定、むせ・残留・手順の同一書式記録で、誰が介助しても同じ水準に近づきます。
出典
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013(本文・解説)
食事形態・とろみ段階を共通言語化し、数値の一律化ではなく運用手順の標準化で再現性を担保する枠組みを提示。施設間連携での誤解を減らす。
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf厚生労働省
口腔機能向上マニュアル(2009)
体位・口腔準備・食事操作・評価までをPDCAで標準化。誤嚥・窒息予防とQOL向上に寄与する“型”づくりの重要性を示す。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf
柱② 時間設計(オンに寄せる)で安全と効率を両立
服薬・離床・配膳をオン時間に同期し、オフなら中断→姿勢保持→再セットへ。L-ドパ吸収に影響する因子(食後服薬、牛乳・制酸薬など)を避け、必要時はPRDを医師・栄養士と慎重に設計します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第III編 第4章/第I編 第11章)
教育・食事指導の有用性、L-ドパ吸収に影響する因子、日内変動(オン・オフ)を踏まえた時間設計、進行期でも介入有効である点を整理。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_27.pdf
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
柱③ 共有(多職種×家族)で現場を一枚岩に
歯科・ST・栄養・看護・介護・医師で同じ手順・同じ説明に統一。配膳票にコード・とろみ手順・オン時刻を記載し、むせ回数・残留の所見を共有。家族にも同じ資料で合意形成し、次の介入に反映します。
出典
日本神経学会
パーキンソン病診療ガイドライン2018(第I編 第11章)
多職種連携と家族教育をリハビリテーションの重要要素として位置づけ、継続と安全確保の枠組みを示す。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf日本老年歯科医学会
要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドライン2017/暫定版
口腔・嚥下・栄養の同時介入と、家族を含むユーザーへ分かりやすく伝える運用を重視。現場実装の具体枠組みを提供。
https://www.gerodontology.jp/publishing/file/guideline/guideline_20181130.pdf
https://www.gerodontology.jp/committee/file/job_link_20170626.pdf
明日やることはシンプルです。①チェックリストを配布、②配膳票にコードとオン時刻を追記、③申し送りの様式を統一。この三つで、今日より安全で短い“次の一口”に近づきます。
関連記事
更新履歴
- 2025年9月30日:新規公開








