不安になりますよね。呼吸がつらそうに見えるとき、食事でむせたとき、思いが伝わらないと感じたとき――「自分の支え方は合っているのかな」と迷うのは自然なことです。まずは同じやり方で統一すること、そして確かな根拠にそって進めることから始めましょう。
本記事は「日本神経学会 筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023」「日本呼吸器学会 NPPVガイドライン(改訂第2版)」「日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類2021」に基づき、独自の解釈を加えず、新人の方にも読みやすいように要点だけをやさしく整理します。
結論として、最初に覚えるべきは“基準”と“順序”です。
日本神経学会のガイドラインでは、機械を使った呼吸の補助が、ALSの方の暮らしと命を支えるうえでとても重要だと示されています。横になっていると息が苦しくなる・座っていないと楽に息ができない・朝起きたときに頭が重い/だるい・夜間に息が浅くなっているサインがあるときは、主治医と相談して夜からの呼吸の補助を検討します。
食事は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の基準に沿って、食べ物の形や飲み物のとろみを同じ基準で整えることが基本です。意思疎通については、日本神経学会のガイドラインで、早い段階から複数の手段(まばたきの合図、文字盤、視線を使う道具など)を準備することが勧められています。

この記事を読んで分かる事
呼吸がつらいときに始める支え方の目安、むせを減らす食事の整え方、弱った咳を助ける方法、声が出にくくなっても思いを伝える準備。公的な基準にそって、いつ・何を・どう進めるかが一つの流れでつかめます。
結論:‘基準’と‘順序’で整える――ALS介護の3本柱

焦りや不安があるときこそ、根拠に沿って同じ手順で進めることが安心につながります。まずは「呼吸」「食事」「意思疎通」の順で、現場で使える基準をそろえましょう。
呼吸:NPPVの意義を押さえ、兆候があれば導入を検討する
NPPVはALS患者の生命予後を改善する最もエビデンスレベルの高い治療と日本神経学会のガイドラインに示されています。起坐呼吸や夜間の酸素飽和度低下などのサインが見られたら、%FVC<80%やPaCO₂>45 Torrといった基準の有無を主治医と確認し、導入を検討します。夜からの開始や、睡眠の質・QOLの改善という目的を共有し、チームで同じ説明を用いて周知します。
ポイントは「サイン→客観指標→主治医と判断」という順序です。
%FVC < 80%とは?
これを一言でいうと「思いきり息を吐き出すパワーが、健康な人の8割以下に落ちていますよ」というサインです。
風船で例えてみましょう
- 肺活量(FVC)とは、風船をふくらませる時のように、「おもいっきり息を吸い込んで、一気に強くフーッ!と吐き出せる空気の量」のことです。
- 「%」 がついているのは、年齢や性別、身長が同じ健康な人(100%の人)と比べているからです。
つまり、%FVC < 80% というのは、呼吸をするための筋肉が弱ってきていて、健康な人のように力強く息を吐き出せなくなっている状態を指します。風船をパンパンにふくらませるパワーが少し落ちてきている、というイメージです。
介護士さんから見たポイント
まだ本人が息苦しさを感じていなくても、呼吸を助ける機械(マスクタイプの人工呼吸器など)の準備を考え始める、大事な目安の一つです。
このサインが見られると、咳をして痰を出す力も弱まっている可能性があります。
「最近、むせやすくなったな」「痰が絡む時間が増えたかな」といった変化に気づくきっかけになります。
PaCO₂ > 45 Torrとは?
体の中に“排気ガス”が溜まっているサイン:PaCO₂ > 45 Torr
これを一言でいうと「呼吸が浅いために、体の中の“いらないガス”をうまく外に出せず、溜まってきていますよ」というサインです。
工場と換気扇で例えてみましょう
- 私たちの体は活動すると、二酸化炭素(CO₂)という“排気ガス”を出します。
- 肺は、この排気ガスを体の外に追い出す「換気扇」の役割をしています。
- PaCO₂ とは、血液の中にこの排気ガスがどれくらい溶け込んでいるかを測る数値です。(Torrは圧力の単位です)
通常、換気扇(肺)がしっかり回っていれば、排気ガス(CO₂)はどんどん外に出ていくので、工場(体)の中はきれいです。 しかし、PaCO₂ > 45 Torr というのは、換気扇のパワーが落ちて、排気ガスを十分に外に出しきれず、工場の中に煙がこもり始めている状態です。これを「換気不全」と言います。
介護士さんから見たポイント
この状態は、特に夜間の睡眠中に呼吸が浅くなることで起こりやすいです。夜間に呼吸を助ける機械を使うことで、溜まった排気ガスをしっかり外に出せるようになり、日中の覚醒状態が改善することがよくあります。
二酸化炭素が体に溜まると、朝起きた時に頭痛がしたり、日中にうとうと眠そうにしていることが増えます。
「なんだか最近、日中ぼーっとしていることが多いな」という気づきは、このサインと繋がっているかもしれません。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 「非侵襲的陽圧換気(NPPV)療法は,ALS 患者の生命予後を改善する最もエビデンスレベルの高い治療法」(p.58/紙面47)
- 「%FVC<80%…起座呼吸…の場合に NPPV 導入を考慮する」
- 咳介助や他支援と合わせた呼吸リハの一環として計画的に進める(該当章)
食事:嚥下調整食分類2021で“同じ物性”にそろえる
日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類2021に合わせ、食形態(コード)ととろみ段階を標準化します。コードや物性を指示書・配膳・記録で同一表現に統一すると、場面が変わっても安全性と再現性を保てます。評価が必要なときはVF/VEへの相談ルートを作り、判断を個人技にしないことを徹底します。
ポイントは「分類に合わせる→同じ表記→同じ作り方」です。
出典元の要点(要約)
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2021
https://www.jsdr.or.jp/news/news_20210907.html
- 「嚥下調整食の情報を安全かつ円滑に共有するための基準」
- とろみは「薄い・中間・濃い」の段階で規定
- 食形態(例:コード1j・コード3・コード4 など)の物性を定義
意思疎通:早期から複数の代替手段を準備する
日本神経学会のガイドラインでは、構音・書字が難しくなる前から介入し、複数の代替手段を提示することが推奨されています。筆談・口文字・透明文字盤・視線入力装置を段階的に選択し、合図ルールの統一をチームで共有します。ALSでは眼球運動が比較的保たれることが多く、視線や瞬目を使う方法が基盤になります。
ポイントは「早期開始→多重化→合図の統一」です。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 「早期から介入し,進行をみながら複数の代替手段を提示する」
- 上肢機能に応じて筆談・口文字・透明文字盤を使用
- 「比較的眼球運動が保たれる」ため視線・瞬目を用いる
チーム運用:共通手順書で“同じやり方”を固定する
用語・フレーズ・手順を共通化した手順書を作成し、交代してもやり方が変わらない状態にします。呼吸(NPPVの導入可否と説明文)、食事(コード・とろみ・作り方)、意思疎通(合図・機器の設定)をひとまとめにし、記録と見直しの頻度も決めて運用します。ポイントは「書式を一つに」「更新を習慣に」です。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 多職種でのチーム医療と情報共有の推奨
- コミュニケーションノート等の活用提案
- ACPは診断後早期から繰り返す
迷ったときは、ここに戻れば大丈夫です。NPPVの意義→嚥下調整食分類2021で標準化→早期からの代替手段→共通手順書。この順序で、現場の不安を一つずつ小さくしていきましょう。
事例:現場でつまずきやすい“よくあるケース”3選

「どこから直せば良いか分からない」と感じる場面を、一次資料の基準に沿って整理します。基準に合わせる、同じ表現で統一する、チームで共有する――この3点を通して再現性を高めます。
ケース① 食事でむせが続く:まず“同じ物性”にそろえる
日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類2021で食形態ととろみ段階を標準化します。コードや表記を指示書・配膳・記録で同一に統一し、ばらつきを避けます。必要に応じてVF/VEで評価に進み、分類の選択を見直します。
- そろえる順序:分類の確認 → 表記統一 → 作り方統一
- 見直しの合図:食事時間の延長、むせの反復、体重の低下
出典元の要点(要約)
要約2
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2021
https://www.jsdr.or.jp/news/news_20210907.html
- 嚥下調整食の情報を安全かつ円滑に共有する基準
- とろみは「薄い・中間・濃い」の段階で規定
- 食形態(コード1j・3・4など)の物性を定義
ケース② 夜間に息が浅い:導入の“サイン”を手がかりにNPPVを検討
日本神経学会のガイドラインでは、NPPVがALS患者の生命予後を改善すると示されています。起坐呼吸や夜間の酸素飽和度低下、朝のだるさなどのサインがある場合、%FVC<80%、PaCO₂>45 Torrなどの基準の有無を主治医と確認し、導入を検討します。目的(睡眠・QOLの改善)をチームで共有し、説明文を同じ表現で統一します。
- 確認の順序:サインの把握 → 客観指標 → 主治医と判断
- 併用の要点:咳介助を呼吸リハビリテーションの一環として組み合わせる
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- NPPVは生命予後を改善する最もエビデンスレベルの高い治療
- %FVC<80%、起坐呼吸、PaCO₂>45 Torr、夜間の酸素飽和度低下などで導入を考慮
- 咳嗽力低下には用手的・器械的咳介助を推奨
ケース③ 声が出ない・伝わらない:早期から“複数の手段”を準備
日本神経学会のガイドラインでは、早期から介入し、複数の代替手段を提示することを推奨しています。筆談・口文字・透明文字盤・視線入力装置を段階的に用意し、合図ルールの統一をチームで共有します。ALSでは眼球運動が比較的保たれることが多いため、視線や瞬目を使う支援が土台になります。
- 段階の流れ:合図の統一 → 文字盤 → 視線入力装置
- 共有の要点:同じ合図・同じ記録で交代時の混乱を防ぐ
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 早期から介入し、進行に合わせて複数の代替手段を提示
- 上肢機能に応じて筆談・口文字・透明文字盤を使用
- 眼球運動が比較的保たれ、視線・瞬目を用いた手段が有用
迷ったら、基準に合わせる→同じ表現で統一→チームで共有の順序に戻ります。小さな修正でも、同じやり方を積み重ねることで安定が生まれます。
理由:なぜ「呼吸・食事・意思疎通」が中核になるのか
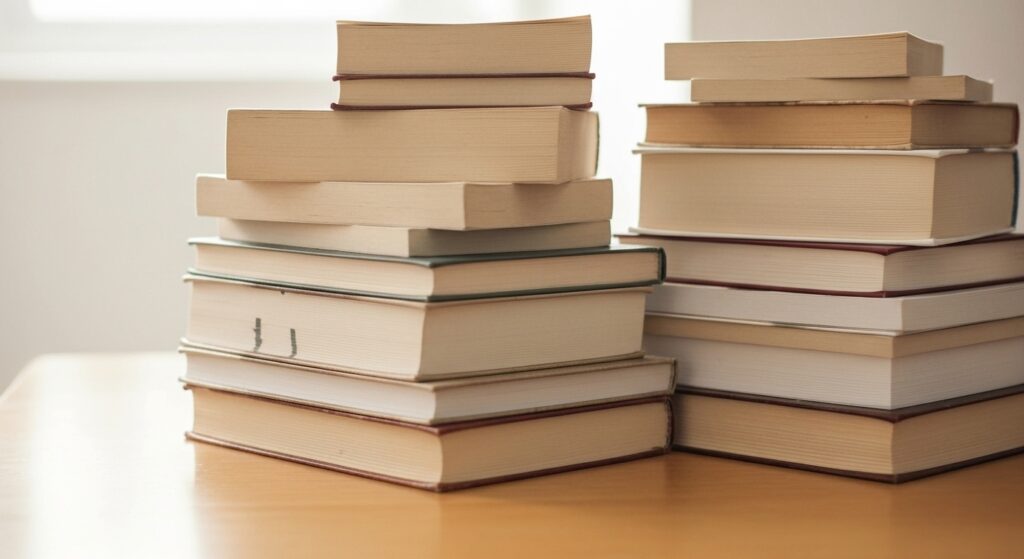
不安を減らす近道は、一次資料に示された基準と順序をそのまま運用することです。ここでは、根拠となる要点を整理します。
呼吸管理――NPPVは予後・睡眠・QOLの改善に直結する
日本神経学会のガイドラインでは、非侵襲的陽圧換気(NPPV)はALS患者の生命予後を改善する最もエビデンスレベルが高い治療と位置づけられています。導入は、起坐呼吸や夜間の酸素飽和度低下などのサインを手がかりに、%FVC<80%やPaCO₂>45 Torrなどの指標の有無を主治医と確認し、計画的に進めます。日本呼吸器学会のガイドラインでも、神経筋疾患における慢性呼吸不全はNPPVの良い適応とされています。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- NPPVはALS患者の生命予後を改善する治療
- %FVC<80%、起坐呼吸、PaCO₂>45 Torr、夜間の酸素飽和度低下などで導入を考慮
- 説明と同意のもと、計画的に実施
日本呼吸器学会
NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)ガイドライン(改訂第2版)
https://is.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/ajrs/004030262j.pdf
- 神経筋疾患の慢性呼吸不全はNPPVの良好な適応
- 夜間低換気の兆候が確認された時点で導入を検討
- QOLの改善と生命予後の延長に寄与
咳介助――喀出力低下には用手的・器械的介助を併用する
ALSでは進行に伴い咳嗽力が低下し、分泌物の喀出が難しくなります。日本神経学会のガイドラインでは、用手的咳介助と器械的咳介助(MI-E)を呼吸リハビリテーションの一環として行うことを推奨しています。これにより、誤嚥性肺炎のリスク低減と日常の安定につながります。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 咳嗽力低下に対し、用手的・器械的咳介助を推奨
- MI-Eは陽圧から陰圧への変化で喀出を促進
- 呼吸リハビリテーションの一環として計画的に実施
嚥下――嚥下調整食分類2021で“同じ物性”を共有する
日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類2021は、食形態(コード)ととろみの段階を標準化し、場面をまたいだ情報共有を可能にします。コードや物性の定義に合わせて提供すれば、むせや窒息のリスク低減と栄養・水分の確保に直結します。評価が必要な場合はVF/VEで客観的に確認します。
出典元の要点(要約)
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2021
https://www.jsdr.or.jp/news/news_20210907.html
- 複数の現場で安全に共有するための基準
- とろみは「薄い・中間・濃い」の段階で規定
- 食形態コード(例:1j、3、4など)の物性を定義
意思疎通――早期から複数の代替手段を準備する
日本神経学会のガイドラインでは、早期から介入し、進行に合わせて複数の代替手段を提示することを推奨しています。筆談・口文字・透明文字盤・視線入力装置を段階的に準備し、合図ルールを統一します。ALSでは眼球運動が比較的保たれることが多く、視線や瞬目を活かす支援が土台になります。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- 早期からの介入と複数手段の提示を推奨
- 上肢機能に応じて筆談・口文字・透明文字盤を選択
- 眼球運動を活かした視線・瞬目の活用が有効
TPPVとACP――切り替え判断は本人の意思を軸に繰り返し確認する
日本神経学会のガイドラインでは、NPPVの継続が困難、嚥下機能低下で誤嚥リスクが高い場合に気管切開下陽圧換気(TPPV)を選択肢として考慮します。導入に際しては、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を診断後早期から繰り返すことが重要です。本人と家族の意向を定期的に確認し、最新の希望に合わせて計画を更新します。
気管切開下陽圧換気(TPPV)とは?
一言でいうと、「マスクの代わりに、首に作った空気の通り道から、機械で呼吸を助ける方法」のことです。
NPPV(マスクで行う呼吸の補助)に慣れていると、イメージしやすいですよ。TPPVは、2つのパーツに分けて考えると分かりやすくなります。
① 気管切開(きかんせっかい)
これは、空気の通り道(気管)への「近道(ショートカット)」を首に作ることです。
通常、私たちは鼻や口から空気を吸い込みますが、ALSの進行などでそのルートを使うのが難しくなったり、唾液や食べ物が気管に入りやすくなる(誤嚥)リスクが高まったりします。
そこで、喉のあたりに小さな入り口を作り、そこに「カニューレ」という短い管を入れます。これにより、空気は鼻や口を通らず、直接、気管に届くようになります。
② 陽圧換気(ようあつかんき)
これは、機械が「がんばって!」と優しい圧力をかけて空気を肺に送り込み、呼吸を助けることです。
この「呼吸を助ける」という仕組み自体は、マスクで行うNPPVと全く同じです。弱ってきた呼吸の筋肉の代わりに、機械が呼吸の仕事を手伝ってくれます。
つまりTPPVとは、「気管切開」という空気の入り口を使って、「陽圧換気」という呼吸の補助を行う方法なのです。
なぜマスク(NPPV)ではなく、気管切開(TPPV)を選ぶの?
利用者さんやご家族がTPPVを選ぶのには、マスクと比べたいくつかのメリットがあるからです。
お顔周りがスッキリする: マスクによる皮膚トラブルや、ベルトの締め付け感がなくなります。
呼吸がより安定する: マスクのようにズレたり、空気漏れしたりする心配がありません。24時間、安定して呼吸を支えることができます。
痰の吸引がしやすい: 気管に直接アクセスできるので、奥の方にある痰も安全・確実に吸引できます。これは介護をする上で大きなメリットになります。
誤嚥のリスクが減る: カニューレのカフ(風船のような部分)をふくらませることで、唾液などが気管に流れ込みにくくなります。
TPPVは大きな決断ですが、より安全で安定した長期的な呼吸サポートを実現するための大切な選択肢の一つです。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- NPPV継続困難や誤嚥リスク高値でTPPVを考慮
- ACPは診断後早期から繰り返し実施
- 本人・家族の意向に基づき計画を更新
根拠をそろえて同じ手順で実行すれば、判断のばらつきが減り、日々の不安が小さくなります。次のセクションでは、現場で迷いやすい疑問に要点で答えます。
よくある質問(新人が最初に迷うポイント)

- Q呼吸が苦しそうなとき、NPPVはいつ検討しますか?
- A
起坐呼吸、夜間の酸素飽和度低下、朝のだるさなどのサインがある場合に検討します。%FVC<80%やPaCO₂>45 Torrなどの指標の有無を主治医と確認し、説明と同意のもと計画的に導入します。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
NPPVはALS患者の生命予後を改善する治療であり、%FVC<80%、起坐呼吸、PaCO₂>45 Torr、夜間の酸素飽和度低下などを手がかりに導入を考慮する。説明と同意のもと、呼吸リハビリテーションの一環として進める方針が示されている。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- QNPPVとTPPVの違いと、切り替えの目安は何ですか?
- A
NPPVはマスクで行う換気補助、TPPVは気管切開下での換気です。NPPVの継続が困難、または嚥下機能低下で誤嚥リスクが高い場合にTPPVを考慮し、ACPを診断後早期から繰り返して意思を確認します。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
NPPV継続困難や嚥下機能低下により誤嚥リスクが高い症例ではTPPV導入を考慮する。導入に際してはアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を診断後早期から繰り返し行い、患者・家族の意向を慎重に確認することが不可欠である。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- Q咳が弱く痰を出せないとき、どう支援しますか?
- A
用手的咳介助と器械的咳介助(MI-E)を組み合わせ、呼吸リハビリテーションの一環として計画的に実施します。喀出を促し、誤嚥性肺炎のリスク低減を図ります。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
ALSの進行で咳嗽力が低下した場合、用手的あるいは器械的咳介助(MI-E)を行うことを推奨する。MI-Eは陽圧から陰圧へ切り替えることで分泌物の喀出を効果的に促すと位置づけられている。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
- Q食事でむせが続くとき、食形態やとろみはどう決めますか?
- A
嚥下調整食分類2021に合わせて食形態(コード)ととろみ段階を標準化します。必要に応じてVFやVEで客観的に評価し、分類の選択を見直します。
出典元の要点(要約)
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2021
嚥下調整食は誤嚥や窒息のリスクを減らし栄養・水分を確保するための基準で、食事の物性と飲料のとろみ段階(薄い・中間・濃い)を標準化する。医療・介護・在宅をまたいで安全に共有できるよう設計されている。
https://www.jsdr.or.jp/news/news_20210907.html
- Q声が出にくくなったとき、意思疎通はどう準備しますか?
- A
早期から複数の代替手段を用意します。筆談や透明文字盤、視線入力装置などを段階的に提示し、合図ルールを統一します。ALSでは眼球運動が比較的保たれる特性を活かします。
出典元の要点(要約)
日本神経学会
筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023
コミュニケーション障害には早期介入が推奨され、進行に合わせて複数の代替手段を提示する。上肢機能に応じて筆談・口文字・透明文字盤を用い、眼球運動が比較的保たれる特性を活かして視線や瞬目を利用する方法を準備する。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/als_2023.pdf
まとめ:同じ基準でそろえ、同じ表現で共有する
本記事は、日本神経学会「筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023」、日本呼吸器学会「NPPVガイドライン(改訂第2版)」、日本摂食嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2021」の要約に基づいて、呼吸・食事・意思疎通を整理しました。要点は、NPPVの意義と導入の手がかり、用手的・器械的咳介助の併用、嚥下調整食による標準化、早期からの複数手段による意思疎通、そしてチームでの共通手順書化です。明日からは、用語とフレーズを統一し、記録と見直しを繰り返してください。
関連記事
更新履歴
- 2525年10月5日:新規公開









