忙しい現場で、徘徊の多い入居者につい薬で静かにさせたい…そう感じている方、いらっしゃいますよね?時間も人手も限られ、家族対応の重圧も重なる――その切実さは十分に理解できます。
結論は明確です。非薬物療法を第一選択として運用し、薬が必要な局面でも低用量で開始し、長期使用は避けます。使用中は常に減量・中止を念頭に、効果と不利益を定期的に再評価します。日本認知症学会のガイドラインでは非薬物介入を起点に整理し、厚生労働省の指針は高齢者の適正使用と継続的見直しを要請します。加えて化学的拘束の回避と尊厳の保持が制度面の要請です。
この記事を読んで分かる事
非薬物療法を第一選択とする理由、原因評価の要点、薬の最小有効量・最短期間・定期的再評価の基準、化学的拘束の回避と尊厳の保持を踏まえた実装の型を、一次エビデンスに沿って整理できます。
非薬物療法が推奨される明確な理由

忙しい現場で、徘徊の多い入居者につい薬で静かに…と感じている方、いらっしゃいますよね?まずは非薬物療法を第一選択とする根拠を、要点だけ端的に押さえましょう。
原因に直接アプローチできる
行動・心理症状は疼痛・排泄・睡眠・感染・薬剤性・環境刺激などの可変要因と関係します。最初に原因評価を行い、環境や関わり方を整えると症状が変化し得ます。日本認知症学会のガイドラインでは非薬物療法を第一選択と明示し、評価→介入→再評価の循環を求めています。
※出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
非薬物療法を第一選択に据え、原因評価と環境・関わりの調整を起点に、薬物は必要時のみ最小用量・最短期間で用い、効果と不利益を定期的に再評価し減薬・中止も検討する枠組みを示す。
https://dementia-japan.org/guideline/
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
高齢者の薬剤リスクが高い
高齢者は転倒・せん妄・過鎮静・嚥下低下などの薬物有害事象が起こりやすく、ADLや安全に影響します。厚生労働省の指針は最小有効量・最短期間・定期的再評価と全処方の把握、減薬・中止の検討を基本原則として示しています。薬より先に非薬物での調整が合理的です。
※出典
厚生労働省
高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
高齢者での薬物有害事象リスクに配慮し、必要最小限の処方、継続的見直し、効果と副作用の定期的再評価を求める。BPSDを含む高齢者診療の横断的原則として、適正使用と減薬・中止の検討を提示する。
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
化学的拘束を避け尊厳を守る
薬で過度に行動を抑える化学的拘束は、身体拘束等の具体例として整理されます。通常は非薬物療法を第一選択とし、緊急時に限り三要件(切迫性・非代替性・一時性)と詳細な記録を徹底します。尊厳の保持と制度順守の観点からも、薬の先行は避けるべきです。
出典
厚生労働省
介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き
身体的拘束等の原則禁止を明示し、化学的拘束を具体例として提示。例外は三要件と短期化・検証・記録を要する。通常運用では拘束回避と非薬物的対応の優先を求め、尊厳の保持に配慮する立場を示す。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
現場で迷ったら、非薬物療法を第一選択、薬は低用量で開始し、長期使用は避ける。使用中は常に減量・中止を念頭に、効果と不利益を定期的に再評価する。そして化学的拘束の回避。この三点を共通言語にすれば、安全と品質の両立へ一歩進めます。
事例:非薬物療法の有効性を現場ケースで理解する
「薬で静かにさせたい」と感じやすい場面を取り上げ、原因評価と環境・関わりの調整で落ち着きが得られるプロセスを、一次エビデンスに沿って要点化します。
夕方の不穏が強いケース
夕刻に興奮や帰宅願望が強まる。まず原因評価(疼痛・排泄・睡眠負債・薬剤性・環境刺激)を行い、照度を落として眩光と陰影を軽減、騒音源を整理し、整容や散歩など軽い活動で日中の覚醒と夕方の不安を調整する。非薬物療法を第一選択とするガイドラインの基本に沿う。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSDの初期対応として非薬物療法を第一選択に位置づけ、原因評価と環境・関わりの調整を起点に、必要時のみ薬物を最小用量・最短期間で用い、効果と不利益の定期的再評価、減薬・中止まで含めた運用を示す。
https://dementia-japan.org/guideline/
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
夜間の徘徊が続くケース
就寝前の覚醒刺激と日中活動の不足が背景になりやすい。日中活動の強化と短時間の昼寝にとどめる調整、就寝前のルーティンを一定化し、就寝直前のトイレ誘導と水分量の調整を行う。結果として夜間覚醒が減少し、ADLの維持と安全性が両立しやすくなる。
出典
国立長寿医療研究センター
認知症・せん妄ケアマニュアル 第2版
患者中心のケアとして、生活リズムの整備、日中活動の確保、環境調整、関わりの一貫性を基盤に据える。夜間覚醒や不穏に対して非薬物的な調整を行い、薬物使用はリスク・ベネフィットを踏まえ限定的に位置づける枠組みを提示。
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/nintishomanual2025.pdf
入浴拒否が続くケース
拒否の背景に、環境条件(温度・照度・騒音・湿度)や手順、生活歴との不一致がある。好みの時間帯への調整、脱衣室の温度・照度の適正化、騒音の軽減など環境面を整え、パーソンセンタードな関わりで拒否の要因を一つずつ是正する。具体的な声かけ手順は施設のSOP(標準手順)に準拠し、ガイドラインの一般原則(非薬物的介入の優先/継続的評価)と整合させて運用する。
出典
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017 第3章 治療
BPSDへの初期対応として、生活環境やケア手順の見直しを含む非薬物的介入を基本とし、薬物療法は有害事象に留意しながら必要最小限にとどめ、効果と不利益のバランスを継続的に評価する立場を示す。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_03.pdf
迷いやすい場面こそ、非薬物療法を第一選択、原因評価の徹底、環境と関わりの調整という共通言語で揃えることが重要です。これにより、過鎮静の回避と尊厳の保持、そして現場の安全性向上が期待できます。
理由:非薬物療法が推奨される根拠を一次情報でそろえる
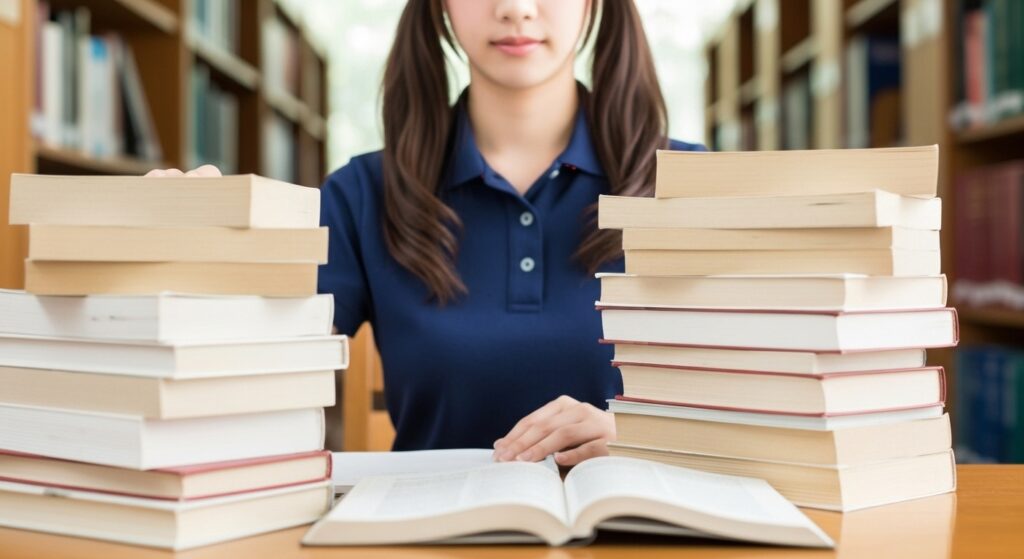
忙しい現場ほど「まず薬を」となりがちですが、ここでは臨床ガイドラインと制度文書が支える根拠を整理します。重なる結論は一つ、非薬物療法を第一選択に据えることです。
学会ガイドラインの合意がある
日本認知症学会のガイドラインは非薬物療法を第一選択に位置づけ、原因評価→介入→再評価の循環を明確化しています。日本神経学会のガイドラインも、環境・関わりの調整を初期対応の基本に置き、薬物はリスクと便益を秤にかけた必要最小限を求めます。
※エビデンス
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSD管理の基盤として非薬物療法を第一選択に据え、原因評価の徹底、環境・関わりの調整、薬物は最小用量・最短期間・定期的再評価と減薬・中止までを一体で運用する枠組みを示す。
https://dementia-japan.org/guideline/
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017 第3章 治療
認知症治療の総論として、BPSD初期対応に非薬物的介入(環境・関わり・身体要因の是正)を置き、薬物療法は有害事象へ配慮しつつ最小限で運用、継続的に効果と不利益のバランスを評価する立場を示す。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_03.pdf
高齢者の薬剤有害事象リスクが高い
高齢者は代謝や感受性の違いから、転倒・せん妄・過鎮静・嚥下低下などの薬害リスクが高くなります。厚生労働省の指針は処方の原則として最小有効量・最短期間・定期的再評価と全処方の把握、減薬・中止の検討までを明確に求めています。
出典
厚生労働省
高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
高齢者に特徴的な薬物有害事象の頻度と影響を踏まえ、必要最小限の処方、継続的見直し、効果と副作用の定期的再評価、減薬・中止の検討を横断的原則として提示。BPSD対応にも通底する基礎文書。
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
化学的拘束の回避と法令順守
薬で過度に行動を抑える化学的拘束は、身体拘束等の具体例として整理されています。平時は非薬物優先を徹底し、緊急時のみ切迫性・非代替性・一時性の三要件と詳細記録を求める運用が示され、尊厳の保持という制度理念とも一致します。
出典
厚生労働省
介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き
身体的拘束等の原則禁止を示し、化学的拘束を具体例として明示。例外は三要件の充足、短期化、検証、詳細記録を要件化し、通常運用では拘束回避と非薬物的対応の優先を求める。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
ADL・QOLの維持に資する
日中活動、睡眠リズム、環境整備、関わりの一貫性は、過鎮静による活動性低下を避け、ADL維持やせん妄・転倒の予防に資します。国立長寿医療研究センターのマニュアルは患者中心の非薬物的調整をケアの基盤に据え、薬物は限定的に位置づけます。
出典
国立長寿医療研究センター
認知症・せん妄ケアマニュアル 第2版
生活リズムの整備、日中活動の確保、環境調整、関わりの一貫性を中核とする患者中心のケアを提示。BPSDやせん妄に対し非薬物的介入を基盤とし、薬物はリスク・便益に基づく限定的適応とする。
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/nintishomanual2025.pdf
複数一次情報の結論が収束している
非薬物療法を第一選択、薬は必要最小限、定期的再評価、化学的拘束の回避――この骨子は学会・行政の文書で一貫しており、現場での標準判断として採用できます。重なる根拠が、実装のブレを抑えます。
出典
日本認知症学会/日本神経学会/厚生労働省/国立長寿医療研究センター
各ガイドライン・指針・手引・マニュアル(該当文書一式)
非薬物を第一選択とする立場、薬物の最小用量・最短期間・定期的再評価、化学的拘束の回避、患者中心のケアという骨子で合致。相互補完的に現場実装の基準を提供する。
https://dementia-japan.org/guideline/
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/nintishomanual2025.pdf
以上の通り、臨床的合理性と制度的要請の双方が、非薬物療法を先に選ぶことを支えています。次のセクションでは、この骨子を現場で迷わず使える形に落とし込みます。
よくある質問(FAQ)
- Q認知症でなぜ非薬物療法が推奨される理由は?
- A
行動・心理症状は疼痛・排泄・睡眠・感染・薬剤性・環境などの可変要因と関連し、評価と調整で変化します。学会ガイドラインは非薬物療法を第一選択に位置づけ、薬は必要時のみ最小有効量・最短期間・定期的再評価を求めます。
出典
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
BPSDの初期対応を非薬物療法に据え、原因評価(身体要因・環境・関わり)→介入→再評価の循環を提示。薬物はやむを得ない場合に限定し、最小用量・最短期間、定期的な効果・不利益の見直しと減薬・中止を枠組み化。
https://dementia-japan.org/guideline/
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
- Q認知症の非薬物療法は何から始めればよい?優先順位は?
- A
原因評価→環境調整→日中活動と睡眠衛生→統一した声かけの順で進めます。照度・騒音・動線の最適化、日中の覚醒保持、就寝前ルーティンの一定化が基本です。これらはADL維持や転倒・せん妄の予防に資します。
出典
国立長寿医療研究センター
認知症・せん妄ケアマニュアル 第2版
患者中心のケアとして生活リズム整備、日中活動確保、環境調整、関わりの一貫性を中核に配置。BPSDやせん妄への初期対応は非薬物を基盤とし、薬物はリスク・ベネフィットを踏まえた限定的適応とする立場を示す。
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/nintishomanual2025.pdf
- Q薬の方が早いと感じる場面では、どう使えば安全?
- A
開始する場合でも低用量で開始し、長期使用は避けます。使用中は常に減量・中止を念頭に、効果と不利益を定期的に再評価します。高齢者は転倒・せん妄・嚥下低下などの薬害リスクが高いため、非薬物を先に行い、薬は限定的に用います。
出典
厚生労働省
高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
高齢者の薬物有害事象リスクに配慮し、必要最小限の処方、全処方の把握、継続的見直し(減薬・中止含む)、効果・副作用の定期的再評価を通則として提示。BPSD対応を含む高齢者診療の横断的原則を整理。
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
- Q化学的拘束と非薬物療法の違いは?法的な位置づけは?
- A
化学的拘束は薬で過度に行動を抑える行為で、身体拘束等の具体例として整理されています。通常は非薬物療法を第一選択とし、緊急時のみ切迫性・非代替性・一時性の三要件と詳細記録を求める運用が示されています。
出典
厚生労働省
介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き
身体的拘束等の原則禁止を明示し、化学的拘束(向精神薬の過量投与等)を具体例として提示。例外は三要件の充足、短期化、検証、詳細記録を要件化し、日常運用では拘束回避と非薬物優先を要請。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
- Q家族から「薬で落ち着かせてほしい」と求められたらどう説明する?
- A
非薬物療法を第一選択とする学会ガイドラインの立場、薬の最小有効量・最短期間・定期的再評価という厚生労働省の原則、化学的拘束の回避という制度の要請を示し、原因評価と記録に基づく手順で合意形成します。
出典
日本神経学会/厚生労働省
認知症疾患診療ガイドライン2017 第3章 治療/高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
診療GLはBPSD初期対応に非薬物介入(環境・関わり・身体要因の是正)を基本化。適正使用指針は最小用量・最短期間・定期的再評価と減薬・中止の検討を通則とし、家族説明の根拠として活用できる。
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
まとめ:非薬物療法を第一選択にする理由を現場標準へ
非薬物療法を第一選択、薬は低用量で開始し、長期使用は避ける。使用中は常に減量・中止を念頭に、効果と不利益を定期的に再評価する。そして化学的拘束の回避。この三本柱は、学会ガイドラインと厚生労働省の文書で一致しています。原因評価(疼痛・排泄・睡眠・感染・薬剤性・環境)を起点に、環境と関わりの調整を先行させることが、安全・尊厳・業務効率のいずれにも合致します。今日から施設内で合意し、記録とカンファレンスで運用を継続してください。
出典:
日本認知症学会
BPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第3版)
https://dementia-japan.org/wp-content/uploads/2025/06/guideline.pdf
日本神経学会
認知症疾患診療ガイドライン2017 第3章 治療
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_03.pdf
厚生労働省
高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
厚生労働省
介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
国立長寿医療研究センター
認知症・せん妄ケアマニュアル 第2版
https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/nintishomanual2025.pdf
更新履歴
- 2025年9月26日:新規投稿



