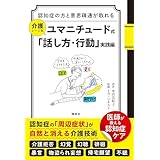認知症の入居者さんへの食事介助。 「もう食べた」「いらない」と拒否されてしまう。
フロア全体の時間も限られており、「早く食べていただかないと他の入居者さんのケアが…」と焦る気持ちと、うまくいかない現実との板挟みになっていませんか?
拒否が続くと、ご本人の栄養状態も心配ですし、介護士自身の「対応が悪いのでは」という心理的負担にもつながります。
しかし、その拒否は「わがまま」ではありません。ご本人なりの切実な理由が隠されています。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます。
【この記事を知っていると】
この記事を読むことで、食事拒否の裏にある入居者さんの「心理(不安や混乱)」を理解し、厚生労働省のガイドラインに基づいた「信頼できる具体的な対処法」を知ることができます。
結論:食事拒否を減らすための「3つの基本アプローチ」

時間がない中で「早く食べてほしい」と焦る気持ち、よくわかります。しかし、その焦りがご本人に伝わると、不安から拒否が強まることも。ここでは、厚生労働省のガイドラインに基づき、まず試してほしい3つの基本アプローチを紹介します。
アプローチ1:「安心できる環境」を整える
ご本人が食事に集中できない環境は、不安や混乱の原因となります。「ここは安心できる場所だ」と感じてもらうことが第一歩です。厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、慣れた場所で行うこと、そして集中できない時期を避けることを推奨しています。食堂が騒がしい場合は少し時間をずらす、いつもと同じ席に誘導するなど、ご本人が落ち着ける環境を優先します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思を表明できる条件を整えることを求める。
アプローチ2:「記憶違い」とは戦わず、「目的」を変えて提案する
「もう食べた」というご本人の“現実”を、真正面から「食べていません」と否定しても、混乱や怒りを招くだけです。厚生労働省のガイドラインは、焦らせるようなことは避けなければならないと示しています。「食事」として真正面から「食べていません」と否定することは、ご本人の“現実”を否定することにつながります。厚生労働省のガイドラインが示す「焦らせるようなことは避けなければならない」状況を避けるためにも、まずはご本人の言葉(「もう食べた」という認識)を受け止めることが重要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
言語表出が困難な場面では「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る」。進め方は「時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要」であり、「焦らせるようなことは避けなければならない。」として、拙速な促しを戒めている。
アプローチ3:「いらない」の本当の理由を探り、「選択肢」を提示する
「いらない」は、「お腹がいっぱい」という意味とは限りません。「入れ歯が痛い」「眠い」「味が好みでない」など、様々な理由が隠されています。厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、相手は「『認知症』ではなく、『人』」であると強調しています。ご本人の表情や仕草を観察し、意思表示として読み取ることが大切です。その上で、「お粥とパン、どちらがいいですか?」と複数の選択肢を示し、ご本人に「選んでもらう」ことで、自己決定を支援します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選択肢提示は「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解を助ける表現・媒体を用い、本人の「自己決定」に資する環境を整える。
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
相手は「『認知症』ではなく、『人』」である。意思疎通の過程を経ずに満足するケアは続かず、「良質なコミュニケーションに基づくケア」を求める立場を明確に示す。
これら3つのアプローチは、「説得して食べさせる」のではなく、「ご本人が安心して食べられる状況を整える」という視点に基づいています。まずはご本人の意思を尊重する姿勢が、信頼関係の第一歩となります。
理由:なぜ「もう食べた」「いらない」と拒否するのか?

食事拒否は「わがまま」ではありません。ご本人にとっては、そうするしかない切実な理由があります。その背景にある心理や理由を、認知症の特性から解説します。
理由1:「もう食べた」の背景にある記憶と時間の混乱
認知症の中核症状である記憶障害により、食事が終わったばかりだと本当に思い込んでいるケースがあります。また、時間や場所の感覚が不確かになる(見当識障害)ため、今が「食事の時間である」と認識できず、混乱から拒否につながることがあります。厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、認知症の人は説明された内容を忘れてしまうこともあり、その都度、丁寧な説明が必要であると示しています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
認知症の特性として「説明された内容を忘れてしまうこともあり」、支援者は「その都度、丁寧に説明することが必要」とされる。繰り返し説明を前提に、混乱や不安の軽減を図る。
理由2:「いらない」に隠された身体的な不快感
「いらない」という言葉は、体調不良のサインかもしれません。「いらない」という言葉は、必ずしも食欲の問題とは限りません。ご本人がうまく説明できない、言葉にならない身体的な不快感が隠されている可能性もあります。厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」、では厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、ケアの前提として「観る、聴く」というプロセスを挙げており、言葉にならない非言語的なサイン(表情の変化や仕草など)を読み取ることが重要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
認知症の特性として「説明された内容を忘れてしまうこともあり」、支援者は「その都度、丁寧に説明することが必要」とされる。繰り返し説明を前提に、混乱や不安の軽減を図る。
理由3:「いらない」に隠された環境への不安と認識のズレ
食堂が騒がしくて落ち着かない、介護士が忙しそうで急かされていると感じるなど、環境への不安が拒否につながることがあります。また、認知症の症状の一つである「失認」により、目の前にあるものが「食べ物」だと認識できない、あるいは「失行」により、お箸やスプーンの使い方がわからず混乱している場合もあります。厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、(周囲の)環境の影響もコミュニケーションの要素であると示しています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
利用者中心の実践として「コミュニケーションの成立する軸を 利用者に移す」。要素として「非言語的表現」「(周囲の)環境の影響」を重視する姿勢を示す。
このように、拒否はご本人なりの理由に基づいています。介護士がその理由を理解しようと努めることが、次のアプローチ(声かけ)の成功につながります。
よくある事例:アプローチ別の具体的な声かけと環境づくり

先に解説した「3つのアプローチ」を、現場でどのように実践するか。厚生労働省の資料を根拠に、具体的な声かけと環境づくりの事例を紹介します。
事例1【環境】:「慣れた場所」で「集中できない時期を避ける」
ご本人は、初めての場所や慣れない場所では緊張したり混乱したりすることがあります。厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、「慣れた場所で…行うことが望ましい。」と示されています。具体的には、できるだけ「いつもと同じ席」に誘導し、安心感を確保します。また、ご本人が「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」配慮も必要です。フロア全体が騒がしい時間帯ではなく、少し落ち着いたタイミングで声をかけるなどの工夫が有効です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
意思の表明が揺らぎやすい状況を避ける観点から、面談等は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」また「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」ことを求め、環境・時間の配慮を具体的に示す。
事例2【声かけ】:「焦らせる…避ける」ことと「ゆっくりと説明」の実践
時間がない中でも、介護士の焦りはご本人に伝わります。厚生労働省のガイドラインは、「焦らせるようなことは避けなければならない。」と明確に示しています。また、コミュニケーションは「本人と時間をかけて」取ることが重要です。さらに、同省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、「声の調子に気をつけてゆっくりと話す」ことを具体的なポイントとして挙げています。早口で説得するのではなく、落ち着いたトーンで「ゆっくりと説明」することが、ご本人の理解と安心につながります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
進行は「本人と時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要」であり、「焦らせるようなことは避けなければならない。」と明記。拙速な決定や急かしを避け、納得形成を重視する姿勢を求める。
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
身体的特徴に応じた配慮として、「はっきりとした声,聞こえやすい大きさ」で話し、「声の調子に気をつけてゆっくりと話す」ことを具体的ポイントとして示す。聴取と理解を助ける基本配慮である。
事例3【意思の尊重】:「複数の選択肢を示し」本人の自己決定を支援する
「いらない」という全否定も、選択肢が多すぎたり、何から手をつけて良いか分からなかったりする混乱から生じることがあります。厚生労働省のガイドラインは、情報提供の方法として「可能な限り複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」であるとします。例えば、「ご飯とお粥、どちらになさいますか?」「お茶と汁物、どちらから飲みますか?」と具体的に選んでもらうことで、ご本人の「自己決定」を支え、食事への意欲を引き出すきっかけになります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。
事例4【専門知識】:食形態が「いらない」の原因になっていないか確認する
「いらない」という拒否が、実は「飲み込みにくさ」から来ている可能性もあります。ご本人がうまく説明できなくても、むせが多い、口の中に溜め込むといった様子が見られる場合、食形態が合っていないかもしれません。専門職は、「日本摂食嚥下リ”ビリテーション学会嚥下調整食分類 2021」のような基準を用いて、ご本人の嚥下(えんげ)能力に適した食事(嚥下調整食)の段階を評価・選択します。介護士もこうした分類を理解し、多職種と連携することが重要です。
出典元の要点(要約)
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf
分類の「名称は,「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2021」」。内容は「食事(嚥下調整食)およびとろみについて,段階分類を示した.」とし、医療・介護での共通基盤を提供する。
これらの事例は、入居者さんの「意思」を介護士がどう読み取り、支えるかという視点に基づいています。一つの工夫が、ご本人の安心感につながります。
FAQ(よくある質問)

現場で生じる具体的な疑問について、介護士の視点で悩みやすいポイントを、ガイドライン等の視点から回答します。
- Qどうしても時間がない時は、どうすれば良いですか?
- A
現場では時間に追われ、焦ってしまうお気持ちはよくわかります。しかし、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、「焦らせるようなことは避けなければならない。」と示されています。焦りが伝わると、ご本人の不安はかえって強まります。もし時間がない場合は、「説得」するよりも、ご本人が「集中できない時期を避ける」ことを優先し、一度その場を離れて落ち着いたタイミングで再度関わる方が、結果的にスムーズな場合があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
タイミングは「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。進め方は「本人と時間をかけてコミュニケーション」を基本とし、拙速を避ける。
- Q感情的に拒否された時は、どう対応すべきですか?
- A
強い拒否や怒りは、ご本人の不安や混乱の表れかもしれません。厚生労働省のガイドラインは、言葉にならない「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る」努力を求めています。感情的な反応も、ご本人の大切な「意思表示」の一つです。真正面から説得しようとせず、まずは「そうですね、今は食べたくないのですね」とご本人の意思を受け止め、「本人の意思の尊重」を最優先します。無理強いせず、一度距離を置くことも大切なケアです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
言語表出が困難な場面では「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る」ことが求められ、支援者はその「努力を最大限に行うことが求められる。」非言語情報の重視を明示する。
- Q結局食べてもらえなかった場合、どう記録すべきですか?
- A
単に「食事拒否」と記録するだけでは、次のケアにつながりません。厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、ケアのプロセスとして「プロセス②····· 観る、聴く」ことを挙げています。記録は、この「観て、聴いた」事実を具体的に記載することが重要です。単に「食事拒否」と記載するのではなく、ご本人の言動や観察できた状況、試した対応などを記録することで、拒否の背景にある理由をチームで考察する材料になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
「専門職としてのコミュニケーション 5つのプロセス」の前半として、「空間をともにする」「観る、聴く」「対話する」を段階的に示す。導入から相互理解までの道筋を明確にする。
これらの疑問は、多くの介護士が共通して抱える悩みです。ご本人の様子を観察し、その意思を尊重する姿勢が、解決の糸口となります。
まとめ
「早く食べてほしい」という焦りと、「拒否される」ストレス。日々の食事介助、本当にお疲れ様です。この記事では、認知症の方の食事拒否の理由と、公的資料に基づいたアプローチを紹介しました。
食事拒否は「わがまま」ではなく、ご本人の不安や混乱、あるいは身体的な不快感からくる切実な意思表示です。厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、ケアの相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調しています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。
また、同省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」が示す「本人の意思の尊重」は、食事介助の場面でも変わりません。
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
「なぜ今、拒否しているのか」という視点を持ち、環境を整え、選択肢を提示することで自己決定を支えるアプローチは、ご本人の安心につながります。時間がない中でも、まずはご本人の“現実”を受け止めることから始めてみてください。それが信頼関係を築き、結果としてスムーズなケアにつながります。
関連記事
更新履歴
- 2025年10月24日:新規投稿
- 2025年11月1日:一部レイアウト修正